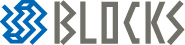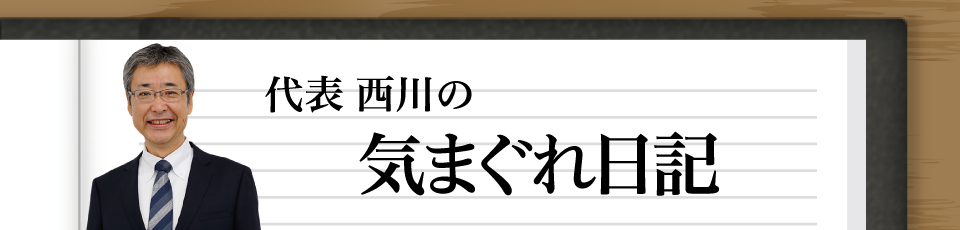2023 年 12 月 28 日 15:50
未来から考える
過去の実績から「今、何をやるべきか」ではなく、未来にどうなりたいかと目標を定め、そこから「今、何をやるべきか」と考える思考法を、バックキャストというそうです。
SDGsなどもそうした思考法。持続可能な社会を実現するために何をするか。過去の延長線上の未来ではなく、未来を定めてそこに線をつくるという考え方は、新しいものではないのかもしれませんが、過去の経験が生かしにくい、変化の大きな時代には、このバックキャストの思考法がより大切になってきているように感じます。
ただ、そうはいっても、つい過去の成功体験が頭によぎってしまい、過去のやり方を手放せないことも多い。これまで、これで上手くいったのだから、これで良いはずだ、過去のやり方を伸ばしていこうという発想になりがちです。特に私のように年齢を重ねれば重ねるほど、過去のやり方に囚われてしまいます。ただ、どんどん過去の知識や成功体験が通用しなくなる時に、それは足かせになってしまうこともある。
誰もが理想の未来を描き、そこに向かって今を考えるという思考の大切さはわかっていても、その実現が難しいのは、つい安定を望んでしまう思考の癖が原因なのかもしれません。
ただ、「世の中をより良くしたい」というモチベーションから、新しい企業を立ち上げ、これまでにないビジネスを展開する企業が増えているように、若い人にとっては、未来から今を考えることはもはや普通になのかもしれません。
しかし、過去の企業を見ても、戦後の混乱期に「世の中に役立とう」と高い理想を掲げ発展してきた会社もあるので、バックキャストは、決して新しい思考法ではないと思います。理念経営は昔から未来志向です。
未来をどう描くのか。どんな未来をつくり出したいのか。
経営者にとっても大切な思考ですが、働く人にとっても、「過去の実績を何%上げよう」と言われるより、未来志向の考え方の方がワクワクしてきます。
より良い未来をつくり出していきたいですね。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営
2023 年 12 月 18 日 15:51
主体性を育てる
自ら考え、自ら行動する。若手育成において、昔からよくこの大切さを言われていますが、何が正解か誰もわからない、やってみないとわからない時代にあっては、ますます、大切になっています。
しかし、なかなかそうならない。若手の育成に悩んでいる人のお話をよく聞きます。
新人も頭でわかっていても学生時代に手とり足取り教えられて育っていると、何かやろうにも、失敗が怖く、なかなか前に踏み出せない。自ら考え、自らやるというのは若手にとって思った以上に難しいのかもしれません。
しかし、社会人ではそれではなかなか難しい。何事も最初が肝心と言いますが、新人の頃に「自ら」を身に付ければ、その後の成長も違ってきます。わからないことばかりの新人には、何でもしてあげたくなりますが、手をかけすぎると「自ら」が育たない。教える側が問われています。
例えば、何かわからないことがあった場合、「教えてくれない」「教わっていない」とふてくされたり、待っていられるのは学生時代ですが、社会人なら「自ら聞きに行く」か「自ら調べる」の2択しかありません。こんな基礎から教えてあげないといけないのが今なのかもしれません。
我が家では、だいぶ前に子育ては終わりましたが、うちの場合、子どもが小学生の頃、朝子どもが起きてこなくても、親が子どもを起こしにいくことはしませんでした。寝坊するのは自分の責任。親は起こさないと決めているので、自分で起きるしかない。親のせいにもできません。時間通りに起きるようになりましたが、こんな子育ては昭和の時代。そうでない環境で育ってきた人も増えています。
しかし、今の若い人は社会に役立つ気持ちも高く、素直でいい面がたくさんあります。いかに良さを伸ばしてあげられるか。変わるべきは教える側かもしれません。
カテゴリー :
これからの時代の人財育成
2023 年 12 月 12 日 10:20
いい会社とは?
学生は「いい会社に入りたい」と言います。
我々も「いい会社だ」とか、「いい会社になろう」とか「いい」という言葉を使います。しかし、そもそも「いい会社」とはどのような会社なのでしょうか?
そもそも「いい」という定義は人によって様々。時代によっても変わります。しかし、「いい会社」というのが、我々がこれから向かう方向性だとしたら、「いい会社」のイメージが明確になっていなければ始まりません。
昭和の頃、有名企業に就職できると、周りから「いい会社に入ったね」と言われました。知名度があり、大企業が「いい会社」という時代もありました。しかし、無名であっても、価値ある製品を世に届けている会社もあります。また町の中にも根強いファンに支えられ「いい店だ」と愛され続けるお店もあります。もはや、全国的な知名度だけが「いい会社」ではなさそうです。
また、「成長したり、拡大している企業は将来性がある」とマスコミが騒ぎ、「急成長がいい」と思われた時期もありました。しかし、今日成長しているからといっても、そこで働く人が幸せだとは限りません。働く幸せもいい会社の必須条件になってきています。また、例えばお客様に安く商品を提供し喜ばれる会社でも、もしも、その裏で取引先に無理を言って叩いているようなことがあれば「いい会社」とは言えません。
「いい会社」をイメージするのは確かに難しいのかもしれません。ただ、今の世の中、「自分だけよければ、お金さえ儲かれば、今だけよければ」というような利己的な企業姿勢は、確かに嫌われているようにも見えます。
「いい」というのは、自分が「いい」というのではなく、関わるすべての人から「いい」と言われること。
昔の近江商人も「売り手よし、買い手よし、世間よし」ということを大事にしていたそうです。そう考えると「いい会社」とは、すべての人の幸せをめざす経営姿勢そのもの。そう考えると「いい会社」とは、業績や規模などではなく、その姿勢を持ち続ける会社だと言えます。
皆さんにとって「いい会社」は、どのような会社ですか?
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方
2023 年 12 月 06 日 10:15
お客様の立場に立つ
昔から営業や接客などで「お客様満足」を高めていくには、お客様の立場になる、お客様の目線になって考えることが大切だと言われています。ただ「お客様の立場に立つ」というのは意外と難しいもの。
そもそも、自分と相手は違う人間。相手のことはわからないのが普通です。しかも、売る側になると、つい売ろうという意識が強くなり、買う側の気持ちになかなか寄り添えません。
ましてや知識も経験があるプロ。お客様は素人。素人であるお客様が高い買い物をする時の不安や、そこにお金を出そうとする時にどんな気持ちになるのか。経験があるほど、お客様の気持ちがわかりにくくなってしまうのかもしれません。
「相手の立場に立つ」というのは、相手のことがいかに自分事として考えられるかということです。難しいとはいえ、高い買い物をする時ほど、自分のことのように考えてくれる人に対応してもらえると信頼は高まります。
先日、あるリフォーム会社で常に優秀な成果を出す一人の女性営業スタッフの方のお話を聞く機会がありました。成績は全国トップクラス。他の人の何倍も売る人だと聞いていたので、さぞ提案力や知識がある人かと思っていたのですが、その人が信頼されているのは、テクニックや知識ではなく、「お客様が、もし自分の家族なら」と考える、営業の姿勢でした。
お客様を逃がしたくない、何とか売り込みたいと思ってしまうと、つい、これが良い、こんな住まいが良いと売り込みや提案をしてしまいそうですが、その人は、お客様を自分の家族と思い、その方がどんな暮らしをしたいか、何を望まれているのか、リフォームに対するお気持ちを最初に徹底的に伺って寄り添っていくそうです。
売り手である前に、お客様を自分の家族や親戚のように思う。そうすると、だんだんと自分事のようになり、お客様が「こうしたい」と希望されたことに対しても「それよりはこうした方がよい」と一緒に考えたり、時には「今は、このまま使う方がいい。リフォームしない方がいい」と言ってしまうこともあるそうです。そんな姿勢で、工事が終わるまで家族の一員のように付き添うのが彼女のスタイル。断ってしまうと、売れなくなるのではと思いましたが、彼女の親身な姿勢にお客様は心から感動し、次々と契約が生まれているのだそうです。
自分の家族がお客様ならと想像すると、確かに無理な販売はしない。家族だと思えば、時には「それはやめた方がいい」ということもあるもしれません。「お客様が自分の家族だったら」という視点はシンプルですが、お客様を自分事としてとらえる上で、いちばん良い方法なのかもしれません。BtoBならば、自分がもし、その会社の社員なら、経営者なら、製造する人なら、「もし、自分の家族が使うとしたら」と考えることでしょうか。
そう考えることで、本当の意味でお客様目線で聞くことができ、真のお客様志向が生まれてくるのかもしれません。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 素晴らしい会社
2023 年 11 月 30 日 11:36
いきいきと働くことの価値
人に「仕事は楽しいですか?」と尋ねると、あたりまえですが様々な反応がかえってきます。即座に「楽しい」と言われる人。「楽しいなんて感じたことがない」という人。そもそも、給料をもらって働いているのだから、仕事はつべこべ言わずやるもので、楽しいとか、楽しくないということは言うものではないという意見を聞くこともあります。「楽しくなくてもやるのが仕事」というのが、世間一般的の認識かもしれません。「楽しくいきいきと働く」ということに価値や意義を感じていない人や会社は、まだ多いのかもしれません。
しかし、社員がいきいきと働いている会社は、そうでない会社より、業績が高いという研究結果もあるように、経営においても重要なテーマであり、同時に働く人のやりがいや生きがいからみても、いきいきと働けることは大切なことだと思います。
ただ、いきいきと働くというのは本当に曖昧です。いきいきに明確な定義もなく、こうすればいきいきと働ける、こうすればやりがいが高まるというような決まりもありません。いきいきと働くきっかけも人によって様々です。
例えば、面白くないと思って働いていたとしても、誰かに「ありがとう」と言われたりすると、自分の役割を感じて自分の仕事が違ってみえることもあります。人間関係の中で「やりがい」がみつかることがあります。
自分が一生懸命に取り組んだ仕事で、お客様が涙を流して喜んでくれた。そんな体験を通して仕事に誇りを感じることもあります。喜ばれることはやりがいになります。役立てた体験は心が躍ります。
また、マニュアル通りにやっていた時は楽しくなかったけど、初めての仕事に挑戦していく中で創意工夫をしている時にいきいきしてくることもあります。言われたまま仕事をしていると辛いけど、「自分が仕事をコントロールしている」と感じられる時は楽しいもの。だんだんと仕事ができるようになると、この楽しさが得られます。
それ以外にも、誰からも褒められない単調な裏方仕事。流れ作業のようにこなしていた仕事が、その先にお客様がいてそれが幸せにつながっていると実感できた時、自分の仕事が輝いてみえることがあります。自分の仕事は地味だけど、社会に役立っている。そんな体験をした時に、自分に誇りを感じるでしょう。
やりがいを感じる瞬間、いきいきとする瞬間は様々です。このような瞬間はいつ訪れるかわかりませんが、この中のひとつでも体験できれば、自分の仕事の見方は変わる。そんな人もたくさん見てきました。
だだ、やりがいを感じるかどうかは個人差もありますので、会社がこのためにやれることは少ないのかもしれませんが、例えば、仲間同士で「ありがとう」を言う。仲間を信じて仕事を任せる、裏方の人に感謝を伝える、仲間の頑張りを認める、褒める。お客様の感謝の声を共有する。小さなことならできることはあるのかもしれません。
こうやって仕事の中にはいろんな体験ができる。しかし、「そもそも仕事は楽しくないもの」と思っていると、こんな瞬間に出会っても素通りしてしまうのかもしれません。「いきいきと働く」ということに価値を感じるのか、そんな風に働きたいと願っているのか。最後はその人がどう働きたいかなのではないでしょうか。
8時間の労働時間をつまらない時間するのも、楽しい時間にするのも自分。楽しさは見つけたいと思う人だけが見つけられるのかもしれません。皆さんは、いきいきと働きたいですか?
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2023 年 11 月 22 日 09:52
見えるもの、見えないもの
当たり前の話ですが、世の中は目に見えるものと、目に見えないもので出来ています。
人間の身体は見えても、心は目に見えない。財産は見えても、幸せは目に見えない。命も見えません。
経営でも、利益や会社の状況は財務指標として見ることができますが、お客様からの信頼や社員のやる気というのは目に見えない。
今、大きな会社でもお客様からの信頼を失い、場合によっては倒産してしまうようなことが起こっていますが、会社にとって、財務指標には載らない、この目に見えない資産がなくなるととたんに経営が出来なります。お客様からの信用や信頼という目に見えないものは本来、数字以上に大事な資産。誰もがわかっていることなのに、見失うこともあります。もう一つの社員のやる気も、これがなくなってしまうと会社は存続出来ません。会社の風土という空気も見えませんし、理念という「経営の想い」も本来は見えません。命が人間をつくっているように、本来、見えないものがその本質で大事なことなのに、私たちはつい、目に見えるものを追いかけて、見失ってしまうこともあります。
見えないものを見るにはどうすればいいか。それが見えている人は、見ようとしている人だと思います。そこに関心があれば見えてくる。それを大事にしていれば見えてくる。何百年と続く老舗企業が先代から続く精神や理念を大事にしているように、社員がいきいきと働く会社は、社員の幸せを大事にし、お客様から信頼されている会社は、その信頼を大事にしている会社なのかもしれません。
あなたが大事にしている目に見えないものは何ですか?
カテゴリー :
経営理念の浸透・共感
2023 年 11 月 14 日 15:06
心が突き動かされるもの
先日、ある塾の講師の方のお話を聞く機会がありました。勉強嫌いの生徒のやる気をいかに高めるかということを一生懸命取り組まれてきた方で、その塾から何人も難関校への合格者が出ています。
どうすれば生徒のやる気を高められるのか。その方が取り組まれたのは、受験する「目的」をとことん聞くことでした。〇〇に合格するというのは目標ですが、目的があいまいな生徒はやはり最後まで頑張ることができない。なぜ合格したいのか?何のために勉強したいのか?勉強を始める前に、その人に向き合い、その理由をしっかり聴くそうです。自分が勉強する目的、その学校を受験する目的。そこがはっきりすると、生徒の目の色が変わり進んで勉強するようになる。こんな話を伺いました。
ビジネスの世界でも同じかもしれません。いくら数値目標や行動目標を明確にして取り組んでみても、その目標の奥にある「何のためにやるのか」という自分が進む理由、目的がなければ、最後は力がでない。あの山に登ろうと言われても、そこに「どうしても登りたい」という強い思いがなければ途中で諦めてしまいます。
そこに行きたいと思うかどうか。自分の心を動かされる目的があるかどうかは、社会人にとっても大切なことだと思います。
ただ、社会人の場合、どの組織でも組織の目的は明確になっています。我々は何のために働くのかは「企業使命」として理念に謳われています。それなのに、その目的が社員にとっての「登りたい山」になっていない場合もある。最近、行動指針を示し社員に徹底させようしているのに、なかなか現場で実行されないという悩みを伺ったことがありますが、これも目標の奥にある目的が語られていないからかもしれません。「どこをめざすか」「何をやるか」は明確になっていても「なぜやるか」がわからない。働く人が目的に心が突き動かされていないと、いくら行動を強制しても形だけになってしまいます。
組織の目的が自分も登りたい山であれれば自分から登ろうとする。そう考えると、企業の理念はやはり、働く人の心を突き動かすものであり、人がそこに行きたいと思う崇高なものでなければならないでしょうし、その理想と経営者の行動が一致していなければ、誰の心も動くはずがありません。
自分の心を突き動かす目的があれば努力は継続する。やる気の源泉はやはり「目的」だと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 11 月 07 日 17:29
頑張るエネルギー
もう何十年も続くテレビ番組、「はじめてのおつかい」。番組では、子どもたちが頑張る姿が映し出されていますが、その子どもの姿に親も感動し、司会者もゲストの人たちも涙し、視聴者の私もいつも励まされます。
「あの人があんなに頑張っているんだから、自分も頑張ろう」。誰もがこんな思いを持ったことがあると思いますが、子どもに限らず、誰かが一生懸命がんばっている姿は、やはり周りの人に大きな影響を与えます。
私も自分の子どもが一生懸命頑張っていると、自分も頑張らねば、と思いますし、逆に子どもも、親が頑張っている姿に励まされることもあるかもしれません。誰かの頑張るエネルギーが人の頑張るエネルギーになり、成果も生まれる。世の中はそんなエネルギーで出来ているのかもしれません。
チームで何かを成し遂げようとする時も、誰のひたむきに取り組む姿勢がチームを盛り上げることもあるように、頑張っているエネルギーは人に伝染していきます。ただ、頑張る姿が美しく感じるかどうか、人に伝わるかどうかは、そこに駆け引きがない時かもしれません。「私はこんなに頑張っているのに、なぜ、みんなは頑張らないのか」と思っているような時は伝わらない。ただ、純粋に目的に向かって一途に頑張っていくような人の頑張るエネルギーだけが自然と人に伝わっていく。何のために頑張るか。そのことを行う動機が大事なのかもしれません。
会社も同じ。どの会社もスタート地点はゼロからのスタート。会社を大きくしようと一生懸命がんばる社長がいるからこそ社員も頑張る。そこで働く先輩社員の頑張る姿が若い社員に伝わり、頑張るエネルギーが相互に影響し合って会社が発展していきます。利己的なリーダーではなく利他的なリーダーが、もっと、お客様に役に立とう、もっと社員のためにと頑張る。そんな姿に人は動かされていきます。お金が人を動かす動機になることもありますが、やはりリーダーが理念に向かっていく姿勢こそが、いちばん人を動機づけるものになるのではないでしょうか。最近、よく理念浸透が話題になりますが、どれだけ社員に理念を教えていても、リーダーが理念に必死でなければ伝わる訳はありません。理念の浸透でいちばん大事なのは、リーダーや先輩の頑張る姿勢なのかもしれません。
カテゴリー :
経営理念の浸透・共感
2023 年 10 月 24 日 11:34
仕事の意義と経営理念
給料よりも生きがいのある仕事をしたい。
最近、20代~30代のあいだで、こんな風に「意義ある仕事」を選ぶ人が増えているそうです。人生の3分の1を過ごす仕事を、意義を感じないまま過ごすより、自分にとって幸せな働き方を選びたい。昭和の時代は、例え意義を感じなくても、仕事は我慢してやるものだと言われたことを一生懸命にやってきましたが、令和の時代はそれでは頑張れない。自分の仕事が社会の役にたっていると感じられたり、仕事を通して自分の成長が実感できたり、仕事をやることに意義を感じられないことはやりたくない。例え給料が低くなるかもしれないが社会に役立つ仕事をする。こうした価値観の人の割合は、今後もどんどん増えていくと言われています。今後、益々採用が難しくなってくる時代の中で、若い人を採用するためにも「仕事の意義」は大きなテーマになっていくのかもしれません。
自分の仕事に意義を感じる。
意義を感じない時は、仕事はやらされる仕事になりますが、「自分のやっていることは、社会の役に立っている良い仕事だ」と感じられるときは、人は進んで行動します。目的を達成しようと思うと「もっとこうしよう」と創造的なアイディアも出る。意義を感じていると辞める人が少なり、採用も困らない。働く人が仕事の目的に共感しているということは組織にとっても良いはずです。
しかし、いくらそれが大事だとわかっていても、企業の現場が実際にそうなっていないことがある。職場の先輩は誰も「仕事の意義」を語らない。問われるのは数字だけ。ただ仕事をこなし、ただ毎日を過ごす。意義を感じなくても日常は過ぎていく。「仕事とはそんなものだ」と言われても、意義を求める若い人にとって、ずっと、そんな職場で働いていていると不安になってしまいます。
仕事の意義。その根本にあるのが経営理念です。
職場の誰も意義を語らないというのは、文章として経営理念があったとしても、その経営理念が職場の中に生きていないということになります。当たり前になってしまっているその現状がいちばんの問題なのかもしれません。
経営理念は誰のためにあるのか。何のためにあるのか。
もちろん、顧客や社会に対して自社の姿勢や方向性を示すという意味もあると思いますが、今、いちばん必要としているのは働く人。自分の仕事の意義を感じたい、やりがいを感じながら働きたい。働く人のためにも、経営理念が大事になってきているように思います。
カテゴリー :
経営理念の浸透・共感
2023 年 10 月 17 日 18:11
組織の壁の壊し方
組織の壁、部門の壁というのは、昔からよく聞く話ですが、壁というのはなぜ出来てしまうのでしょうか。
先日、顧客満足が高いホテル、大阪の「道頓堀ホテル」の経営改革の話を伺う機会がありました。
道頓堀ホテルは、今でこそ稼働率9割を超える顧客から人気の高いホテルですが、20年ほど前は、組織の中に厚い壁がいくつもある古い体質の会社で、経営は赤字になっていたそうです。当時から働く料理長に伺うと、その当時は、他の部門の人と口をきくこともなく、それぞれが自部門のことだけを考える風土だったそうです。調理部門は「美味しい料理」を作るプロであり、それを提供するのが仕事。営業部門やサービス部門から、何か依頼されたとしても、「こっちには関係がない」「料理にケチをつけるな」とまったく相手にしない。「他部門は敵だ」というくらいに感じていて、大きな壁がいくつもあったそうです。
そうした状況の中で、三代目の経営者によって道頓堀ホテルの経営改革が始まったのですが、料理長にとって壁を超える転機になったのは、それぞれの部門長と参加した外部の勉強会だったそうです。最初は嫌々参加していた勉強会でしたが、回を重ね、飲み食いをしているうちに少しずつお互いを知るようになり、他の部門がどれだけ大変なのか、どんな思いで働いているかがわかるようになりました。そんな中で、少しずつ他部門への気持ちが変わっていったそうです。無理やりでも参加した「共通体験」の場がわかり合う機会になった、と言われていました。
その勉強会では、自分の仕事の目的を考える機会があったそうです。何のために仕事をしているのか。その問いに向かっていく中で、調理部門は、本当は料理を作ることが目的ではない、料理を通してお客様に喜んでもらうことが目的だと気づかれます。美味しいものを作るのが本来の料理人であるという昔堅気の世界で育った料理長にとって、大きな価値観の転換。しかし、「目的」がわかると、料理を運んでくれる人、宴会を受注してくれる人など他部門への見方も変わり、会社の理念が改めて腹に落ちたと言われていました。
それぞれの部門で、各部門の目的の先にある「大きな目的」が腹に落ち、「部門は違っても私たちは同じ目的に向かっている仲間だ」と感じられるようになると、自然と協力や助け合いが生まれ、当然、お客様からの評価も高くなり、顧客満足もどんどん上がっていったそうです。
会社に限らず、家族でも、スポーツでも、人と人との行き違いは「わかりあえていない」ことから生まれるもの。「わかりあえていない」状態をほっておくと「壁」が生まれ、余計にわかり合えなくなり、敵対心まで生まれてしまいます。最初はストレスがあったとしても、やはり、時間をかけても、じっくりと話し合うことがいちばん大事なのでしょうか。
しかし、そもそも、何のために部門があるのかと考えれば、全体で良いものを生み、お客様に満足していただくために生まれたもの。その共通の目標、目的を忘れるから、壁が生まれる。とすれば、壁があるのは、数字ばかりに目が向いて、理念が形骸化したり、蔑ろにされているのかもしれません。
カテゴリー :
DOIT! 「いい会社」が実践する理念経営 素晴らしい会社
2023 年 10 月 10 日 18:03
お客様に熱心な営業
以前、ある方から、「熱心な営業」と「しつこい営業」は紙一重であるという話を聞いたことがあります。営業スタッフは、自分の商品に自信を持って顧客に紹介する。断られても、何度も何度もお客様のところに通い、熱い思いを持って商談をする。しかし、同じようにお客様に向かっていても、ある人は顧客から「しつこい営業だ」と嫌われてしまう。しかし、ある人は「熱心な営業だ」と好意を持たれる。この違いはどこにあるのでしょうか。
お客様に「しつこい」と思われる人は、どうしても売りたい、自分の成果を上げたいと思う気持ちが強い人。しかし、同じ熱意を持っていたとしても、お客様のことを第一に考え、どうすれば喜んでくださるかという気持ちが強い人は「熱心だ」という評価になる。熱意の方向が自分の為か、相手の為かが違う。それが「熱心」と「しつこい」の差であり、やはり営業はお客様本位でなければならないというのが、その方のお話でした。
しかし、営業は数字をあげてこないと評価されないという空気があり、つい結果を出すことに頭が働いてしまいます。熱心に訪問し、熱心に説明をする。その熱意は絶対に大事なことですが、「売りたい」という気持ちばかりだとお客様は嫌になってしまいます。その人の根底にある思いは、小さな差になって、相手に伝わってしまうものなのかもしれません。
以前、私の会社を担当するある営業スタッフに、その人の業務範疇を超える悩みを話したところ、その解決に親身になって動いてくれました。商売にならないことなのに、親身になって考え行動してくれたことに私は感動し、それ以来、ずっとその人に依頼するようになりました。売ろう、売ろうとその人が一生懸命になっている時は、信頼できなかったのに、そんな小さなことから、信頼が生まれていきました。顧客は顧客に熱心な人から買いたくなる。そんなことを感じたことがあります。
自分の数字に熱心な営業ではなく、お客様に熱心な営業。求められる営業も変わっていっているのかもしれません。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上
2023 年 10 月 03 日 17:22
空気の影響力
いい会社を訪問すると「良い空気」を感じます。
士気が高い、みんなが笑顔、助け合って働いている。活気があり、いきいきとした空気があります。
「空気」というのは、人の心が作り出す全体的を包む雰囲気。日本人は、この空気に左右されやすいと言いますが、私たちは、何となくその場の空気につい影響を受けてしまいます。
例えば、野球。終盤に大きな点差になるとベンチが「負けムード」になる。そうなると、今まで声を出していた選手が声を出さなくなり、やる気も下がる。いつもなら出ないようなミスが出たりする。
会社の会議でも、上司が一方的に話をしている時は、何か反対意見を言いにくい空気が生まれます。おかしいなと思っても、みんな黙ってしまう。
しかし、野球でも、ヒットが続き、「やれるぞ」という空気になると、昨日打てなかった人がヒットを打つ。勝ちムードになると作戦も上手くいくことがあります。
会議でも、みんなが笑顔で、意見をどんどん発言するような空気の時は、新人も何となく自分も意見を言わなくてはと思い、発言する。上司が笑顔でいるだけで、反対意見を言ってもいいという気になる時もある。「空気」は、悪い方向にも影響していくし、良い方向にも影響します。
しかし、「空気」は見えないし、科学的に解決するものでもなく、なかなか手が出しにくい。ただ、組織の空気が悪いと、社員の士気は下がり、仕事も停滞する。挑戦も生まれないし、長く続くと息苦しくなることもあり、空気が社員満足に影響することもあります。「こうしたらもっと良くなる」と、もしもいいアイディアを持っていても、言い出しにくい空気では意見を出しにくい。先輩に相談しても、ムスッとされると意見を言うのも嫌になる。みんながそんな空気になっている時に、やる気など出るはずがない。
では、どうすれば、「良い空気」をつくれるか。やはり、いい空気も悪い空気も、作っていくのはその場のリーダーなのだろうと思います。しかし、負けムードの時に、一人の選手が声を出し始めて、一気に空気が変わることもあるように、リーダー以外の人であっても、空気を変えることできるのかもしれません。あえて空気を読まない人が空気を変える時もあります。
職場の「空気」とは、つまり組織風土。良い「空気」が社員のやる気を高め、満足につながっていくとすれば、「よい空気」をつくっていくことがいちばん大事なのかもしれません。
あなたの職場は、今、どのような空気ですか。
カテゴリー :
素晴らしい会社 素晴らしい組織風土づくり
2023 年 09 月 26 日 15:06
問題解決と問題対処
仕事の中でも、日常生活の中でも、次から次への問題が起こります。この「問題」をどう解決していくか。そのアプローチで結果が変わっていきます。
社員が自律的にいきいきと働く自動車ディーラー、ネッツトヨタ南国の創業者、横田英毅さんは、「問題対処」ではなく「問題解決」が大事だと言われています。
横田さんから伺った話がいちばんわかりやすいので、引用させていただくと、例えば、一人の空腹の人がいたとする。問題は空腹で困っていること。この人に魚を一匹与えれば一日は食べることができます。しかし、それは問題対処。一日空腹が満たされても、次の日また問題が起こる。しかし、その人に魚の取り方を教えれば、その人は一生食べていけることができる。これが問題解決。問題に対して、直接的な、見えている部分にアプローチするのが問題対処。見えにくい部分にアプローチしていくのが問題解決だということです。
例えば、「売上が未達になりそうだ」という問題が起こった時に、訪問件数を上げるように指示するようなことは問題対処。そもそもなぜ未達という状況になってしまうのか、その根本原因に目を向ける。確かに今月のためには、すぐに問題対処をしないといけませんが、解決しなければまた問題が起こってしまいます。
しかし、この問題解決というのは、見えない原因を探ることなので、なかなかすぐに解決策が見つけられない。もし、見つかったとしても時間がかかることなのでなかなか手をつけないという問題もあります。例えば、空腹の人に魚を与える例でいえば、確かに魚を一匹与えることはその場限りだとわかっている。しかし、その人に魚の取り方を教えることは、時間も手間もかかるので躊躇してしまう。仕事の中でも、対処、対処で済ませてしまおうとすることはたくさんあるのかもしれません。しかし、そうやってその場をしのいでもまた問題が起きてしまう。火事になったら消火するという問題対処も必要です。でも、火事になる要因を見つけて火事が起こらないようにしなければ同じことが起きる。やはり、時間がかかっても、問題解決をしないと物事は進化していきません。
働く人が幸せになる会社をつくろうとされた横田さんは、働く人のやりがいがいちばんの要因だと考えられ、トップが指示命令をしない、社員の人たちがお客様のために自分で考え行動する組織をつくってこられました。問題を発見する。そして、時間がかかっても、問題解決にトライする。仕事でも、経営でも、日常生活でも、このスタンスがいちばん大事なのかもしれません。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営
2023 年 09 月 21 日 10:22
公私が混ざる職場
いきいきと働く職場づくりを考える上で、メンバー同士の協力関係は欠かせません。
以前、社員満足度の高いネッツトヨタ南国の職場で働く人に「この職場のどんなところがいいですか?」とインタビューをした時、ある女性スタッフが「ここのメンバーはみんな協力体制ができているんです。私は子育てをしながら働いているのですが、今日も子どもが急に熱を出ししていまい、病院に連れていかなければならなくなったんですが、みんなが私の仕事を助けてくれるんです。このメンバーじゃなかったら、今の私はいないと思います」と話してくださったことがあります。
困った時に助けてくれる人がいる。応援してくれる人が傍にいる。仕事の悩みはもちろん、家族の悩みまで相談できる職場。そんな職場だからこそ、人は思い切って働けるのだと思います。
子育てをしながら働く、病気の親の面倒を見ながら働く。多くの人がいろんな事情を抱えながら働いていると思います。私自身も少し前まで認知症になってしまった親の面倒を見ていましたが、仕事と親の世話の両立は大変でした。仕事と私生活は分けるべきだという意見もあるかもしれませんが、家庭に問題があれば仕事中も気になりますし、家庭のことをしている時でも仕事のことは気になってしまう。私生活と仕事を分けるのは無理なことではないでしょうか。
お互いにいろんなことが相談できる。いろいろな家庭の事情を気軽に話ができて、職場の仲間がその人の事情を考えメンバー同士で相談しながら、最適な仕事をする。家庭の事情を職場に持ち込むなではなく、もっと家庭の事情を持ち込んでいく方が、全体としての効率が上がっていくのかもしれません。今、うちの会社にも、病気の子供を抱えながら、小さな子供の面倒をみながら働く社員がいますが、みんながその事情を察し、助け合って働くことで良いチームワークが生まれています。
公私混同という言葉は良くない意味で使われることがありますが、良い意味もあるのかもしれません。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2023 年 09 月 12 日 15:29
「小さな不満」に向かう企業
顧客に見えることが、企業が見えないことがあります。
自分も顧客として体験したことがありますが、例えば、忙しすぎるお店に行った時、ぞんざいに扱われてしまったりする。忙しい時間だからしょうがない、と納得はするものの、少し嫌な気がします。また、例えば通販で購入した商品に小さな傷がついていることに気づく。性能上は問題がないから、「まあいいか」と使うことにする。日常生活の中で、些細な「嫌なこと」に出会うことが時々あります。
きっと、どの企業でも、企業が気付かないうちにお客様に「嫌なこと」をしてしまっていることがあるはず。
でも、こうした見えない不満を活かすこともできる。そんな企業のひとつがユニクロ。昔の話になりますが、創業間もないユニクロが、新聞一面に「ユニクロの悪口を言って100万円」という広告を出したところ約1万通の応募があり、実際に100万円を支払ったという有名な話があります。より良い商品をつくるために、あえてお客様の不満を集めたことで、何を改善すれば良いかがわかり、これが同社の躍進の転機になりました。小さな不満を解消することで多くのヒット商品が生まれていったそうです。
また、食品会社のミツカンも顧客の声に真摯に向き合う企業のひとつ。ヒット商品である、「金のつぶ」(納豆)は、容器がパキッと割れてタレが出てくる商品ですが、あれも「たれが開けにくい・手が汚れてしまう」という顧客の不満をきっかけに、長年研究して開発された画期的な容器です。もっとお客様に喜んでほしいという同社の姿勢が生んだヒット商品。「開けにくい」という小さな声を無視しなかった企業の姿勢に感動を覚えます。
クレームは宝物と言われていますが、発生したクレームへの対応はもちろん、いかに企業が知らないうちに提供してしまっている「小さな不満」にも向き合っていくか。もっと喜んでほしい、もっと役立ちたいという姿勢がそうした行動を生みます。今、問われているのは企業の姿勢なのかもしれません。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2023 年 09 月 05 日 15:08
やりがいを見つける力
よく、私たちは「この仕事はやりがいがある」「この仕事はやりがいがない」ということを言いますが、よく考えてみると、仕事は仕事であり、それぞれの仕事に「やりがい」という色がついている訳ではありません。
例えば「トイレ掃除」。この仕事を「嫌な仕事を押し付けられた」「やる気にならない」とだらだらとやる人もいれば、同じ掃除でも「みんなが使うトイレだから、少しでも綺麗にしよう」と一生懸命、取り組む人もいる。当然ながら、やりがいを感じていると仕事は楽しくなり、感じていないとつまらなくなります。つまり、「仕事」には色がなく、色を付けているのは人です。
「やりがいがある」とは「仕事の意義」を感じている状態です。トイレ掃除でいえば、後者の人は、仕事の奥にある「意義」に気づけた人。前者の人は、意義に気づけない人とも言えます。意義を感じる仕事は、前向きに取り組める。では、なぜ、意義に気づける人と気づけない人が生まれるのでしょうか。
今、自分の仕事に意義を感じている人でも、もしかすると、最初の頃は、「なんで私がトイレ掃除を・・・」と思っていたかもしれません。ただ、どんな仕事も一生懸命に取り組んでみると、誰かから感謝されたりする機会に出会うことがある。一生懸命に取り組んだ。思わず、人から感謝された。そんな体験の中で、自分の仕事が「人に喜ばれる仕事だ」という意義に気づくことがあります。
最初は「嫌だな」と思いながらも、「とにかく一生懸命にやってみよう」と切り替えて、集中して取り組んでみると、仕事の「奥深さ」に気づくことがあります。例えば「水を流すだけでは綺麗にならない」という壁にぶつかる。そこで「どうすれば、綺麗にできるか」と工夫する。それが成功する。そんな体験を通して「トイレを綺麗にする」ということの難しさや面白さに気づくこともあります。
多くの人が体験されているかもしれませんが、やりがいを感じていなかった仕事が、やっているうちに、やりがいのある仕事に変わることがあります。一生懸命にやってみないと、その仕事に「やりがい」があるかどうもわからない。「やりがい」は、やった後にしかわからないものです。
とすれば、どんな仕事も「やりがいのある仕事」にすることもできるし、「つまらない仕事」にもすることもできる。
大事なのは、そこに「やりがいを見つける(意義を見つける)力」なのかもしれません。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 08 月 29 日 10:21
やる気と行動
私たちは日頃、「やる気がある」「やる気がない」という言葉を使いますが、そもそも「やる気」というのは、どんなことなのでしょうか。
最新の脳の研究によると、脳が諦めた時にやる気がなくなるのだそうです。
私たちの脳は、いつも結果を予測してから実際に行動し、その時に得られた結果との誤差を埋めようと調整し、その情報を蓄積していくのだそうです。例えば、100点を取ろうとテストを受けて、何回受けても30点しか取れないというような「小さな誤差」が続くと、脳は「どれだけやっても無理だ」と予測して、その行動を諦めてしまう。その結果、治癒にエネルギーを回すようになり、何も行動する気が起こらない、やる気のない状態になるのだそうです。
会社でも、いつも営業成績が最下位になる。提案を上司からいつも否定される。よかれと思って行動したことが逆に怒られたりする。こんなことが続くと、脳は「どうせやってもムダ、言ってもムダ」と予測して、行動しなくなる。つまり、行動する気がない、やる気のない状態になっているということです。
ただ、こういうやる気がない状態であっても、車が突然目の前に飛び出してきたとしたら、人はとっさに逃げる。実は、人間は、やる気の有無に関係なく、行動するものなのだそうです。つまり、脳科学を研究している人によると、「やる気」というのは、人間が作り出した言葉で、実は実体はなく、結果をあれこれと思考して行動がとれなくなってしまうことが習慣になっているだけなのだとか。
だから、いかにこの習慣をなくしていくか。思考するだけにとどまらず、まず行動することで次の結果を得て、次の思考に移るという習慣を作っていくことが大事だと言われます。
確かに、あれこれ考えるより、行動すると違う結果が得られることがあります。過去に否定された提案も、状況が変わった今では役立つかもしれないし、上司が怒ったのはその時の気分かもしれません。やってみれば、結果は変わるかもしれない。新人が上司のことを素直に聞いて行動した結果、あっさりと成績を出すことがあります。ましてや現在は、過去のやり方が通用しないVUCAの時代。正解は誰も知らないはずで、やってみないとわからないことの方が多いのではないでしょうか。
まず、やってみて(行動)、そこで得られた情報で次を考える。実体のない「やる気」という言葉に左右されるのは本当にもったいない。小さくてもいいから、まず行動してみる習慣をつくる。それが「やる気」の一番の解決策なのかもしれません。
DO IT!
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 08 月 22 日 15:59
失敗を活かす
仕事をしていると、成功することもありますが、時には失敗することもあります。失敗してしまうと、本当に悔しく情けない気持ちになり、落ち込みます。立ち直るまでには時間がかかることもあります。失敗をして人は成長すると言われても、誰も好んで失敗はしたくはありません。
ただ、失敗は成功とつながっているのも事実です。仕事柄、いろんな経営者のお話を伺うことがありますが、優秀な経営者と言われる方も、過去には数多くの失敗をされておられます。経営の失敗が考え方を変える転機になり、経営方針を180度変えられた方もいます。お客様に喜ばれるものを作りたいと、何度も何度も失敗を重ねながら、世の中にない新しい商品を作りだされた経営者もいます。失敗が多い方が成功するというのは言い過ぎかもしれませんが、成功している方のお話には、失敗体験がたくさん出てきます。
失敗を次に活かせる人、活かせない人がいるそうです。ハーバード大学のフランチェスカ・ジーノ教授は、失敗のとらえ方とその後の成功の関連を調べるために、被験者に2つの難しい課題を与え、取り組ませる実験をしました。その結果、「最初の課題で失敗したのは自分の責任である」と受け止めた人は、次の課題で成功する確率が3倍だったとか。失敗の数は同じでも、その失敗を「自分の失敗だ」と自責で捉えられるかどうかが、次の成功に大きな影響を及ぼすということがわかったそうです。
失敗の数が多いというのは、それだけチャレンジをしているからとも言えます。成功経営者はチャレンジの数も多いから、失敗も多くなる。失敗が少ないというのは、一見良いように見えますが、逆に挑戦が少ないとも言える。ミスを怒られたり、追求されるような環境では、確かに失敗の数も少なくなりますが、逆に挑戦の数も少なくなる可能性もあります。「失敗したけども新しいことに挑戦したことは素晴らしい」という文化があれば、挑戦は多くなっていくのだろうと思います。
「こうすれば上手くいく」という過去の正解が通用しなくなっていくときに、新しい挑戦は不可欠です。ただ失敗も多くなる。失敗を活かし、学ぶ人や組織がますます大事になっていくように思います。
カテゴリー :
思うこと
2023 年 08 月 18 日 15:55
待つことの大切さ
「はじめてのおつかい」というテレビ番組がありますが、子供たちがはじめての体験を通して成長する姿にいつも感動してみています。はじめての体験で成長するのは、勇気をもって挑戦する子どもたちだけでなく、その場をつくるために手助けしたい気持ちを、ぐっと我慢する親も成長する体験かもしれません。失敗を繰り返す子どもを、親が待ってあげるから子どもが成長する。「待つ」という姿勢が、人の成長にとっていちばん大事なことじゃないかと、この番組を見ながらいつも思います。
しかし、会社になると、なかなかこの「待つ」ということができないことがあります。自分自身、いろんな失敗を重ねる中で技術など様々なことを身に付けてきたはずなのに、いざ人を教える立場になると、できない人に対して、つい「なぜ出来ないのか」と叱責したり、手助けしてしまったり、自分自身が待ってもらって成長したことを忘れてしまうことがあります。
諦めないこと、助け合うこと、最後までやり抜くこと。はじめての体験を通して、子どもたちは人として大切なことを身に付けていきます。体験を通して成長するということは会社も同じかもしれません。はじめて部下を育てる。はじめてリーダーになる。はじめて難しいプロジェクトを推進する。振り返れば、必要な技術や知識は、すべて体験を通して身に付けてきたことばかり。人の成長には体験が欠かせないのだと思います。
「会社は人間成長のための舞台である」という経営者がおられましたが、どれだけ良い体験を積ませてあげられるか。そのためにも「待つ」ということがいちばん大事なのかもしれません。
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方
2023 年 08 月 08 日 17:41
どんな時も理念が優先
日曜日、スターバックスさんのお店に入ると、広い店内はお客様でいっぱい。座れないお客様が待っておられました。席には、本を読む人、教科書を広げて勉強をする人、パソコンを出して仕事をする人。それぞれが自分の休日を楽しんでおられます。この店なら、ゆっくりと過ごせるという雰囲気があるからだと思いますが、経営する側は、長居されるお客様について、本当はどう思っておられるのか。
スターバックスさんの本を読ませていただくと、やはり、同社へのいちばんのクレームは「座れない」ということだそうです。しかし、だからといって、時間制限したり、お客様を急き立てるようなことは絶対にしないのが同社のポリシー。「人々の心を豊かで活力のあるものにするために」というミッションを業績より大事にして、経営をしてこられた会社です。アルバイトさんも、社員の人も、みんながこのミッションに共感して働いておられるので、その空気がお店全体からから伝わってきます。店舗もゆっくりできる空間ですが、スタッフの想いがお店の雰囲気をつくり、このお店でしか味わえない体験を求めるファンが生まれているのだと思います。
しかし、経営である以上、業績が悪くなると企業は存続できません。スターバックスも昔、大きな危機があり、大量のお店を閉店してしまったことがあるそうです。それでも、この理念優先の経営方針を絶対に変えることはなかったそうです。もう一度原点に戻り、1万人のリーダーが集まる会議で存在意義確認したそうです。そこから業績が再び上昇。危機を乗り越えたのも理念でした。
日本のスターバックスさんも、このミッションを大事にされています。「何のために私たちが存在するのか」。何度も何度も、事業の目的・ミッションを伝え、考えてもらう。スタッフの初期教育に70時間もかけられると伺っています。
会社が本来の目的を忘れてしまうと、利益が目的になってしまう。そうなれば、現場は利益をあげるための行動を優先する。その行動が長年のファンを裏切ることになり、お客様が離れる。だからこそ、どんな時も理念を優先する。スターバックスさんの強さは、理念への強いこだわりだと思います。
ひと昔前、日本でも「理念みたいな、きれいごとで飯が食えるか」と、経営理念より業績が大事という論調もありました。しかし、理念を忘れた経営が問題になっています。今は、「理念がないと飯が食えない」という時代がきているのかもしれません。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 素晴らしい会社
2023 年 08 月 01 日 09:58
おもてなしは、自由に。
お客様へのおもてなしは一律であるべきか。
先日、ある勉強会の中でこんな議論をしていました。
例えば、お客様への誕生日のお祝い。あるお客様にはしてあげた。しかし、他のお客様にはしない。これでは不公平になるのではないか。社内でこうした議論があって、結局、その会社では、やらないことにしたそうです。確かに、差がついてクレームが起こるかもしれないと思えば、怖くなります。
しかし、そうしたことを一切気にせずに、お客様満足に取り組んでいる会社もあります。
北九州の美容室バグジー。おもてなしで有名な美容室です。
バグジーのスタッフは、お客様が誕生日だと聞けば、誕生日のお祝いをしたり、雨が降ってきたら、お客様の自転車が濡れないようにサドルにビニールをかぶせてあげたり、気が付いたスタッフが、主体的にお客様のために動いていくお店です。
バグジーには、おもてなしのルールやマニュアルは一切ありません。誕生日のお祝いも、やっても良いし、やらなくても良い。おもてなしは、スタッフに任せられています。確かにバラつきがあると言えばあるのですが、こうしたやり方を長年続けているバグジーには、不公平だというようなクレームは一度も来たことはないそうです。
もちろんバグジーにも「購入者への特典や割引」など、店として実施するサービスはあり、一律にされることは他と同じようにされています。
しかし、「サービス」と「おもてなし」は別物。おもてなしは、気配りや心配りと言われるように、本来、一律では行うことはできません。足が悪い方がこられたら、席を用意して休んでいただく。雨に濡れた方が来られたら乾いたタオルをお持ちする。その人が、相手の状況を見て、気持ちが動いたら行動する。何かしてあげたいという気持ちが行動をつながっていくもの。双方の心の交流がおもてなしです。だから、おもてなしは、その場限りのもの。もし、されていない人がいたとしても、その人は決して損をしたという気持ちにはなりません。
バグジーの久保社長は、「一律に提供しなければと思って躊躇してしまうより、まず、やってみた方がいい」と言われます。もちろん、範囲や枠はある程度指示をしたとしても、「あとは、好きにやっていい」と、スタッフに自由にやってもらう。きっと、この方が「おもてなし」はうまくいくのでしょう。「決められたこと」をやれといわれるより、自由にやっていいという方が、スタッフにとってもやりがいがあるはず。
おもてなしは、形より、お客様を喜ばせたいという真心が一番大事なのではないでしょうか。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 素晴らしい会社
2023 年 07 月 26 日 10:22
経験から学ぶ
人は本から知識を得たり、話を聞いて学ぶことがありますが、人の学びの7割は経験からの学びだそうです。
そう考えると、確かに今の自分の行動も、過去にしてしまった失敗から学んだことや、成功の体験を活かしてやっていることがほとんど。可愛い子には旅をさせろといいますが、子供も大人も経験をしながら成長をしていくのが人間なのかもしれません。
しかし、どんなに経験をしても、ただ後悔をしたり、喜んだりしているだけでは、そこからの学びは少なく、次に活かしていくためには、経験を上手に活かす習慣が必要だと言われています。
そのひとつが、体験後の「振り返り」。一流のスポーツ選手も練習後に振り返り、良かったことや課題を記録する日誌をつけるそうですが、仕事でも、良い振り返りをしていくことが大事だと昔から言われています。振り返りをする目的は、体験を次に活かすためですが、つい、うまくいかなかった時は、あれがダメだった、ここが悪かったという追求の場、反省の場になりがちです。逆に、上手くいった時は、良かった良かったと拍手をして終わってしまうこともあります。日報や日誌も振り返って学びを次に活かすことが目的のはずなのに、行動や体験を記録するだけになることもあります。
良い振り返りとは、なぜ上手くいかなかったのか、次に気を付けるべきことは何かと考える時間をつくって、教訓を引き出していくことだと言われています。失敗した時も、そこから何を学んだか。成功した時も、そこから何を学んだか。常に経験したことから、教訓を引き出そうという習慣が大事なのかもしれません。
教訓は、同じ仕事をする時の成功確率を高めると同時に、他の仕事にも生かせます。
今は、誰も正解がわからないVUCAの時代と言われていますが、過去の知識が役に立たなくなっていく時に、経験を活かしながら進んでいくことが、ますます大事になっていく時代なのかもしれません。
カテゴリー :
これからの時代の人財育成
2023 年 07 月 19 日 10:29
誇れる仕事
先日、何百年も前に建てられたお寺などの建築物などを修繕したり、建て直しをする、宮大工の方のお話を読みました。古い建物は一度すべて解体し、傷んだ部分を直し、できるだけその古材を利用して建て直すのですが、解体してみると、外から見えない部分が見えてきて、当時、この建物を建てた大工さんの技術が見えてくるそうです。
外側から、見えないところにこそ丁寧な仕事が施されているそのきめ細やかな技術を見ると、「自分に恥じない仕事をしよう」という当時の大工さんの心が伝わってくる、解体に携わった宮大工さんは、その当時の職人さんの誇りや仕事への姿勢に、とても感動されていました。
裏側の部分だから、もし手を抜いても誰も見ていない。怒られることはない。しかし、それでよしとするかどうか、決めるのは自分です。しかし、いちばん見ているのは自分。
もし、手を抜いてしまったら、その人はその建物を通る度に胸が痛くなるかもしれません。その前に立てなくなるかもしれません。
出来上がったお寺の前に立って、誇れる自分でいたい。きっと、それがその職人たちの想いだったのではないでしょうか。仕事の判断基準は、自分の「良心」です。
翻って、今の自分の仕事はどうか。
本当はもう一度やり直した方がよいものができるのに、安易に妥協していないか。
早く納めることばかりに意識がいって、品質を下げていないか。
仕事の質は、追求すればするほど、さらに上が見えてきて、なかなか100点が見えてきません。
納期、予算、スピード、全体の生産性・・・。いい仕事の前にはいろんな壁があり、どこかで妥協しなければならない。しかし、数百年前の大工さんの時代でも、もしかするといろんな制約があったのではないか。しかし、彼らは、その厳しい制約の中でも、自分に恥じない仕事をしようと闘っておられたに違いありません。
どこまでいい仕事をやり抜くか。自分の良心に誇れる仕事をしていきたいです。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 07 月 11 日 13:24
自ら立てた目標、与えられた目標
先日、あるお店でサービスを受けているときに、スタッフの方から今月のおススメだと、新商品の案内がありました。良く来ているお店ですし、若い子が熱心に勧めてくれるので、断るのも悪いと思い申し込みましたが、少し強引な感じがして、少しモヤモヤとした気持ちになりました。新しい商品なので、きっとお店に課せられた目標があるのだろうと思います。一生懸命に進めてくれるのは良いことで、そのスタッフも頑張っているのはわかりますが、何かその会社の都合を押し付けられている気がして残念な気持ちになりました。
数値目標を持つことは、やるべきことが明確になり、達成の度合いがわかるので、対策も打ちやすくなります。達成すればやる気も高まるので、目標管理はいろいろな会社で使われています。ただ、やるべきことが明確になるが故に、その他のことに気が回らなくなったり、手段が目的化してしまうというデメリットもあります。このお店で感じたのは、いつもはお客様のことに気を配ってくれるいい店だと思っていたのに、お勧めに熱心なあまり、その良さが感じられなかったのかもしれません。
ただ、目標を持つことは悪いということではないはず。問題は、その目標の奥にある気持ち。会社から与えられた目標をこなそうと一生懸命にお勧めしているのか。会社の理念にも通じる商品だと感じ、自分自身も良いと感じたものを、できるだけたくさんの人に薦めたいと思いながら自ら目標を立て、一生懸命にお勧めしているのか。見た目の状況はそんなに変わらないのかもしれませんが、醸し出す雰囲気は微妙に違う。それがお客様に伝わっているのかもしれません。
趣味の世界では、「今日は魚を何匹釣ろう」という目標を自分で決めます。自分で決めるから楽しくなり、工夫もする。それがもし、誰かに「何匹釣ってこい」と言われたら、とたんに面白くなくなってしまうはず。さらに、その目標をなんとしてでも達成しろと、隣で数字を追い立てられたら、数字ばかりに目が行き、「帳尻を合わせるために、スーパーで買ってこよう」というような手抜きもしたくなりそうです。趣味と仕事は違うのかもしれませんが、「面白い」と思えば、どんなことでも工夫し挑戦していこうと考えていくのではないでしょうか。
しかし、はじめてのことは、何でも実際にやってみないとわからないことがあります。もし、納得がなく、ただ会社からやれと言われて、最初はやらされ感で始めることがあったとしても、そこに一生懸命に取り組んでみる。自分が一生懸命にお勧めした商品を、お客様が喜んでくださった。そんな体験を通して、改めて商品の価値に気づくこともあります。目標を与えることは悪いことではないのだろうと思います。
何れにしても、目的を忘れて、目標だけになってしまうのが、面白さを失う原因なのかもしれません。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 07 月 04 日 11:23
価値をお届けする
先日、社内で私たちが提供している「価値」について話し合う機会がありました。
購入したものが、自分の目的実現に役立ったと感じた時、「買って良かった」、「価値があった」と感じます。「価値」を感じると、多少価格が高くても「いい買い物だった」と思えますが、価値を感じることができなかったから「損をした」と感じる。お客が「この商品には価値ある」と感じていただければ、リピーターになってくださり、それが「他にない価値」であれば、ずっと、お客様でいてくださるはずです。
当たり前ですが、お客様が「価値があった」と思っていただけるように商品を作り、販売していくのが商売だと思いますが、価値を感じるのはお客様の心。見えないだけに理解するのは本当に難しい。
例えば、こちらが「価値がある」と思っても、そもそもその価値がお客様に伝わらないと売れませんし、どれだけ価値を伝えても、「価値があった」と本当に実感されるのは、お客様が商品を使われた後。良い商品だとしても、購入後にお客様が上手く使えなかったり、十分に機能を使いこなしていただけなければ、「価値があった」という結果にはなりません。もそも、販売時点で、お客様の目的に沿うものをご提供していなければ、どんなに良い商品でも価値を感じてくださることはありません。
顧客満足の向上が難しいのは、お客様の気持ちを理解するのが難しいからだと思います。そう考えると、見えない気持ちを理解するためには、こちら側が、どれだけお客様に寄り添っていけるかが大事なのかもしれません。購入前なら、どれだけお客様の目的、何を達成したいのかをわかってあげられるか。その目的に沿ったものをどれだけご提案してあげられるか。販売した後も、お客様の目的が実現されるように、どれだけサポートしてあげられるか。「価値があった」と思っていただくことは、確かに手間がかかります。
料理などは、食べて「美味しかった」とすぐに価値を感じてもらいやすいですが、企業向けの機械やサービスなどは、顧客の社内で使いこなしていただいて初めて価値が生まれていくもの。販売後のアフターサービスを大事にしている企業が成長しているということも、こういうことの流れなのかもしれません。
お客様が実現したい目的にそって、どれだけ寄り添っていけるか。価値を生み出していくことは難しいことですが、お客様から「価値があった」「値打ちがある」という言葉をいただくことは、本当に嬉しいこと。だからこそ、やりがいがあります。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 06 月 27 日 09:57
ミッションと働きがい
先日、ある会社の方たちと、若いスタッフの「働きがい」をどう高めていけるかというお話をしていた時に、やはり、ただ機械的に仕事をするのではなく、仕事の意義や意味を感じさせてあげることが大切なのではないかと議論になりました。この仕事にどんな意義があるのか?何のためにやっているのか。それを感じられないと今の若い人は会社を辞めていくのではないか、そんな話し合いをしていました。
アルバイトスタッフの離職について悩んでおられた教育担当の方は、「確かに、自分は、ただ、仕事のやり方を教えるだけで、仕事の意義などは伝えたことがなかったかもしれない。」と話されていましたが、昔なら、それで良かったのかもしれません。しかし、物が豊になり、お金を稼ぐこと以上に「やりがい」を求める人が増えてきた時に、何の説明もなく「やってください」では納得できないのかもしれません。
ただ、「これをやってください」とやることだけを伝えて仕事を与えるのか。この会社は何のためにあるのか、この仕事は社会にどのような役割を果たすのか、つまり会社の使命(ミッション)をしっかり伝えてから仕事を与えるのか。納得して働きたいという若い人にとっては後者の方が大事なのかもしれません。
会社のミッションとは会社の存在意義。つまり「私たちは、なぜ社会において必要なのか?」「どんな役割を果たしていく意思があるか?」という問いに対する答え。昔は、ただ売上をあげて納税していくだけで十分、会社は存在意義があるということだったのかもしれませんが、より「働きがい」が求められる時代になって、ますます大事になってきている気がします。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 06 月 20 日 14:39
働きがいと若手の成長
今、若い人の育成に課題を抱えている企業が多いそうです。主体性がない、指示待ちになってしまう人が多い。3年も経たずに離職してしまう。教育に悩んでいる会社は多いと思います。
どれだけ良い待遇であっても、この場所では自分は成長できない、働く意味がないと感じたら、大企業でも辞めていく人もいると聞きます。若い人たちがどうすれば成長してもらえるのか。なかなか答えが出ない問題です。
そんなことを考えているとき、いつも通っている美容室に行きました。昨年から私のシャンプーを担当してくれる今年2年目のスタッフの方と話をしていたのですが、この仕事が楽しいと感じているようで、日々の仕事が充実している感じが伝わってきました。
この会社ではスタッフが美容師としてデビューするまで綿密な教育カリキュラムがあり、シャンプーやカットなど、何十種類もある技術を自分で身に付け、社内テストに合格しなければお客様にすることはできないという決まりがあるそうです。アシスタントは、お客様の髪を切ることはまだできませんが、技術を身に付ければつけるほどできることが増え、お店はより回るようになります。
ただ、1年目は仕事を覚えることに必死で、心に余裕がなかったそうです。しかし、だんだん先輩の手伝いができるようになってくると、ありがとうと言われることも増え、「少しだけだけど店に貢献できている」という手ごたえも感じるようになってきたとか。去年合格した「シャンプー」も、一生懸命やっているとお客様から「気持ちよかったよ」と褒められる場面も出てきて、またやる気が出る。この4月に初めて後輩ができ、人を教える立場になり、それが自分の成長を見つめるいい機会になっているようです。
「働きがい」という少し大げさかもしれませんが、彼女は少しずつ働くことの楽しさや喜びを感じるようになってきたのかもしれません。今は、次の技術の習得と後輩の成長支援をしていきたいと話してくれました。
自分が成長する嬉しさ。人に役立てる嬉しさ。誰もそうだと思いますが、一度この喜びを体験すると、仕事の意味が変わってきます。仕事はただお金を稼ぐことだと思っていた人が、働くことにそれ以上の意義を感じる瞬間。「働きがい」を感じれば感じるほど、もっと成長したい、もっと頑張ろうと思えるのではないでしょうか。1年目、2年目の最初の頃に、どれだけこの「働く喜び」を感じさせてあげられるか。若手の育成はここにかかっているような気がします。
カテゴリー :
これからの時代の人財育成
2023 年 06 月 14 日 17:30
創業者からの伝言
誰もが知っているウォシュレットなど革新的な商品で有名なTOTOグループ。そのTOTOグループには「どうしても親切が第一」という価値観が先代から受け継がれているそうです。初代社長である大倉和親氏が、二代目社長に送った書簡に記されたものの中にこんな文章が書かれていたそうです。
「どうしても親切が第一、良品の供給、需要家の満足が掴むべき実体で、その実体を握り得れば、結果として報酬という影が映る」
利益はあくまでも影であり、追い求めるものは影ではなく、良い商品をつくること、お客様の満足であるから、我々はどんな時でも、どうしても「親切」「誠実」が第一で、「お客様思い」であるべきだ。その前提で事業を行えば、必ず利益である影はついてくる。TOTOらしさを忘れるな、と代々伝えてられているそうです。
考えてみれば、大企業であれ、中小企業であれ、今、地域や顧客から指示され伸び続けている会社はどこも同じかもしれません。判断軸はいつも、どうすればお客様に喜んでもらえるか、どうすれば役に立てるか。あくまでも「実体」を追い続ける。「きれいごと」だけでは経営はできない。そんな声もある中でも信念をぶらさず、ずっと「きれいごと」を追求されてきた会社が今、顧客から支持されているのかもしれません。
しかし、企業は利益が出なくなれば倒産してしまいます。いつも、この「きれいごと」と「影」の天秤に悩み、迷うことがあるものまた事実。創業者がこうやって大事なことを次の世代に渡そうとするのは、きっと、それがわかっているから。迷いが出た時こそ思い出せという教えなのかもしれません。
理念は判断に迷った時の羅針盤と言いますが、ぶれない軸のためには本当に大切なものだと思います。
カテゴリー :
経営理念の浸透・共感
2023 年 06 月 07 日 15:03
強い思い
プロジェクトでも会社の経営でも、何かを始める時にはまず「なぜやるのか」「どうなりたいのか」という目的や行き先をしっかり決めることが大事だと言われています。「どうやるか」(方法)を考えても、「そこに行きたい」と思う行き先や目的が明確でなければ、プロジェクトも経営も右往左往する。勉強にしろ、仕事にしろ、最初に「ありたい姿」を描くことが何をする上でも大事だと思います。
しかし、どれだけ目的や行き先を明確にしても、そう簡単にいかないのが世の常。たどり着くまでには困難や試練がある。諦めたくなる、投げ出したくなる要因がいくらでも起こってきます。昔から成功する唯一の方法は、成功するまで諦めないことだと言われているように、もしかすると、成功するためには、目的や行き先に対して、どれだけ強い思いを持っているか、その強さの違いが大きいのではないでしょうか。
先日、侍ジャパンの監督を務められた栗山秀樹さんの言葉を教えていただきました。
「『こうなったらいいな』ではなく、『絶対になる。こうなる』と考える。『こうなる』という前提があってはじめて、いったいどうすればそうなるんだろうと考えられるようになる。『こうなったらいいな』と思って考えるのと、『こうなる』と信じて考えるのではまったくプロセスが変わってくる。『そこにたどり着くために、今日自分は何をすればいいのか』といった具合に発想も変わってきて、そこに知恵が生まれるのだ。」
「ビジョン」にどれだけ強い思いを持つか、「絶対に、こうなる」と信じて考えることで、単なる夢が具体的な夢になっていくかもしれません。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 05 月 30 日 15:13
お店を変えた「対話」
先日、ある会社のミーティングに参加させていただきました。この会社は、以前は本社が店舗に指示を出し動かしていくトップダウン型の会社だったそうですが、それでは持続していかない、各お店が経営者のように考え運営する組織にならねばと、十年前くらいから、それぞれの店舗が店長主体に運営する組織づくりを進めてこられました。その核となったのが「店舗ミーティング」です。
いろんな会社でミーティングは行われていますが、メンバーが発言しなかったり、誰かが一方的に話すだけの場になってしまうことがよくあります。この日、ミーティングが定着し成果が上がっているお店を見学させていただきました。
その日のテーマは、「どうすればよりチームワークが良くなっていくか」。会議の前に店舗スタッフ全員がテーマに対する自分の考えを紙に書いてくるところからスタートします。自分の考えを述べるだけでなく、「なぜ、そう思うのか」というその人の想いを語り合います。店長は傍で見ているだけ。答えを示すことも、誘導することもなく、スタッフだけで対話が行われています。このミーティングでは、結論を出すことにとらわれていません。同じテーマを何回も話し合っていくそうです。
結論を出さない話し合いをしていても無駄ではないかと思ってしまいますが、店長に聞くと、このようなミーティングを続けてきたことでいい変化が生まれてきたそうです。対話を続けてきたらチームの中の人間関係が良くなり、部門を超えた協力や助け合いが生まれるようになってきたそうです。メンバー同士、お互いに関心が向いていったのでしょうか。自分の想いも伝わるようになってきたと話されていました。
「対話」と「議論」。議論は、どうあればいいか、お互いが意見をぶつけ合ってひとつの答えを見つけていくこと。それに対して「対話」は、自由な雰囲気の中で、ひとつのテーマに対するお互いの想いを共有して理解し合うこと。「その人は、そう思っているのか」と、人の奥にある気持ちや価値観を理解し合うことから、本当の納得感が生まれたり、相互の協力が生まれてきたりするのが対話です。
このお店が大事にされてきたのは「対話」。店長が関与していけば、きっともっと早くに結論が出るはず。「こうやっていこう」「こうしてほしい」と指示を伝える方が、伝わるのは早いかもしれません。ただ、それではメンバーは頭で理解したとしても納得感がない。頭でわかっているだけでは、結局、やらなくなってしまうと店長は話されていました。
「対話」は、お互いの価値観を理解し合うこと。私はこう考えるということを話し合う。なぜ、そう思うのかという思いも話し合う。そのプロセスは時間がかかるかもしれませんが、人が働いていく上でいちばん大事な信頼というベースをつくるのでしょう。
私たちはつい、スピードや効率を求めて、メールや何かで端的に手短に伝えたり、早く結論を出そうしてしまいますが、それが逆に納得感を置き去りにしていたり、長い目で見た時の効率や生産性を阻害してしまっているのかもしれません。時間をかけることがいかに大事か。このお店から学んだ気がします。
ちなみに、このお店は今年、お客様満足度や様々な指標でその会社でナンバーワンの成績になったそうです。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2023 年 05 月 23 日 11:44
苦情を伝えるお客様
以前、ある顧客満足を学び合う勉強会で改めて「グッドマンの法則」について話し合ったことがあります。「グッドマンの法則」は、CS(顧客満足)の勉強をしていると必ず出てくる有名なクレームに対する法則です。グッドマン氏がまとめた2つの法則の中の第一の法則は「不満を持った顧客のうち、苦情を申し立て、その解決に満足した顧客の当該商品・サービスの再購入決定率は、不満を持ちながら苦情を申し立てない顧客より高い」というもの。第二の法則は「苦情処理に不満を抱いた顧客の非好意的なクチコミの影響は、満足した顧客の好意的なクチコミに比較して2倍も強く影響を与える」というものです。
その時の勉強会では、参加者同士で自分自身が体験した不満と苦情を申し出た体験を話し合ったのですが、消費者のリアルなクレーム体験が語られました。ある方は、ずっと利用していたカーディーラーで車の整備をされたのですが、修理に問題があり、それをお店に伝えに行ったのですが、責任逃れをするような対応をされたうえに、再修理も思うようにしてくれなかったそうです。こういうことはあるかもしれないとそこまでは、普通に聞いていたのですが、その後のお話を聞いて「苦情対応」の怖さを実感しました。
その方は自分が信頼していたお店にぞんざいにされたことが、本当に辛い体験だったのでしょう。その後、何年間も、知人や家族の中で車の話題がでる度に、「〇〇は買わない方がいいよ」とそのメーカーの悪口を言っていたそうです。一人のお客様とはいえ、この「非好意的な口コミ」で何台かが「売れるチャンス」を逃し、継続的に利用されるようになったかもしれない未来のお客様を失っていると思うと、ぞっとします。
確かに、失敗は誰でもするものなので、私は単にミスがあっただけでは怒ることはありませんが、そのことに対してごまかしたり、誠意がなかった時は、きっと同じような気持ちになるはず。もし誰かから相談があれば、「買わない方がいい」と言ってしまうかもしれません。
グッドマンの第一の法則は、「不満を持った顧客のうち、苦情を申し立て、その解決に満足した顧客の当該商品・サービスの再購入決定率は、不満を持ちながら苦情を申し立てない顧客より高い」ですが、もし、この時、このお店がお客様の気持ちにしっかりと向き合い、解決するまで真剣に対応していれば、不満が満足に変わり、その後もずっとお付き合いをしてくださったかもしれません。
人間が商売をしている以上、ミスや行き違いは起こってしまうものだと思いますが、その時にどのような対応をするか。その対応ひとつで、その後の販売がマイナスにもプラスにもなっていくとすれば、いかにお客様の苦情から逃げず、誠意をもって対応していくことが大切かわかります。
誠意ある対応をしてくれると、逆にその店の良さがわかり好きになることがあります。モンスター顧客がいる時代なので、なかなか難しいかもしれませんが、自分たちのミスを素直に謝り、顧客の心に真摯に向き合ってくれるお店はきっと信頼され続けていくような気がします。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上
2023 年 05 月 16 日 15:34
一生懸命の力
仕事が好きだ、楽しい。いつもこの気持ちで働けていれば、自分の心も明るくなるし、仕事の成果も生まれていくはずです。だからこそ、昔から自分の仕事を好きになれということを言われてきました。
では、どうすれば、好きになるのか?私自身が多くの先輩から教わったことは、今の仕事を一生懸命にやることだということでした。一生懸命とは、どうすればより良くなるかと、自分で考え、試し、うまくいくまでやり遂げていくことだ。そうやって仕事をしていると、仕事が好きになる、楽しくなると言われて新人時代を過ごしました。
好きだから一生懸命になれるのではなく、一生懸命にやったからこそ、仕事が好きになる。こんなプロセスを何度も経験した気がします。何事にも一生懸命にやるというスタンスを新人時代に身に付けた人は、きっと、どんな仕事についてもその仕事が好きになり、成功できるのではないでしょうか。
先日、ある自動車販売店の女性スタッフにお話を伺いましながら、そんなことを思い出しました。お客様のおもてなしなどをするショールームアシスタントに配属されたのですが、このお店を良くするために、ここにいる自分がもっと役に立てることは何かと考えました。自分には営業も修理もできない。でもお客様とお話することはできる。そこで、すべての来場者に声をかけお話をすることに挑戦したそうです。続けていくとお客様が笑顔になってくださる。また会話の中で、ふとお客様が「車を検討している」とか「困っている」という声を聴くようにもなりました。彼女はそれを営業に伝えたり、自分で記録して次のご来店時に対応すると、さらにお客様が喜んでくださる。彼女はどんどんと仕事が好きになっていったそうです。彼女の一生懸命さが仲間に伝わり、お客様の声を聴くことがいつしか風土になり、数年後には社内でCS No.1のお店になっていったそうです。
一生懸命にやる。ただ、闇雲に一生懸命にやるといっても、ただ、言われたことを言われた通りにやっていては面白くはなりません。なぜするのか、何のためにするのかという仕事の目的をしっかり理解して、そこに向かって創意工夫する。目的意識こそが一生懸命の原点かもしれません。
誰かの一生懸命が楽しさを生み、成果を生み、まわりの人を巻き込み、より良くしていく。一生懸命には大きな力があるような気がします。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2023 年 05 月 09 日 10:12
仕事への誇り
全国のレクサス店の中でも、トップクラスの販売台数を誇る、レクサス星が丘。すべての部門のスタッフが協力しながら、お客様満足を高め続けているお店です。
映像で取材する前に、そのお店の警備員として働く、早川正延さんという方にお話を伺いました。早川さんのお仕事は警備。お店に入るお客様の車を誘導したり、出て行かれる車が安全に出庫できるよう誘導をされています。待ち時間はお店の前に立ち、お客様のご来店を待っておられます。
早川さんは、ある時、「ただ、ここで待っていてもつまらない。もっと何かできないか。」そんなことをぼんやり考えるようになったそうです。そんなある日のこと、目の前の通りを通り過ぎていくレクサス車にお辞儀をしました。
それから、早川さんは、通り過ぎていくすべてのレクサス車にお辞儀をすることに。このお店で買われたお客様だけでなく、他店で買われたお客様のレクサス車にも、1日1000台近い車に、深々とお辞儀をする。それを何年も続けておられます。
走っている車への挨拶ですから、気が付かれる方もいれば、気付かれない方もいる。それでも早川さんはそのお辞儀をするそうです。そんな早川さんの姿勢に感動されるお客様が増え、早川さんに会いたいと来店される方もおられるそうです。
なぜ、こんなお辞儀をするようになったのかと伺うと、「大したことはしていません」と謙遜しながらも、自分がここで働かさせてもらっていることへの感謝の想いやお客様への感謝の気持ちが自然とお辞儀になったと話してくれました。
早川さんは、店頭でのお辞儀の他にも、駐車場での車の誘導の場面でも、どうすればもっと「お客様が安心して駐車していただける誘導ができるか」と考えながら、誘導時の立ち位置、オーライという言葉の大きさ、わかりやすいしぐさについても研究を続けておられました。お客様のバックミラーに自分がどう映っていれば、安心されるのか。そんな細かなことまで研究されています。「素晴らしいですね」と言うと「まだまだ完璧な誘導はできません」と笑顔で話されていました。
「お客様のためにもっと何かできないか」。お辞儀をする、誘導をするという行動は誰でもできることかもしれません。ただ、早川さんのお辞儀や誘導は、確実にお客様に伝わり、感動を生み出しています。それはきっと早川さんが自分の仕事に誇りをもち、もっとよくしようと思っているからこそ、その姿勢や心が伝わっているのだと思います。
仕事だからと嫌々やる仕事、より良くしようと誇りを持って行う仕事。どちらも同じ仕事ではあるかもしれません。どうせやるなら、後者のような仕事をしていきたいですね。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 素晴らしい会社
2023 年 05 月 01 日 17:02
売らない営業
昔の営業のイメージは「買わないお客様に、いかに買わせるか」というようなものがありましたが、今やそんなスタンスではお客様から嫌われるだけ。営業も大きく変わってきているように思います。
先日、ある地方の小さな街にある自動車整備店を取材させていただいたのですが、そのお客様本位の営業が心に残りました。このお店は、少子高齢化が進む街の中で、整備だけでは商売が難しい、新車の販売もやっていこうと若い経営者が頑張っている個人商店です。ただ、近隣には大手ディーラーが立ち並び、新車販売といってもそう簡単ではありません。同じことをやっていてはダメだと思ったその経営者は、自分の体験やお客様の声をヒントに「無理に売らない店」になろうしました。ディーラーの営業の「売り込もう」とするプレッシャーがどうしても苦手だと思う人がいる。ディーラーを避けているお客様もいる。だったら無理な営業は絶対にしない。お話を聞き、商品をご提案するだけの営業。「決めてください」「買ってください」と迫るような営業を否定し「売らない営業」を続けてこられました。やってみると、同じ思いを持っているお客様が意外と多くいる。そのお店で買いたいというお客様がどんどん増えていったそうです。
また、別の取材で、全国上位に入る保険セールスの方にお話を伺いました。この方の営業も「売らない営業」。お客様のお話を親身になって伺い、その人にあった情報をお伝えするだけ。「間に合っています」と断られても「それは良かったです」とニコニコとする。「安心をお届けすること」が私の仕事。だから、お客様が既に安心されていると仰るなら私も嬉しい。「断られた」という意識もないそうです。どこまで行ってもお客様本位。もし、お客様が「それを買う」と仰っても、プロとして必要がないと思えば「それは今契約されない方がいいですよ」とお話したり、「他社の保険の方が良い」と思えばそれを進める。お客様の応援団に徹する営業。お客様は彼女のそんな姿勢にすぐにファンになってしまうそうです。「この人は自分の味方」「この人なら信頼できる」と感じたお客様は、家族の保険はもちろん、県外に住む家族の保険まで任せるようになるそうです。自分自身が無理なことをしていると思っていないので、この仕事が大好きで一生やっていきたいと言われていました。
迷っているときに、営業マンの熱心なお勧めが「積極的に背中を押してくれた」と好意的に感じたり、仕事への熱心さと受け止めるお客様もいますので、売ること、お勧めすることは良い時もあるのかもしれません。ただ、自分の成績の為にという気持ちの熱心さと、お客様のためにという熱心さがあるとすれば、後者の気持ちの営業マンの方が、ずっと付き合っていきたいと私は感じます。「売れる営業マン」は変わってきましたね。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上
2023 年 04 月 25 日 10:33
仕事の目的
何のために仕事をするのか。目的意識をもって仕事をすることが大事だと、私も若いころから言われていました。目的を意識してやる仕事と、していない仕事では質が違う。仕事をこなすな。目的を意識して、目的にこだわって、創意工夫しながらやるのが仕事だ。若い時に何度も言われて育ってきました。
このようなことを言われるのは、私たちはつい、目的を忘れがちになってしまうからなのかもしれません。
目的は「未来」のこと。こうありたい、こうしたいと考えることです。それが「今」の仕事の処理にばかりに目がいくと、現在のことであたまがいっぱいになる。期日に間に合わせる、言われたことを処理する。処理することで頭がいっぱいになっている時は、未来はありません。
例えば、経営理念に、私たちの目的は顧客に満足していただくこと、お客様に喜んでいただくこと、と書かれている。しかし、今の業務を処理することで頭がいっぱいになると、それをこなすことでいっぱいになって、この大事な本来の目的をつい忘れがちになります。お客様のことを考えなくなる。相手のためにプラスαの行動をしようとも思わない。よく理念が形骸化するということが言われていますが、このように、つい現在ばかり思考が向いてしまい、未来への想いを忘れてしまうことかもれません。
ただ、働く人にとっては「今の仕事」が大事なのは言うまでもありません。だからこそ、余計に普段から強く目的を意識しないといけないのかもしれません。朝礼などで理念を唱和したり、クレドを確認するのは、そんな意味があると思います。
この仕事は何のためにやるのか。
目的を意識し、重視し、その目的にこだわり続けることを「目的思考」と言うそうですが、言われたことを言われた通りにやっていればいい時代が終わり、自分で考えていくことが求めてられていく時代には、こんな思考がますます大事になっていくように思います。
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方
2023 年 04 月 11 日 13:47
自分がされたら嬉しいことをする
ある商品を購入した際に、商品の入った箱を止めるためのガムテープの端が折り曲げてあり、はがしやすくなっていました。
端が折っていないテープをはがすのに、爪を立ててイライラする時がありますが、こうやってテープの端を折って貼ってくれているだけでそのストレスがなくなります。その1センチの端にお店の方の気遣いを感じ、気持ちがほっこりしました。こうした貼り方の呼び方は何というのかわかりませんが、トイレットペーパーの端を三角に折る行為のように、相手のことを思う小さなことを実践されている人の仕事への姿勢が伝わってきます。
マクドナルドの新人アルバイト教育では、相手の立場になって考え行動することの大切さを教えていくそうですが、最初はまず「お客様や仲間には、自分がされたら嬉しいことをする」という基本ルールから教えていくのだそうです。相手の立場に立つのは口でいうのは簡単ですが、相手軸で考えることはなかなか難しい。でも、自分がされて嬉しかったことなら、自分軸だから実践しやすい。だから、まずは自分がされたら嬉しいことをしていこうと教えられるのだそうです。先ほどの荷物も、もしかすると配送係の人が、テープの端が折ってある荷物を受け取り、その行為が嬉しかったから、相手にもそうしてあげようと思ったのかもしれません。
お客様に対してだけでなく、社内でも同じで、書類をつくる時は、相手が見やすいように、使いやすいようにひと手間かける。次の工程の人がやりやすいように仕事を渡す。自分がされて嬉しいことをしていくことが、全体の仕事の質が高めていくのかもしれません。
「自分がされたら嬉しいことをする」。シンプルですが、質の良い仕事をしていく上でいちばん大事な基本ルールのような気がします。自分自身も初心にかえってやっていこうと思います。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上 素晴らしい会社
2023 年 04 月 04 日 10:49
新人の心が育つ風土
先日、ある会社で洗面所を利用させていただいたのですが、そこにおられた若い社員の方が洗面所の回りに飛び散った水を丁寧に拭かれていました。関心して上司の方にお伺いすると、この会社では誰もが次の人が気持ちよく利用できるようにと、洗面所を使ったら清掃をされる習慣があるそうです。
またある会社では、玄関で人を待っていると、玄関を通る社員の方が次々が挨拶をされ、「ご用件お伺いしておりますか?」と声をかけてくださいます。自分のお客様でなくても、誰もが会社のお客様と思い、関心を持つ、気にかける。素晴らしい文化が定着している会社だなと思いました。
誰が見ていようといまいと使った後は綺麗にするという習慣、お客様に声をかけるという習慣。誰もが自然とこんなふるまいが実践されるのは、それがその会社では当たり前の習慣なのです。
この春、新入社員が入社し様々な研修が行われますが、どんなに新人が挨拶の練習をしたとしても、基本のマナーを身に付けたとしても、職場の先輩が挨拶をしなければ、挨拶をしなくなるはず。洗面所を汚したままで立ち去る人が多ければ、それがあたりまえになるはず。
私たちは、新人が挨拶をしない、元気がない、マナーを守らない等と、つい新人のせいにしてしまいますが、本当に人を育てるのは研修の場でなく、職場での先輩の姿であり、風土。そうなってしまっているとすれば、周りがそうなっているのかもしれません。
真っ白なキャンパスの人財が、どのような人に育つか。試されているのは、先輩であり、会社の風土なのではないでしょうか。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2023 年 03 月 28 日 14:35
今、ここ、自分
全国20代~60代の働く人に対して行われたアンケートでは、「あなたは仕事が楽しいですか」という質問に対して6割以上が「楽しい」と答えているそうです。楽しいと感じているときは、ハードワークも苦になりませんし、自分から学びにいこうともする。
先日開催されたWBCの中でも、大きなプレッシャーがかかる場面でも、中心にいる大谷翔平選手が常に野球を楽しんでいる姿が話題になりましたが、本気で楽しむ姿勢は良い結果を生み出す確率が高くなるだけでなく、その姿勢が周りにも良い影響を与えていくものだと思います。
ただ、大きなプレッシャーがかかる場面でなかなか楽しむという気持ちになるのは難しい。結果を出さなければと思えば思うほど気持ちが焦り、身体も心も縮こまります。
数々の金メダリストのメンタルコーチをしているスポーツドクターの辻秀一さんは、この楽しむ心の大切さをアスリートに伝えている方ですが、どんな時も楽しむためのキーワードとして「今、ここ、自分」ということを教えておられます。これは禅の言葉ですが、取返せない過去を悔やんだり、まだ来ていない未来を憂いたり、人と比べて落ち込んだりすると、どんどん心が不機嫌になる。だからこそ「今、ここ、自分」を意識して取り組んでいく。大谷選手は、優勝という結果も大事にしていたと思いますが、世界一のレベルの選手が競い合う大会に出場できること自体に感謝し、楽しんでいる。まさに、「今、ここ、自分」の境地だったのではないでしょうか。
もし、うまくいかなかったらどうしよう。あの人がうまくっているのに自分はダメだ、など不安になる時、怖くなる時は、心が「今、ここ、自分」から離れてしまう時かもしれません。「今、ここ、自分」を大切にすることが楽しむことの一歩目なのだと思います。ただ、そうはいってもなかなか自分の心を変えることは難しい。そんな時にアスリートが大事にしているのが自分が発する言葉や態度。大谷選手もそうですが、選手の多くが「楽しむ」「感謝している」「ありがとう」「おかげで」などという言葉を口にしています。「必ず勝ちます」というような言葉ではなく、今、ここ、自分に意識が向くような言葉を口にすることで心を整えていく。楽しむことの価値を知っているアスリートは、人や環境のせいにせず、自分で自分の心を作っているようです。
仕事を楽しむ。夢中になる。まずは、この価値を知ることがいちばん大事なのかもしれません。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 03 月 22 日 14:33
Fail fast(早く失敗せよ)
目標を掲げて取り組んでいたのに達成しなかったり、仕事を抱え込みすぎてパンクしてしまったり、仕事をしていると上手くいかないことが時々発生してしまいます。失敗すると精神的にも辛いし、落ち込みます。だから、次は失敗したくないと思い、なぜ上手くいかなかったのか、どうすれば上手くいくようにできるかを考えて、次に挑戦をする。取り組みを変え、自分の向き合い方を変え、やり続けていく中でようやく成功する。
スポーツにしても、ビジネスにしても、この繰り返しの中で、人は成長していくのだろうと思います。
そう考えてみると、失敗ということは、人が成長していくためには最も大事なこと。よく言われるように、失敗こそが、成長の原動力なのだと思います。だからよく「失敗を恐れずに挑戦しろ」と言われるのだと思いますが、失敗すると怒られたり、厳しく叱責されるという環境の中だと、失敗を避けるようになってしまいます。
目標を低く設定したり、新しい挑戦を避ける。不安な道に進むより、正解がある道、安全な道を選ぼうとする。その道は、確かに失敗は少ないけど、考える機会も少ない。成長のためには、失敗のある道の方が良いように思います。
ただ、いくら失敗が大事だと言っても、それを自分の「糧」にしなければ成長はない。「失敗を気にしない」と反省をしないで次に挑んでも同じ失敗をしてしまいます。失敗が大事というよりは、「失敗から何を学んだか」、教訓を得ることが大事であって、失敗後の「振り返り」がなければ、成長にはつながらない。一番大事なのは、ここだと思います。
アメリカのシリコンバレーでは、「Fail fast」(早く失敗せよ)という言葉が良くスローガンとして使われているそうです。どのような天才でも100%成功する時代ではない。だからこそ、アイディアを実際に試して失敗し、そこから得た教訓をもとにまた新しい仮説を試す。その繰り返しを早く実行することが成功につながる。
それがFail fastという標語の意味。変化が激しく、誰も正解がわからない時代だからこそ、失敗から学んでいくことが大事だと、この業界では失敗を推奨しているそうですが、どの業界でも大事なことではないでしょうか。
失敗の連続は確かに苦しいことかもれませんが、そこで七転八倒してきた数年を振り返った時に、人生の充実感や自分の成長を感じることがあります。そうやって考えてみると、人生にとっても失敗は大事な経験であるように思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 03 月 14 日 14:19
知・好・楽
仕事の成果を上げる。生産性を上げる。いろいろな技術や方法があると思いますが、いちばんの方法は、仕事をする人がそれ楽しいと感じてやっていることではないでしょうか。今話題のワールド・ベースボール・クラッシックで活躍している大谷選手などのプレーを見ていても、勝とうという気持ち以上に、楽しんでやっているという雰囲気を感じます。この晴れ舞台を最高に楽しもうという気持ちこそが、最高の成果につながっているような気がします。
論語の中に、「これを知る者は、これを好む者に如かず、これを好む者は、これを楽しむ者に如かず」(知・好・楽)という言葉があります。仕事に例えると、いくら、仕事で成功するための知識を持っていても、その仕事を好きだという人にはかなわない。また、ただ仕事が好きだという人は、その仕事が楽しいと感じて取り組んでいる人にはかなわない、ということになるのでしょうか。
確かに、楽しいことをする時は、傍からみると大変なことでも、本人は苦労と感じませんし、楽しいからこそ探求し、知らず知らずに創意工夫をしています。ただ好きだという以上に、楽しんでやることが、仕事の成果につながるということは間違いのないことかもしれません。
ただ、仕事の成果につながるから、仕事を楽しみなさいと言われても、楽しいかどうかは自分次第。大谷選手も、誰かに野球を楽しめと言われて楽しんでいる訳ではなく、創意工夫し努力することが楽しいと自分が感じるからこそ打ち込んでいるはず。楽しむことは自分にしかできません。
ただ、好奇心を持って知識を増やすこと、今、ここに集中すること、失敗を糧にすること、結果よりプロセスを大切にすることなど、仕事を楽しくするための手段はいくらでも紹介されていますが、それこそいくら知識を身に付けたとしても、楽しむことに意義を感じていなければ、長続きはしないのではないでしょうか。
一度きりしかない人生の中で、起きている時間の大半を占める仕事の時間を楽しい時間にすることに自分自身が価値を感じるかどうか。どんな人生を歩んでいきたいか、そこが楽しむことの出発地点のような気がします。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2023 年 03 月 07 日 11:57
お客様の声
お客様の声に耳を傾けて商売をする。これは昔から言われ続けていることですが、「お客様の本音が聞けているか」と言われると、なかなか難しいことかもしれません。
そもそも我々はお店で嫌な体験をしたとしても、わざわざお店に苦情を言うということはせず、「黙って去る」「そこで利用しなくなる」のが一般的です。
いわゆるサイレントカスタマーというお客様です。統計によると、企業の対応で不満があった場合に「企業に対する申し出率」は27.5%。7割の人が不満をもったまま家に帰っているということになります。この人達は、不満が解決されていないので、その企業を利用しなくなる確率が高い。大切な既存顧客を失ってしまいます。それだけならまだしも、最近はその不満をSNSで「不満」を発信して広げてしまうこともあり、ほっておくと企業イメージが悪くなってしまいます。
最近、こんな体験をしました。
いつも利用しているお店に予約の電話をしたのですが、いつもならお店の人が出てくれるのですが、その日は音声ガイダンスに変わっていました。ガイダンスに従って予約をしていったのですが、本当に時間がかかり、途中であきらめてしまいした。人手不足の時代なのでしょうがないとはいえ、以前なら数分で終わっていた予約がこんなにも手間がかかるのかと、不満を感じました。しかし、この不満をお店に伝えようにも、お店にかけても出るのはガイダンスの音声。私の希望は伝わりません。その予約はせず、私は他のお店に行きました。この不満をあえて伝えるかというと、聞かれる機会があれば言いますが、あえてわざわざ言いにいくようなことはしないと思います。
最近は、お客様が気軽に連絡できるように相談窓口を設けるなど、申し出しやすいようにされている企業も多くなっていますが、実際のところ「不満だが、苦情をいうほどのことではない」「そこまでやるエネルギーを使いたくない」というのがほとんどではないでしょうか。
ただ、既存客が一人減ったのは事実。少子高齢化でどんどん顧客が少なくなっていく時代に、大切な顧客を失うことは大きなダメージです。
顧客満足度の高いある会社は、こうしたお客様を少しでもなくしていくために、社内に「クレームは宝」と打ち出し、不満を伝えてくださるお客様を大事にしようと、苦情と向き合い、ひとつひとつを真摯に解決していくことを大事にされていました。顧客が少なくなる時代には、「わざわざ苦情・苦言を言ってくださる顧客」というのは、本当に大切なことを教えてくださる企業の先生のような存在かもしれません。
ある調査によると、様々な技術革新で買い物の仕方や商品そのものは、大きく変化してきていますが、お客様の心理は、昔からそんなに大きく変わっていないそうです。
「繁盛したければ、お客様の声を聴け」という言葉が改めて心に響きます。
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方
2023 年 03 月 01 日 12:47
AIと人間のホスピタリティ
話題のAI、ChatGPTは、様々な質問に答えてくれるだけでなく、文章の作成から、要約、校正、小説や詩の制作までやってくれるAIですが、その正確性や使い方など、まだまだ課題があるとはいえ、これまで時間がかかっていた作業をこうしたAIが代行してくれると、仕事もより効率的になっていくはずです。こうしたメルマガなどもいつかChatGPTが書いてくれる時がくるかもしれません。
外食産業ではタブレット注文があたり前になり、セルフレジのお店はもちろん、今後はレジすらいらないお店が出てくると言われていますが、人口減少による労働力不足の時代には、AIやロボットは不可欠な存在になっていくのでしょう。こうした時代の中で人間の仕事はどのようなものになっていくのでしょうか。
以前、臨機応変な対応、お客様の心に寄り添う対応など、「ホスピタリティ」(おもてなし)は人間にしかできないと言われていましたが、24時間どんな時でも質問に答えてくれたり、機嫌に左右されず、いつも安定して対応してくれるAIは、確かに臨機応変さや気配りは劣っているとはいえ、ある面、人間よりホスピタリティや顧客満足を提供できているとも言えます。
ロボットも以前は無機質なものという感じがしていましたが、表情を変えたり、会話をするロボットと接していると愛嬌を感じることもあり、ロボットが人を癒すということも生まれています。
ホスピタリティの分野まで機械やAIが活躍していくと人の仕事が奪われると心配になりますが、まだ、お客様の雰囲気や表情から気持ちを察知したり、その状況に応じて最善の対応を考えるということは機械にはできないと言われていますし、ロボットやAIがお客様との人間関係を築けるとは思えません。人間らしい気配りや人間力が、今以上に人に求められていくのだと思います。AIやロボットの対応は確かに便利で、良いことがたくさんありますが、お客様との絆をつくる顧客サービスの世界は、いつまでも人が中心になりそうですし、そうあってほしいなと思います。
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方
2023 年 02 月 20 日 18:07
お客様の立場に立つ
お客様の立場に立って考える。お客様のニーズをつかむ。
昔から接客においても、商品開発においても、お客様の側に立って考えて行動することが大事であると言われています。ただ、実際は「お客様のためになる」と思ってやったことが、すべて上手くいく訳ではなく、思ったよりもヒットしなかったり、「お客様のために」と考えたことが、逆に余計なお世話だと感じられてしまったというようなことが起こったりします。
以前こんな話を聞きました。あるお客様のお店の「おもてなし」についての感想です。
「お店に入った時、駐車場でスタッフがドアの前で迎えてくれるのは嬉しいんだけど、何となく早く降りろと言われているようで嫌な気になった」。
お店側としたら、店舗で挨拶をするより、お客様の車の方まで行ってお迎えする方がお客様に気持ちが伝わると思われてやっている「おもてなし」だと思います。しかし、お客様の立場になってみた時、確かに目の前で待たれていると逆に気を使ってしまう。そんな気持ちもわかります。もちろん、これが「嬉しい」「気にならない」というお客様もおられますので、この接客がすべて悪い訳ではないはず。ただ、店側が「お客様のために」と思ってしたことと、お客様の感じ方がずれることは、よく起こっていることかもしれません。
セブンイレブンの創業者、鈴木敏夫さんは、「お客様のために」と「お客様の立場に立つ」という考え方は違うと言われている経営者です。
「お客様のために」という時は、どこか「過去の経験」をもとにしたお客様に対する思い、決めつけがあり、お客様がそれを良いと思われているどうかはわからない。「お客様のために」と言いながら、自分達のできる範囲でしか考えていないのではないか。どこかで自分達の都合を優先しているのではないかと言われています。
「お客様の立場に立つ」ということは、あくまでもお客様の立場で見ることで、お客様のニーズから発想していくこと。もしかすると自分達にとって不都合なことでも実践していかなければならないこともある。だからこそ「お客様のために」ではなく、「お客様の立場に立つ」というお客様を起点にして考えていく。その重要性を従業員に伝えておられています。
「お客様のために」という思いは悪いことではなく、人の役に立とう、喜んでほしいという姿勢は商売の上で大事なことだと思います。ただ何が良いかどうかはお客様が判断すること。その立場に考えてみないと間違ったことをしてしまいます。「お客様の立場で」と強く言われるのはそうした戒めだと思います。
ただ、お客様からの目線で見るということは、意識しないとなかなかできません。鈴木敏夫さんも、実際に毎日、商品を試食し、土日でも消費者としてセブンイレブンを利用して、「お客様の立場に立つ」を実践されていたそうです。
「お客様のために」と「お客様の立場に立つ」。つい、同じような意味で使ってしまいますが、良い商品をつくるためにも、お客様に喜んでいただく店にするためにも、やはり「お客様を起点に考える」ことが重要なポイントになるのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 02 月 14 日 11:10
心の置き方
「その日が、お客様にとっていい一日になればいいなと思って働いています」
これは、以前、ある旅館を取材させていただいた時、朝のバイキング会場でお客様に声をかけ、いろいろとお世話をするスタッフの方がおられたので、インタビューをさせていただいた時にその方が仰った言葉です。
自分の仕事は、単にバイキングでなくなった料理を補充する係ではない、自分は、お客様のいい思い出をつくる仕事をしているのだ、そんな風にとらえられて働いておられるその方の接客が心に残りました。
同じ仕事でも、「今日もバイキング会場で料理の補充をするのか」と思うこともできますが、こんな風にとらえて働くこともできる。自分の仕事をどう捉えているか。心の置き方ひとつで同じ仕事でも景色は大きく変わっていくのだろうと思います。実際にその方は、足のご自由なご老人の方に料理を取り分けあげたり、ここでしか食べられない特別な料理をご説明されたりと、バイキング会場に来るお客様を笑顔にされていました。
よく「CSが大事だ」と接客の技術や行動を改善していこうと「やり方」を見直すことがありますが、どれだけ接客のやり方を学んだとしても、その人がそれを「やらなければいけない作業」だと思ってやっている仕事と、「お客様にいい一日を過ごしてほしい」と思ってやっている仕事では、まったく違った仕事になってしまうと思います。
世の中にはいろんな職業がありますが、考えてみればすべて同じことかもしれません。例えば、車を販売する営業マン。自分の仕事は「車を販売する仕事」だと思って仕事をするか、「その家族が幸せに過ごせる車選びのお手伝いをする仕事だ」と思って仕事をするか。車修理をするメカニックであれば、自分の仕事は「車を修理する仕事」と思って作業をするか、「お客様が不安なく、ずっと幸せに車を利用していただくための大切な仕事だ」と捉えて燃えて仕事をするか。自分が顧客ならどちらの人から買いたいか、頼みたいかと考えてみた時に、多くの人が後者の人に対応してほしいと思うのではないでしょうか。
ただ、心の置き方は自分で決めるもの。仕事をどうとらええるか、自分自身がどうあろうとするかは、その人が決めるしかなく、他人がコントールすることはできません。どうせ仕事をするのであれば、自分の心が前向きになる場所に心を置いていきたいです。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上
2023 年 02 月 07 日 14:07
やってみなはれ精神
ここにきてだいぶコロナ禍も収まりつつありますが、この数年間、飲食や旅行などのサービス業の皆様は本当にたいへんな時期を迎えられたと思います。来店客がゼロになる、しかし大切な従業員を簡単に解雇する訳にはいかないという厳しい選択が迫られる中で、何とか業績を上げようと新しい取り組みに挑戦された方も多かったと思います。先日あるホテルの経営者にコロナ禍での取り組みをお伺いしましたが、料理の通販やお弁当の販売、団体にホテルを1棟丸ごとお貸しするプランなど従業員の皆さんとアイディアを出し合い、この数年間、必死に取り組まれたそうです。行ったものの中には全く売れないものなど、たくさんの失敗があったそうですが、その挑戦の中にはヒットし、今後の新しい柱に成長したものもあったそうです。コロナだからと尻込みをしなくてよかった、やってみることの大切さを痛感したと、その経営者が語っておられました。
「やってみなはれ。やらなわからしまへんで」。これは、国産初のウイスキーを開発したサントリーの創業者、鳥居信治郎さんが大切にされていた言葉だそうです。
入念な市場調査を重ねて開発した新車が売れなかったり、逆に思いもかけない売れ方をすることがあるということがあるそうですが、未来を確実に予測できることは少なく、何事も「やってみなければとわからない」ものかもしれません。
サントリーさんが創業した戦後の混乱期や現代のコロナ禍など、誰も経験をしたことがないことが起こった時や、未開拓の分野に出る時は、誰も正解がわからない。だからこそ、「やってみなはれ」という歩き方が必要だったのでしょう。以前、新しい仕事をする時はPDCAではなく、まず行動から始める「D‐CAP」が大事だという考え方を教えていただいただことがあります。安全に関わることや大きな予算や多く人が動くような仕事は入念な計画をしなくてはいけませんが、初めてのプロジェクトや未知の分野の仕事をする時は、とにかく小さく始めてみること、そこから学び、改善していくという「D‐CAP」の方が良いのかもしれません。
ただ、そうはいっても「まずやってみる」ということは、勇気がいります。責任の重圧や失敗した時の恐怖、未知の世界に飛び込む時は誰でも怖いもの。
「やってみなはれ、やらなわからしまへんで」と言えるリーダーでありたいなと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 01 月 31 日 17:05
心のこもった挨拶
小売業やサービス業では、昔からお客様に挨拶をすることが大切だと言われています。
「おはようございます。」「いらっしゃいませ」「ありがとうございます。」とスタッフが元気に挨拶をしているお店は、活気を感じますし、顧客として気持ちがいい。挨拶を良くする店では、顧客が声をかけやすくなるので、ちょっとしたことでも相談がしやすくなり、顧客満足も高まると言われています。また、スーパーなどでは、挨拶がよくなると苦情が減り、万引きも少なくなるという効果もあるそうです。会員カードのキャンペーンをやって固定客を増やしてもうまくいかなったお店が、挨拶を徹底したことで、ファンが増え、固定客も売上も増えていったという話を聞いたことがあります。
しかし、これほどみんなが「挨拶の大切さ」をわかっているのに、「挨拶をしましょう」と号令をかけたり、挨拶強化月間などで徹底しなければならないのは、「挨拶が徹底できない」という問題があるからだと思います。挨拶を訓練し、管理し、注意をすれば、その時は良くなっても、数か月後にはもとに戻ってしまうという話をよく聞きますが、それほど「挨拶」を徹底するのは、奥が深く難しいことなのだろうと思います。
特に、挨拶は形以上に「気持ち」が重要。どれだけ「いらっしゃいませ」と声を出していても、心がこもっていなければ、逆に「感じが悪い」という評価になってしまいます。本来、挨拶は気持ちを伝えることですから、心から「ようこそお越しくださいました」という気持ちがあれば、アイコンタクトや笑顔だけでも通じるもの。「心のこもった挨拶を全員が行う」ということは、命令や管理でうまくいかないのだろうと思います。
以前、ある有名なスーパーが取り組まれた挨拶強化の話を聞きました。その経営者は、どうすれば挨拶が徹底できるかと考え、結論として、やはり働く人が「お客様に喜んでいただきたい」という気持ちをもって働くことが、命令で挨拶をさせることより大事なことであると考え、様々な取り組みを実行されました。
「お客様に喜んでもらいたい」という気持ちをつくるには、まず、働く人がいかに自分の仕事に誇りや満足感を持ってもらえるかが大事である。まず取り組まれたのが、商品知識の教育でした。売り場でお客様から商品の質問をされても、答えられないと顔が下に向いてしまい、挨拶もできなくなる。売る商品に自信をもってもらうことが大事だと、商品知識の教育をされました。接客においても「売ろう」とすると感じが悪い接客になる。「商品を売ろうとする接客をするな」という指示を出されたそうです。また、働く人が気持ちよく、楽しく働ける環境がなければ、お客様に喜んでもらおうという気持ちも生まれない。そこで、上司が職場に出向いて不満を聞き、現場との話し合いも続けられました。お客様に喜んでもらうことが商売であるという思いを伝え、トップが店舗で話し合いを重ねる中で、次第に社員の中にトップの「お客様に喜んでもらう店にしたい」という思いが通じるようになったそうです。そこから全員が気持ちのよい挨拶をするお店に変わっていったというお話でした。たかが「挨拶」といえば挨拶ですが、本当は奥が深く、徹底するためには本気で取り組まないといけないことなのだと思います。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営
2023 年 01 月 24 日 10:47
仕事の使命感
自分は何のために働いているか。自分の仕事の使命をどうとらえるかで、日々の仕事は大きく変わってくると思います。例えば、店の掃除をするという仕事でも、決められたところを、ただ掃除するのが自分の仕事だと思ってする掃除もあれば、「私の仕事は、来られるお客様に良い思い出を作っていただくこと。だから少しでも綺麗にしよう」と思ってする掃除もあります。自分は、何のために働いているかという使命感ひとつで、日々の仕事の景色は大きく変わっていくはずです。
先日、こんな話を、あるホテルのスタッフの方から伺いました。
宴会部で働くその女性は、仕事にやりがいを感じることがなく、ただ受注した宴会を予定通りにこなすことが仕事だと思い、日々働いておられました。あるとき、その会社で宴会部の使命をもう一度見直そうということになり、幹部の人たちで宴会の本当の使命を話し合ったそうです。宴会部の目的はただ料理を出すことなのだろうか?そもそも何のためにお客様は宴会をするのだろうか?時間をかけて話し合った結果、どのお客様も宴会が目的ではなく、人と人との絆を深めたいから、人が集まり食事をするのだと、この仕事の原点に気づかれたそうです。宴会部の仕事は、ただ料理を出すことではない、本当の使命は「お客様一人ひとりの絆づくりのお手伝いをすること」だと、改めて自分の仕事の意味、意義を感じたそうです。そこに参加していたその女性は、その時から自分自身の仕事への向き合い方が変わりました。ただ予定通りに仕事を終わらすことだけ考えていた「つまらなかった仕事」が、どうすればお客様に喜んでいただけるかと考えながらする仕事になり、今まで以上に仕事が楽しく、やりがいを感じるようになったということでした。
この女性が働くホテルは、大阪、道頓堀にある株式会社王宮という会社のホテルです。今でこそ、リピーターのお客様が多いお客様満足度の高いホテルですが、以前はそのようなホテルではなく、会社も暗い雰囲気だったそうです。そこから経営者が理念や使命を明確にし、社員の人たちと共に理念を作りあげ、変革されていくのですが、これは、その改革の途中であったお話です。
販売をしなれば、業績を上げなければと、目の前のことばかりを考えて仕事をしていると、自分の仕事の使命とは何かということを考える余裕がなくなってしまうのかもしれません。ただ、頑張るだけでは疲れてしまいます。宴会部の彼女は、以前と仕事は同じでも、心は疲れない。楽しく働けるようになったと話されていました。やはり、自分は人に役立つ素晴らしい仕事をしていると感じて働けている時は、疲れも感じないのでしょう。仕事の使命感。仕事をする上で最も大事なものだと思います。
カテゴリー :
DOIT! 経営理念の浸透・共感
2023 年 01 月 17 日 17:41
働く人の幸せとやりがい
先週の土曜日、ホワイト企業大賞の表彰式が東京で行われました。
このホワイト企業大賞は、世の中に「いい会社」を広げていこうと、様々な人が集まって運営されている活動です。私も委員の一人として参加しています。今年も多くの企業がエントリーされ、21社の会社が様々な賞を受賞されました。
ところで、「いい会社」とはどのような会社でしょうか。人によって「いい」という基準は様々だと思います。
ホワイト企業大賞では「いい会社」とは、「社員の幸せと働きがい、社会への貢献を大切にする会社」と定義しています。業績や利益を追い求めるのではなく、働く人たちが幸せや働きがいを大切にし、社会に役立つ会社であろうと努力を続ける会社を「いい会社」であると、ひとつの方向性を示しています。
これは「方向性」であって基準ではありません。経営において「社員の幸せや働きがい」を大切にしている会社が、この賞をひとつの指針としながら、切磋琢磨して進んでいく学びの場でもあります。
しかし、社員の幸せや働きがいとはどんなことでしょうか。
給料が良い、休みが多い、福利厚生が充実しているという目に見えることもありますが、働きがいとはそれだけではなさそうです。アンケートを取ると、社員の人たちが充実して働いていることが見えてきます。
この会社で働いていると自分が成長できる、自分が決めて仕事ができる(任されている)、他者に役立っているという実感がある、自分の個性が活かされていると感じる・・・。働く時間が充実した時間であるからこそ、前向きに働け、社員が協力しながら、もっと良い仕事をしようと助け合いながら頑張っている姿が見えてきます。だからこそ、こうした企業は総じて業績も伸び続けています。
企業は業績をあげ、利益を出してことが求められます。だから、業績を大切にする会社は多い。しかし、大切にするものの順番が違うとその経営も変わっていきます。応募されている会社が、いちばん大事にされているのは「社員の幸せや働きがい」。それを追求していくことが業績や利益につながっていくという信念で経営をされている会社です。いちばん大事にするものの順番が「社員」なのです。
昭和の時代から、他社と戦い、業績を追求する時代が続いてきた日本の中で、ホワイト企業大賞が示すこの方向性の経営は、まだ異端に見えるし、甘い考え方に見えるのかもしれません。
ただ「どうせ働くなら楽しく働きたい、やりがいを感じながら働きたい」というのは、考えてみれば誰もが求めている普通の思いだと思います。いい会社づくりとは、ただその当たり前を大切にしていくことであり、人間にとって自然なことなのだと思います。
ホワイト企業大賞
http://whitecompany.jp/
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営
2023 年 01 月 12 日 10:23
あくなき向上心
一次的に繁盛していても、すぐに飽きられてしまうお店もあれば、何年も繁盛し続けるお店があります。いくら優れた商売でも、時代が変化する中で、同じことをしていてはお客様に飽きられてしまいますし、他店が進化すると差がなくなってしまいます。サービス業に限らず、どの企業でも永続的に繁盛し続けるということは大変なことです。現状に満足せず、常に進化していこうという姿勢がなければ、何十年も支持され続けることはできないと思います。
36年もの間、顧客満足日本一に輝く旅館「加賀屋」さんは、全国にファンがいる老舗の会社ですが、昔から、そんな評判に満足せず、常により良いおもてなしを追求してこられた会社です。毎月の会議で真っ先に話されるのは業績ではなく、客室で集められた「お客様の声」を社長を筆頭に全員で確認するところから始まります。そして少しでもご不満があれば、すぐに改善をする。お客様に喜んでいただける旅館づくりのために、常に地道な取り組みを続けてこられてきた旅館です。
そんな加賀屋さんも、ある時、CSの評価が全国3位に落ちてしまい、36年間守り続けてきた日本一の座を明け渡す事態があったそうです。代表の小田さんは、この時、「もしかすると私たちの中に“自分達は日本一であり、このままで良いのだ”という慢心があったからかもしれない。」と、創業から大事にしてきた加賀屋のDNAの形骸化に危機を感じ、おもてなしを見直していこうと、顧客の声からの改善のサイクルを短くしたり、暗黙知だったおもてなしのDNAを明文化して全員で共有するなど、様々な取り組みをされたそうです。その結果、一年後には日本一に返り咲くことができたそうです。
誤解のないように申し上げますが、加賀屋の社員の人たちは、日本一の旅館であることに誇りを持ち、それに恥じないおもてなしを追求されている方ばかりです。それでも、どこかに慢心が出てきてしまう。誰でもそうだと思いますが、うまくいっている時は、どうしてもこのままで良いと安心してしまいます。そうした中で、加賀屋さんが日本一であり続けてこられたのは、どのような時も「お客様の喜び」を第一に考え続け、常に今のままではいけないという危機感を持ち続けてこられたからだと思います。
ある方が、「進化・向上する会社しか人財は育たない」と話されていましたが、確かに同じことを繰り返している会社で人は育たちません。やりがいもなくなってしまうのでしょう。加賀屋さんが、いつも会社全体でより良くしよう、もっとよくしようと取り組まれていくことは、お客様の満足だけでなく、働く人たちの誇りややりがいにつながっています。現状に満足することなく、常に創意工夫する。そのあくなき向上心こそ繁盛し続けていくために最も大事な価値観ではないでしょうか。
カテゴリー :
DOIT! これからの時代の人財育成
2023 年 01 月 06 日 11:36
地域から尊敬される会社
それぞれの街にはその地域を代表する企業があります。
その中でも「〇〇さん」と地元の人が「さん付け」で呼ぶ、地域の人から親しまれ、尊敬されるような会社が存在します。北海道の六花亭さんや博多のふくやさんなどは、地元の人から長く親しまれている会社です。
そうした会社は、もちろん素晴らしい商品を販売されていることや、買い物をする時の良い接客も評判を生み出しているのだと思います。それ以外にも、地元の行事に参加したり、地域の発展のために、地域貢献活動にも惜しみなく投資する姿勢なども、地元から尊敬されているのでしょう。
しかし、いくら表面上で地域貢献活動をしたとしても、会社の実態をいちばん良く知っているのはそこで働く社員の人たち。働いている人が家族や友人から「会社はどう?」と言われた時に、「いい会社だ」と言うか、「あんな会社は・・」と言うか。社員の人たちが働きがいを感じていなければ、良い評判は生まれません。地域の評判はそこで働く社員の人たちの存在も影響しているのではないでしょうか。
長野県の伊那食品工業さんも、地元の人たちが「伊那食品さん」と親しみを込めて呼び、地域から尊敬される会社のひとつです。会社という存在そのものが地域の人に迷惑をかけているからと、会社の敷地につくったガーデンを地域の人に無料で開放されているのは有名ですが、社員の人たちは、出勤時に車を右折して会社に入ると前の道路が渋滞になってしまうからと、少し遠回りになったとしても、みんなが左折で入るようにしておられるそうです。休みの日に買い物に行くときも、スーパーの店に近い駐車場は身体の不自由な人が利用する場所だからと、多くの社員があえて遠い場所に車を止めると言います。自分の会社の理念に共感し、誇りを感じているからこそ、会社から言われた訳でなくてもこんな行動をされるのでしょう。
昔から、売り手よし、買い手よし、世間よしと、商売は「三方よし」が大事であると言われていますが、これからの時代に長く存続していくためには、やはり地域から応援され、尊敬されるくらいの会社にならなければいけないのかもしれません。その為には、まず自分たちの会社が働く社員の人たちを大切にし、社員の人から尊敬される会社であること。近江商人の言葉に「売り手よし」が先にあるのはそういう教えなのかもしれません。
カテゴリー :
DOIT! 「いい会社」が実践する理念経営