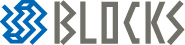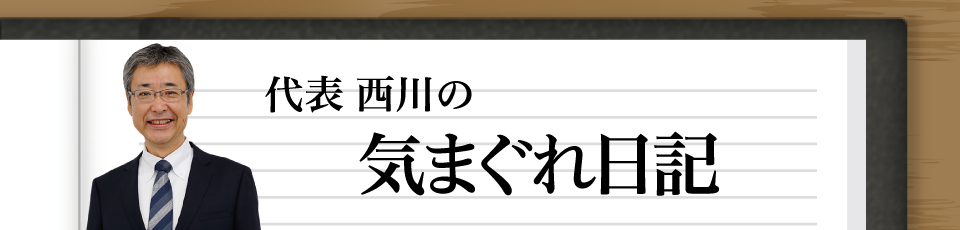2026 年 01 月 19 日 17:54
仕事を丁寧にするという競争力
ビジネスの現場では、よく、もっとスピードをもって効率をあげようという言葉が飛び交います。確かに時間あたりにどれだけ成果を出すかという指標は大事です。しかし、足りていないのはスピードなのでしょうか。本当に成果が生まれる、うまくいっているプロジェクトや成果があがり続けている組織を見ていると、スピードを上げる以上に、仕事を丁寧にしようということに力を入れているような気がします。
丁寧な仕事というのは、単に時間をかけることでも、慎重になりすぎることでもないはず。丁寧さとは、この仕事を届ける相手や結果を想像しながら仕事をすることだと思います。例えば資料をつくる時でも、この一行が相手にどう伝わるか。この言葉は、誤解を生まないか。この一手間で、次の人は楽になるか。相手を考え丁寧にする仕事は、自然と無駄が少なくなり、やり直しも起こらない。結果として最短距離で成果にたどりつくような気がします。
丁寧にやりたいが、時間がかかるから難しいという人もいます。しかし、そうやって丁寧さを欠いた仕事をしていると、説明、修正、クレーム、確認という形で、何度も組織の時間を奪っていきます。そう考えれば、時間をかけるということはコストではなく、後戻りを減らすための投資といえるのかもしれません。
丁寧な仕事をする人や会社は、自分の仕事を自分の範囲でみるだけでなく、その先にいる顧客、同僚、会社全体まで含めて仕事を引き受けているように思います。だからこそ、手抜きしない。見ていないところでも丁寧にやるので、質が落ちない。「丁寧さ」が評価されない組織もあるようですが、丁寧さを大事にする人や組織が結局、周りから信頼され、長く続いていくようにも思います。
仕事を丁寧にするとは、会社を大切にすることであり、人を尊重することであると思います。そして、自分自身の価値を下げない選択。派手さはないのかもしれませんが、長く信頼される仕事する人や会社は、例外なくここが強いような気がします。丁寧な仕事というのは、最も地味ですが、最も再現性があり、最も裏切らない経営資源なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 12 月 12 日 10:44
仕事の奥にある楽しさ
「仕事は、毎日同じことの繰り返しで、つまらない。」そう感じている人も多いかもしれません。あるホテルの経営者に聞いたことがあるのですが、右も左もわからない新人の時は一生懸命フロントで接客をやっていた人も、ある程度仕事ができるようになると以前の輝きが消え、いつの間にか辞めてしまうということがあるということでした。
確かに、ただ同じことを毎日繰り替えしていると仕事は面白くありません。だから、仕事を楽しくするには「同じことを繰り返さない」ということになります。しかし、「業務は決められているのだから、毎日同じことを繰り返すだけだ」とも言われます。どうすれば楽しくなるのでしょうか。
先日、ある美容院のベテランスタッフの方に、シャンプーをしていただく機会がありました。普段シャンプーは新人や若いスタッフがする仕事なのですが、この日は若い人が研修で不在だったので、20年以上この仕事をされてこられたベテランの美容師の先生が私を担当してくださったのです。その手さばきは実に丁寧。シャンプーの間の言葉も、雰囲気も心地よく、夢見心地になってしまいました。
どのようにこういう技術を覚えられたのかと伺ってみたのですが、やはり若い時に毎日シャンプーに取り組みながら技術を向上させてきたということでした。「どうすればもっと気持ちのよいシャンプーができるか」と、手の強さや洗い方を工夫したり、人のまねをしたり。また、お客様によって頭皮の柔軟性が違うことに気づかれて、お客様の皮膚に合わせて力加減を変えるなど、「お客様にとって気持ちよいシャンプーとは何か」という課題にずっと取り組んでこられたそうです。
奥を知らない人からみると、この人は一見シャンプーという「同じ仕事」をしているように映るかもしれません。しかし、この方にとっては、毎日が違う仕事に挑戦している感覚。だから面白くなり、何十年も続けてこられたのでしょう。
どんな仕事にも「奥」があると思います。掃除でも、検査作業でも、一見単調に見える仕事でも、もっと良くできる、もっとうまくできるはずだと追求すればするほど、だんだん奥が見えてくる。まだまだ未熟な自分に出会う。だから技術を高めたくなる。これが「仕事の楽しさ」ではないでしょうか。
「そこそこできる」で「自分は仕事ができるようになった」と思っていると、後はその繰り返し。面白さには出会えない。若い人に、この「奥」の楽しさ、「仕事を深める」ことの面白さを、どう伝えていけるかが先輩の仕事なのだと思いますが、数秒のタイミング、数グラムの力加減で出来栄えが変わるこの世界を言葉で伝えていくのは本当に難しい。その人が「自分もそこに行きたい」と思わないとつかめません。
ただ、仕事は、毎日同じことをくり返すこともできるし、毎日進化させていくこともできる。どちらを選びますか。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2025 年 11 月 27 日 15:22
やらされる仕事とやりたい仕事
世の中にはいろいろな仕事がありますが、同じ仕事をしていても、そこにやりがいを感じてやっている人もいれば、しかたなくやっているという人もいます。やらされていると感じながらやる仕事は、辛いのだろうと思っていたのですが、最近はそれに慣れてしまう人もいると聞きます。自分の意見も言わず、工夫もせず、ただ言われたことだけをやり、時間になったら帰る。お金のため、生活のために自分の時間を売るというのも生き方のひとつなのかもしれませんが、同じ仕事でも、そこに面白さや楽しさを感じられれば自分自身の人生も変わると思います。だだ、仕事を面白くしたいかどうかも決めるのはその人次第。無理に変える訳にはいきません。
しかし、どうすれば、仕事が「面白い」と感じられるのでしょうか。
先日の休みに、地域のボランティア活動があり頼まれてその手伝いをしていました。朝早くから荷物を運びテントを立て、企画していた催し物を協力して実行する。傍から見てもかなりハードな仕事ですが、そこに集まったスタッフの人たちは実に楽しそうにその活動に取り組んでいました。食事は自分持ち、報酬はゼロ。しかし、みんなで来場者をもてなし、イベント運営に一生懸命に取り組んでおられます。
傍から見れば、会社と同じような「業務・作業」をしているように見えます。しかし、全員が笑顔。なぜ会社の業務は「やらされ」になり、無償のイベントが「やりたい」になるのでしょうか。
単純にいえば、この人たちはこの仕事に意義を感じている。スタッフの人たちは、このイベントの趣旨に心から共感しています。これが会社との違い。
ただ、いくら意義に共感して参加していたとしても、会社のように、上からの指示命令ばかりでは「やらされ」になるはず。主催者の動きを見ていると、とにかく、みんなを巻き込んで、スタッフの人たちの意見も聞き、みんなで作り上げるような運営をされています。その人に任したブースは、その人が考え、その人が行動してやっていく。もちろんメンバー同士の人間関係がいい。この空気も楽しさのひとつのようです。
意義の実感と自由裁量、良好な人間関係。その仕事に意義を感じるかどうか、自由裁量があるかどうか。報酬のあるなし、会社かどうかではなく、これが「業務・作業」を“楽しい”に変える要素なのではないでしょうか。自分の仕事の本当の価値や意義を見つけ、自分のやれる領域を自分で伸ばしていけば、仕事は「やりたいからやる行為」に変わっていくと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2025 年 10 月 23 日 13:00
挑戦の場と安全の場
先日、務めていた会社を辞めて自分で起業し一年たった30代の若い経営者の話を聞く機会がありました。起業当初から相談に乗っていたのですが、目標を持って挑んだものの、この一年、何度も壁にぶつかってうまくいかないことが山のようにあったそうです。しかし、壁を乗り越え続け、この一年を振り返ると、出来ることが増えたことはもちろん、何より仲間への感謝や仕事への考え方など、自分の成長も実感したと話をしていました。一皮むけたその様子を見ると、自分で選んだ道とはいえ、自分で目標を立て挑戦していくことは、プレッシャーが大きくても人としての成長につながる大事な機会だと感じました。
一方、最近、人手不足の中で、若手の育成に変化が起きていると聞きます。無理をさせると人が辞めてしまう。ノルマの廃止に踏み切ったり、できるだけ負荷を与えないなど育て方を変えている企業が増えているそうです。確かにプレッシャーが少ない職場は気持ち的も楽なのかもしれません。辞める人も少なくなるのかもしれません。しかし、そうした職場を若い人は望んでいるのでしょうか。ノルマやプレッシャーが嫌で会社を辞めていく人もいる一方で、最近、プレッシャーが少ない会社でも、「このままこの職場で働き続けても成長できない」と転職する若者も増えているということも聞きますが、挑戦もない、ゆるい会社は楽ではあっても楽しくはない。挑戦して成功や失敗を経験しなければ、成長もありません。
人が成長する職場とはどのような職場なのでしょうか。先日、全国的に優秀な営業成績を出し続ける優績スタッフが次々と育つ、ある地方の会社を取材させていただきました。全員が高い目標に挑戦する厳しい環境にも関わらず、ここ数年離職者はゼロ。1年目は先輩の指導を受けながら営業を学んでいきますが、2年を過ぎるころには、ほとんどの人が自律的に働き、優秀な営業スタッフに育っていくといいます。さぞ厳しい上司がいるのかと思うと、そういう人はいません。その職場で昔から受け継がれてきたのは、高い目標に挑戦することはプレッシャーも大きく大変だけど、その中で必ず人として成長できるという成功体験。成長を実感した先輩が、今後は背中を押す役になり後輩の成長を支えます。「辛い時に先輩に声をかけてもらったことが励みになった」「悩んでいる時、先輩が相談に乗ってくれたことが成長につながった」。そんな成功体験が受け継がれています。高い目標に挑戦するシビアな環境でありながらも、職場ではみんなが支え合っていくので誰も孤独にならない。それがやる気の源泉になっていると言います。優しいだけ、甘いだけの職場では人は育たない。厳しいだけの職場でも続かない。厳しいけれど、困った時に何でも聞ける職場だからこそ頑張れるんだと若いスタッフが話されていたのが印象的でした。成長には、高い目標に挑戦することが不可欠ですが、同時に支え合う仲間も必要。成長するための挑戦の場と、信頼しあう仲間がいる安全な場。そんな両輪が混在している職場が、成長できる職場なのではないでしょうか。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 素晴らしい組織風土づくり
2025 年 09 月 22 日 16:44
先義後利
お客様が求めるからといって、何でも無料ですることは無駄ではないか。これは誰もが思うことだと思います。提供したサービスに対してお客様が対価を払ってこそビジネスは成立する。これはきっとビジネスの常識です。しかし、この常識にそったやり方で本当に商売が成立しているのかというと、そうではない気がします。
例えば、雨の日に荷物を持ったお客様が駐車場に向かわれた。それに気づいた一人のスタッフがお客様に駆け寄り、傘を差しだして車までお送りしてあげた。こんなサービスは普段の商売の中でもよくあります。こうしたスタッフのサービスは、決して利益を生み出していないかもしれません。ビジネスとすれば無駄ともいえます。しかし、こうしたスタッフの気遣いは、きっとお客様の心に残り、「また利用したい」と思ってくださるかもしれません。利益を忘れて、思わず行った行為が、結果として自分の利益としてかえってきたということは、人生の中でもあることだと思います。
こうした姿勢を表す言葉として、「先義後利」という言葉があります。これは中国の儒学・荀子に登場する言葉で、「利益より、人としての道義、義理を最優先にしていれば、利益は後から勝手についてくる」という意味です。日本では300年前に呉服店として創業した百貨店・大丸の創業時の経営理念としても有名です。
ただ、最近は何でも結果が求められる時代です。人としての道義や義理などの理想のようなものを優先して、コストはどうなるのか、商売は本当に成り立つのかと思う人も多いかもしれません。ただ、この先義後利を商売の姿勢として実践している企業は全国各地にあり、そして、そうした企業は着実に発展しています。
名古屋にある「レクサス星が丘」。お客様満足の高い店として有名ですが、創業時から、「お客様への価値づくり」を理念とし、お客様本位の商いを続けてこられました。先日、お店を訪問させていただき、創業時の話を伺ったのですが、このレクサス店でさえ最初の5年間は赤字続きだったそうです。しかし、それでもお客様に価値を提供しようと、困っておられるお客様がいれば、それに応え、不便な思いをされているお客様がいたら、みんなで考え改善する。判断軸は「人としてどうしてあげるとよいか」。利益以上にお客様本位に商いを続けてこられました。当初は赤字が続いていましたが、こうした商いを続けているうちに、少しずつファンが増え、販売も伸び、開業20年目の今年になって管理顧客は全国平均の3倍にもなっているそうです。「我々にとって台数は標ではない」と言っておられましたが、お店の姿勢が少しずつ地域のお客様に伝わり、「あの店はいい店だ」という信頼につながっているのだと思いました。
世の中には自分のこと以上に相手のことを考え行動する人がいます。そうした人に感謝や信頼が集まって、結果的にその人も利益が渡る。先に人に与える。喜びを優先する。先義後利は、不変の原則なのかもしれません。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 07 月 29 日 10:11
可能性の蓋
先日、30代前半ですが海外で仕事をしている若い方たちと話をする機会がありました。その人はこれまで一度も日本の企業に就職したことはなく、すべて自分で道を切り開いていく生き方をしておられます。事業に必要な技術や知識はすべて独学で学び、海外に行きたいと思えば語学を学び、決して安定の道を進むのではなく、失敗をしながらも自分のやりたいことに挑戦を続けています。
よく「自分の能力はこんなものだ」と現状に縛られ、自分成長をあきらめてしまう人も多い中で、その人は「やってみてから考えればいい」「できないことはない」と自分の可能性に限界を設けていません。なぜ、そういう考え方や生き方になったのかと聞いてみると、両親の姿を見てきたからだと言います。子どもがやろうとすることを決して否定しない。自分のやりたいことをやってみたらいいという育て方をしておられます。それ以上に両親自身が、そのような生き方をしている人達なので、自然とそう考えるようになったということでした。心配のあまり、子どもに対して「お前には無理なんじゃないか」「リスクがあるからやめた方がいいのではないか」と育てる人も親もいると思いますが、その両親は、子どもが小さな時から、人に迷惑をかけないこと、人に感謝することなどの「人の道」の基本は厳しく教えるものの、それさえ外さなければ、何でもやらせてくれたそうです。
企業の中での人材育成においても、同じかもしれません。この人の能力はこうだと決めつけている上司もいます。失敗をさせないように事細かに指示をして人を動かす人もいます。親がつい子供に失敗させたくないからと、親の過去の経験や価値観を押し付けてしまうことがあると思いますが、それが子どもの自信や自分の可能性を信じる気持ちを奪っていることもあります。企業においても、良かれと思って指示をする、アドバイスをする。しかし、それが逆に可能性の蓋を閉ざせてしまっているのかもしれません。
最近、若い人が挑戦しない、指示通りにしか動かないという悩みを聞きますが、本当にそうなのでしょうか。可能性を信じて軽々と未来に挑戦する若い世代の話を聞くと、そうなってしまうのは若い人の問題ではなく、若い人の可能性を信じない、任せようとしない、挑戦しようとする気持ちを抑えつけてしまう親や上司側の問題かもしれないと考えてしまいます。もし、職場で若い人が辞めていくとすれば、上司の姿から可能性を感じられなくなってしまっているのかもしれません。
先ほどの人は、今の時代はやろうと思えば何でも情報が手に入るから、人に教わらなくても独学で何でもできるんだと話していました。教えてくれる上司が一人もいない状況でもどんどんと成長しているようです。教えないと人は育たないと、過去の常識に縛られているのは、もしかすると私たちの方かもしれませせん。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2025 年 07 月 02 日 11:55
お客様本位と効率性
先日、地元の友人が、ある飲食店について「あの店はすぐにお皿を下げに来て、ゆっくりできない」と対応について不満をもらしていました。お店としてもさすがに「早く帰ってほしい」という気持ちはないと思いますが、お客様からするとすぐに皿を片付けに来られると、何かせかされているような気持ちになります。
お店の側は、早く皿を下げて片づけたい。回転を速くして効率を上げたいという気持ちがあるのかもしれませんが、その効率優先のたったひとつの行為でお客様を失ってしまっているのだとしたら本当に勿体ない。さらに、こうして悪い口コミが広がってしまうのは、本当に残念です。
効率を優先する、しないということで思い出すのは、以前DOIT!でご紹介した川越胃腸病院です。取材中、看護師さんが患者様の検温のために各部屋を回るシーンがありました。しかし、その看護師さんはある部屋で患者様が寝ておられるので「このまま寝かせてあげようと」、やるべき検温をせず次の部屋に行かれます。検温しないともう一度来なければなりません。効率で考えると患者を起こして検温をした方が良いはずです。その看護師さんは「この病院の方針は、あくまでの患者様本位。そっとしておくことが本当の看護であって、寝ている患者を起こしてまで検温をするのは、看護ではないと教えられているんです。」「これまで勤めていた病院では、決めら仕事をしてこないで帰ると怒られたけど、この病院は誰も怒らない」と話してくださいました。
検温を後回しにするのは、二度手間で不効率な行為。しかし、この病院はあくまでも患者様が優先。もちろん経営なので効率も大事にされていますが「お客様の幸せが病院の理念」であると、たとえ手間が増えたとしてもお客様の満足を優先する。どこまでいっても基準はお客様の満足です。
そもそも「生産性」という言葉は工場などで使われる言葉。しかし、サービス業で生産しているものは「お客様の満足」であるとすれば、患者様を起こさないであげる方が生産性は向上していると言えます。最初の飲食店のように、小さな手間を惜しんで生産性を上げることは、本当の意味では生産性を上げていないのかもしれません。自分の会社が生産しているものは何か?私たちの会社でも、生産性の名のもとで、少しの手間を惜しんでお客様を不快にさせてしまっているようなことをしていないか、もう一度見直してみようと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2025 年 06 月 11 日 12:13
心がこもる仕事
売り手の都合ではなく、お客様のニーズを把握し、それに応じて対応していくことが、顧客志向のマーケティングの基本と言われていますが、お客様のニーズを理解するということは、言葉でいう以上に難しいことだと思います。
例えば「食事」というニーズでも、さっと済ませたいと思うニーズもあれば、家族でゆっくり過ごしたいというニーズの時もある。友人との食事か、ビジネスでの食事か、一緒に行く人によってもニーズは違います。
また、例えば、空港を利用する時なども、仕事で利用する時と、休みの日に遊びで利用する時では、空港に対して求めるサービスが違います。年齢、性別、老若男女といろんなお客様がいますが、その一人のお客様の中にもいろいろなニーズがある。お客様のニーズを理解するというのは、理論で言われるほど簡単なことではないのかもしれません。
お客様として企業のサービスを利用する時は、「もっと、気を利かせてほしい」とイライラすることはたくさんあります。しかし、サービスを提供する側にたってみれば、会社から言われたことをするのが仕事だと考えるスタッフもいるでしょう。「自分の業務、自分がやること」に目が向くとお客様のニーズには気が及ばない。
お客様が「急いでほしい」と焦っている時に、マニュアル通りにゆっくりと対応をされたり、「今日は家族でゆっくり話をしながら食事をしたい」と思って食事をしにきたのに、話をさえぎるように、勝手に料理の説明をしてしまう。お客様の不満はこんなところから生まれていきます。こうしたことは「小さな不満」ですから、お客様もあえて声に出しませんが、つもり重なれば「この店はもう利用しない」と思う人もいるはず。スタッフがお客様に目を向けているかどうかは、お店の業績にもつながっていくことなのかもしれません。
逆に、同じ状況であっても、お客様に気遣いができる人もいます。時計を気にしているお客様を見つけて、「お急ぎですか?」と声をかけてくれるホテルのフロント。グラスに入っている水の「なくなり加減」を常に観察し、お客様から声をかけられる前に、グラスに水を注ぎにいこうとするレストランのスタッフ。サービス業だけでなく、お客様のことに目を向け、相手の気持ちを察した行動する人は、いろんな業界にいます。
こうした人たちの仕事には、その人の「心」を感じます。ただ、決められた仕事を決められた通りにしている人か、お客様に喜んでほしい、いい仕事をして役立とうと思いながらやっているか。心の姿勢は、小さなところに現れていくものなのかもしれません。
「心」がない仕事と「心」をこめる仕事は、作業の内容や見た目はそんなに変わらないのかもしれませんが、相手の心に与える影響は大きいはず。どちらの心で仕事をしていくか。もし、自分がお客様だったら、どちらで買い物をしたいか。答えは明白です。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 06 月 03 日 17:21
体験に勝る気づきはない
過去を見て考えるのではなく、未来のありたい姿から今を考えていくことが大事だと言われていますが、確かに自分たちの目標やありたい姿を明確になると、現状の課題も見え、やるべきことが見えてきます。組織のありたい姿、サービスのありたい姿。抽象的でぼんやりしていたものが明確になれば、全員で目指していけます。
自分たちより優れた組織や相手を見つけ、そこを基準にして近づけるために見学に行くことがベンチマークですが、実際に体験すると気づきが生まれます。例えば、リッツカールトン・ホテルのように、お客様を感動させるおもてなしに近づきたいと思ったら、実際にホテルに宿泊し体験をしてみる。社員が自律的に働く組織が目標ならば、そうした組織を訪問し体験する。本でも会社の業績や規模、事業内容などはわかりますが、社風やおもてなしのレベルなどは、実際に行って、自分自身で感じてみないとわかりません。
以前、自社の経営に悩んでおられた経営者が、社員がいきいきと働く組織の見学会に参加し、自分の目の前で、いきいきと自律的に働く社員のレベルに感動し、そこから、その会社が目標になり、そして経営の方向を変え、業績を回復させた方がおられましたが、比較するものや目標が定まってくると、行動がはっきりしていきます。
顧客に対する「接客」に関しても同じかもしません。一流に触れてみると自分たちとの差がわかります。私は、以前、おもてなしレベルが高いある有名な高級ホテルを知り、その接客を体験したいと、家族で食事にいったことがあります。しかし、妻も子供も高級店の雰囲気になじめず、礼儀正しいスタッフに少し緊張していました。すると、そんな私たちの雰囲気を感じたスタッフが、何かを察したのか、それ以降のサービスから、その人はもちろん、他のすべてのスタッフが一緒になって、私たちを楽しませようと、方言を交えたフレンドリーな言葉で接客をしてくれるようになりました。お客様本位で、かつ臨機応変な対応。これが一流の接客なのかと感動したことがあります。自分自身で顧客のニーズを察し、自分自身で解決策を考える。上司に伺いを立てずに。顧客にとっても社員にとっても気持ちがいい。これが接客の理想だと感動し、それ以来、これが自分の目標、基準になりました。
自分たちの日常の中だけにいると、それが普通になっていきます。しかし、一歩出て一流のサービス、一流の組織など、目指したいものに触れると、自分自身の視座や目標が高くなっていきます。体験しないとわからないことは意外と多いと思います。「ありたい姿」を明確にするためにも、またそれを全員で共有するためにも、やはり、自社の外側を体験していくことは重要なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2025 年 05 月 28 日 11:11
仕事を楽しむ人
これまで、いろいろな会社を見てきましたが、成長し続ける会社は、やはり、社員の人たちが仕事を楽しいと思って働いておられます。楽しいというのは前向きな感情。楽しいから、自分で仕事をよりよくしようとするし、楽しいから勝手に挑戦する。チャレンジすると能力も向上するし、心も向上する。しかし、いい会社で働いている人は楽しそうだということはわかっても、なぜ、仕事がそんなに楽しいのかがわからない。そんな声も聞きます。
楽しく働く方法はわかりませんが、つまらなそうに働いている人にも共通点を感じます。例えば、言われたことだけをやる。自分から仕事はしない。やったらやりっぱなし、振り返りも改善もしない。心を無にしてただ会議に参加する。発言しない。誰かが楽しくしていると待っている。大学の授業もアルバイトもそうかもしれませんが、心も込めず、ロボットのように働くと、絶対に楽しくならないということは、誰もがわかっていることではないでしょうか。
仕事を面白くする方法は、その反対の方向にあるような気がします。言われたことだけでなく、言われたこと以上をやる。仕事の目的を考え、工夫改善し、心をこめる。目標を自分でつくり、自分で挑戦し、やった後に自分自身で反省する。
仕事に「楽しい」「楽しくない」という色分けがあるのではなく、どんな仕事でも楽しくしようとすれば楽しくなるし、つまらなくすることもできる。自分次第でどうにでもできるのが仕事。どんな単調作業でも、ぐっと心を込めれば別のような仕事になります。
「〇〇が楽しい。〇〇を楽しむ。」似たような言葉ですが、少し意味が違います。「楽しい」というのは受動的。この「楽しい」は、周りや人の状況に振り回されることがあります。それに比べて、「楽しむ」は能動的。自分でコントロールしようとしている言葉。自分が「楽しむ」から、自分で「楽しい」ということが作り出せるのでしょう。仕事を楽しむか、楽しい状況を待っているか。選ぶのはそれぞれです。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 05 月 08 日 14:06
GW とウェルビーイング
経済的、物質的な豊かさを追うのではなく、精神的、心の豊かさを追う。ここ数年で「ウェルビーイング」という概念が注目されるようになりました。どれだけ経済的に豊かな都市に暮らしていても、何か満たされない、不幸だとかいう人はいますし、たとえ経済的に貧しい村に暮らしていたとしても、自然を楽しみ、仲間と楽しく過ごしている人もいる。物質的な豊かさが幸せにつながらないのはひとつの事実かもしれません。
企業においても、働く人のウェルビーイング向上が注目されるようになってきましたが、心が満たされているかどうかはどれだけいっても主観的なものであって、周囲がどれだけ「良い会社に勤めている」と言ったとしても、あなたの会社は高い給料が出ているとデータで示されたとしても、その人がそう思わなければ幸せではない。心が満たされているかは本人のとらえ方。ウェルビーイングというのはなかなか難しい問題です。
そんな時、ゴールデンウイークが終わって会社に行きたくない、休み明けに退職者が増えるというようなニュースが目に入ってきました。長期の休暇があって、好きなところに行けるお金もあり、十分にリフレッシュし、戻れる会社も、活躍できる場所もある。客観的に見ると幸せと思える状況にあるはずなのに、休みが明けて働くことになると仕事が憂鬱だ、行きたくないと思ってしまう。どれだけ経済的に豊かであったとしても、それに感謝する気持ちがなければ、決して心は満たされないのかもしれません。
会社が社員のために働く環境を整えたり、良い制度をつくることは大事なことなのでしょう。ただ、それをどうとらえるかはその人次第。幸せかどうかは、幸せを受け止める心の問題だと言われますが、感謝できる人がいちばん幸せなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 04 月 21 日 17:32
比べることの良い面、悪い面
それぞれの会社に新入社員が入ってきています。研修が終わって、これからいろいろな現場で仕事がスタートすると思いますが、仕事をやり始めると、どうしても、できることやできないことの差が生まれてきます。そういう事実がみえてくると、つい他人と比べてしまうことがあります。良くできる人と比べて、なぜ自分は出来ないのだろかと劣等感を感じたり、結果を比較されるとプレッシャーにもなる。なぜ、自分だけがこうなのかと自分の能力を疑ったり、不安も生まれます。それ以外にも、環境や条件を比較して、なぜ、あの人だけ特別扱いなのかと負の感情が生まれたりと、他人との比較はよくないことが起こりがちです。これは新人でなくても、誰でも人と比べることで幸せから遠のいていくことは多い。だからこそ、昔のから、幸せになるには人と比べてはいけないと言われます。
しかし、自分を人と比べることは良い面もあります。頑張る仲間を知ることで、自分の意識の低さに気づく。一生懸命に仕事をする同僚の姿を見て、自分ももっと頑張ろうとやる気がわくこともある。他人と比較することが成長の動機になることがあります。また、他人と接し比べる中で違う価値観があることに気づき、視野が広がる。うまくいっている人のやり方と自分のやり方を比較すれば、自分を成長させることもできます。最近は、過度なプレッシャーが負荷になるからと、個人の業績評価を廃止するという会社もあると聞きますが、ライバルを意識することや、他人と比較して仕事をすることは全てが悪いことではないはず。ただ、やはり、いつも他人のことばかりを気にしていては、自分が正しくみえなくなるのは事実かもしれません。確かに人と比較すれば、できていないことや能力の差が目につくかもしれませんが、過去の自分と比べると、成長していること、できるようなっていることも多いはず。一流のアスリートは常に自分を振り返り、自分を向上させていますが、他人でなく、過去の自分と今の自分という成長の視点で見ている人は、劣等感も優越感もなく平常心で仕事ができていそうです。
比較には、人と競い合う、切磋琢磨しながら人間的に成長できるという面もあれば、間違うと不満や自己肯定感を下げてしまう悪い面もある。比較には両面あるということを理解すること、その人自身が比較をどう受けとめているかが、大事なのかもしれません。新人や若手の育成が難しい時代と言われていますが、良い比較、いい成長をさせてあげたいですね。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2025 年 04 月 02 日 15:01
やり方とあり方
最近、アスリートがよく「心のあり方」のことを言われます。心の質がプレイ(行動)の質につながり、結果の質にも影響する。個人スポーツの中でもチームスポーツの中でも、自分は何のためにこのスポーツに挑むのか、どうありたいのか等のあり方を深めたり、心が乱れないようにセルフマネジメントをしたり、競技の「やり方」(行動)の探求以上に、「あり方」(心)のマネジメントに取り組むアスリートが増えていると聞きます。確かに、緊張で本調子が出せない人もいれば、まるで遊びのように楽しみ、平常心で良い結果を出すアスリートもいます。スポーツの世界では心の状態がパフォーマンスに影響するというのは、最早当たり前になっているようです。
ただ、ビジネスの世界では、これまで、あまり「あり方」や「心」に目が向けられることは少なかったかもしれません。問われるのは、やるべきことをやったか、どのような結果を出したか。仕事に、どのような心で取り組んでいるかは、あまりクローズアップされなかったように思います。
しかし、「あり方」(心)が、仕事(行動)に影響を与えるのは実感としてもわかります。例えばモノをつくる仕事の場合でも、「いい仕事で社会に貢献したい」「ずっと残る良いものを作りたい」という思いをもって仕事をする人と、「言われたから、言われた通りにやっている」という人では、細部の出来栄えが違うはずです。営業でも、自分の成績を上げようと自分中心に営業する人と「お客様に喜んでほしい」と「人に役立つことこそが営業だ」というように思っている人では、気配りやご説明の細部が違ってきます。
また、私生活に不安を抱えている時には仕事に身が入らないし、組織の中で孤立を感じている時に、いい仕事をしようという気にはならない。仕事に意義を感じている時や、家庭でも会社でも人間関係に不安がない時は、確かにいい仕事ができます。当たり前のことですが、心と行動はつながっています。
ただ仕事でもスポーツでも、結果がでるとやる気になったり、失敗したことで落ち込んだり、周囲の影響で心は変化しがちです。若い人はより、そうなるかもしれません。どのような状況においても揺らがない心を保つために、アスリートたちは、自分自身でその競技をする目的を明確にしたり、自分の心が前向きになるような言葉を自分に向けて話しかけたり、あえて仲間を応援することで自分自身の心を高めようとしているようですが、ビジネスにおいても、そうしたしなやかで強い心を保つ努力が大切なのかもしれません。
その上で、チーム全体でメンバーの心に配慮する。確かにいい会社、いいチームは人間関係が良好だと思います。お互いに心の状態に気を配り、一人でも不安な顔をしているメンバーがいれば、上司や仲間が自然と声をかけるような優しい風土がある。仕事だから、やるべきこと(行動)をやることは当然ですが、あり方(心)が伴って「いい仕事」ができるとすれば、やはり、「あり方」にも目を向けていくことがますます大事になっているのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 03 月 18 日 15:33
「お客様のため」は正しいか
顧客本位、お客様起点という言葉は、昔からよく耳にします。しかし、本当に「お客様本位」とは、どのようなことを指すのでしょうか。
お客様の言うことを何でも聞く、お客様に迎合する。これが「顧客本位」かと言えば、決してそうではありません。たとえば、お客様から「こうしてほしい」と依頼されたとしても、それがお客様のためにならないと判断した場合は、たとえ売上につながるとしても、代替案を提案したり、場合によってはお断りすることも必要です。本当に「お客様本位」の仕事とは、後者のような対応ではないでしょうか。
確かに、お客様の要望をすべて聞き入れれば、その場では喜ばれ、売上も上がるかもしれません。しかし、それが本当に相手にとって良いことなのか、その人の将来にとってプラスになるのかを考えることが大切です。人間関係においても、一時的に嫌われることがあったとしても、相手のためを思い正直に意見を伝えてくれる人の方が信頼できるものです。同じように、売上のために何でも聞く会社よりも、信念を持って真に顧客のために行動する会社の方が、最終的には信頼されるはずです。
「お客様のために」という言葉も、よく使われます。しかし、その活動が本当にお客様の役に立っているのか、ズレてしまっていないかを見極めることが重要です。
たとえば、「接客は丁寧であるべき」「しっかり時間をかけてお迎えすることが大事だ」と考え、昔から丁寧な接客を徹底しているお店があるとします。かつてはそれが喜ばれたかもしれません。しかし、現在では、丁寧な接客を好む人もいれば、スピードやスムーズさを求める人もいます。結果として、「お客様のため」と思っていた接客が、実際には喜ばれていないということが起こり得るのです。
「お客様のため」という考えは、多くの場合、過去の経験から生まれた基準に基づいています。そして、一度「こうするべき」と決めてしまうと、いつの間にか「それをやること」自体が目的となり、本来の「お客様に喜ばれることをしよう」という思いが薄れてしまうことがあります。
気づかないうちに「過去のやり方」や「こちらの都合」を押し付けてしまっている――こうしたことは、どの企業にも起こり得るのではないでしょうか。
大切なのは、「お客様のために」ではなく、「お客様の立場に立つ」こと。過去のやり方にとらわれず、「今、目の前にいるお客様が本当に望んでいることは何か」「何を求めているのか」を理解する。そして、その人にとって本当に役立つことを提供する。今求められているのは、「お客様のために」という想いを大切にしつつも、お客様の視点に立ち、真に必要とされる価値を提供する姿勢なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2025 年 03 月 05 日 13:30
利益の少ない仕事
仕事をしていく時、生産性や効率は重要なものだと言われています。無駄をなくす。利益の高い仕事に集中する。時間を効率的に使う。確かに理屈はその通りで、これができないと儲かりません。ただ、本当に何が無駄なのか。そんなことを考ええる機会がありました。
「利益の少ない仕事にも心をこめる」。これはカレーチェーン店「COCO壱番屋」の創業者、宗次徳二さんが創業から商売の心構えとして大切にされてきた言葉です。
壱番屋の創業は夫婦で開業した小さな喫茶店。ただそこは裏通りで誰も気づかない場所、商売としては難しい立地でした。そのような中でもお客様がわざわざ来てくださる。それが本当にうれしく、お客様に強く感謝するようなり、そこからお客様第一の商いが生まれました。そんな商売の中で、掃除や挨拶の大切さに気づかれ実践されるようになったそうです。
店前の掃除はもちろん、近所も掃除する。無駄と言われても続けられました。その内に、宗次さんの真摯な姿勢が地域の人にだんだん伝わり、お店は繁盛していったそうです。「もちろん、掃除をしているから良いと来店する人は1%もいない。ただその1%のファンが1月1人でも来てくれたら1年で12人のファンができる。それがいつか売上の一部になる」利益の少ない仕事も心をこめてきたことが壱番屋の原点だと話してくださいました。
効率や生産性は大事。ただそこばかりだと、儲かる仕事ばかりに目が向いてしまいます。そのうえ、忙しくなればなるほど手間がかかる仕事は疎かにしがち。確かにそれの方が儲かるのかもしれません。しかし、自分がお客様の側にいるときは、そう思わない。面倒な相談にも親身になって応えてくれたり、近所の掃除など、儲けにもならないことを一生懸命にやっているお店の方が心に残ります。ファンが増えるのはどちらかと考えると、本当に何が効率なのかと考えてしまいます。利益の少ない仕事にも心をこめる。長い目でみれば商売では大事なことなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 素晴らしい組織風土づくり
2025 年 02 月 26 日 10:49
「負荷」が成長をうながす
筋肉を鍛える時は身体に負荷を与えていきますが、仕事で成長するためにも、やはり負荷が必要だと思います。「自分にできるだろうか?」「無理かもしれない」ということに挑戦していく中で、能力が磨かれたり、視野が広がったりすることは、誰もが経験しています。だからこそ、若いうちは無理をしてもいい、仕事を一生懸命した方がいい、苦労は買ってでもしなさいと歳を取った人は言いたくなってしまいます。
しかし最近は、あまり無理をさせるとすぐに辞めてしまうからと、新人になるべく負荷を与えないようにする会社も多いと聞きます。ゆっくりと育てる方針でも成長してくれると思いますが、負荷がない仕事ばかりでは、筋肉は鍛えられません。視野も広がりません。結果、同じ仕事の繰り返しになってしまい、仕事がつまらなくなります。成長の実感がないまま3年目を迎えるころに会社を辞めるということも多々あるようです。
嫌なら辞めて違う会社にすぐに変わることがあたりまえの時代ですから、ひとつの会社にずっといる必要はないのでしょうが、「石の上にも三年」というように、自分の経験からも、3年を過ぎるころから自信がつき、見える景色も変わっていきます。仕事が好きになっていくのは3年目あたりではないでしょうか。
新入をどのように育成していくか。新人たちではなく、私たちに問われていることのように思います。若手が自ら自分で厳しい道、努力の道を進もうと思い、挑戦していくことがいちばんですが、それには、それをいかに支えるか。「失敗してもいいからやってみたら」と支えてくれる上司や仲間の存在、いきいきと働きチャレンジする先輩の後ろ姿など、新人が成長していく会社をみていると、やはり若い人たちの勇気が掻き立てられ、自然に未知の領域に踏み込んでみたいと思えるような環境があります。
今の人は価値観が違うという声もあります。私も若い人の価値観の違いに驚くことがありますが、時代が違えば考え方も違うのは当然。お互いに違いを認めながらも、せっかく入社してくれた若い人たちが、自ら負荷に挑み成長し、幸せになってくれるように導いてあげたいものですね。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2025 年 02 月 10 日 16:28
現状維持は衰退
昔から、組織は環境に合わせて変化していかなければならないと言われます。確かに成長している企業は常に変化しています。過去のやり方に囚われていてはいつの間にか時代に合わなくなる。だから新しいことに挑戦しよう。この話は、誰もが頭ではわかっていることだと思います。
しかし、これがなかなか難しい。例えば、過去のやり方に固守している古い業界に、時代に合わせた新しいやり方で参入した企業が成長する。そして、その成功に追随するように古い企業がやり方を変えていく。こうしたことは、どの業界でも起こっていますが、「現状維持ではいけない」と思いながらも、自分達のやり方を自分達自身で変えていくことは、頭で考える以上に難しいことなのかもしれません。
確かに、自分の生活を考えても、慣れ親しんだことを急にやめたり、変えていくことは意外とできません。変えたほうがいいと思っても、変えることによって何が起こるかわからない不安、それを実現するための新たな努力に対するリスクなどを考えてしまうと、このままでいいと思ってしまうのが人間の性なのでしょうか。例えば、飽和状態の携帯電話業界。「他社からの乗り換え」を訴求していますが、変える手続きが面倒、今のままでいいというユーザーが多くてなかなか思う通りにいかないそうです。確かに、現状維持には、余計なトラブルも、無駄なリスクが生じません。現状維持の魅力やメリットはそこにあります。
ただ、ビジネスの場合、自分たちは現状維持でよくても、顧客も競争相手も、周りはどんどん変化していきます。現状に甘んじているといずれ時代についていけなくなるのは明白。現状維持は衰退の道です。
では、こうした現状維持の心理をどうすれば打破していけるのでしょうか。どうすれば、自分のやり方を自分で変えていけるでしょうか。
そもそも、どんなやり方をしていようと、その中にどっぷりつかっている時は、自分達のやり方が古くなっていることに気づかないのかもしれません。「別に問題がない」と思っている時に変えようという気がおきません。とすれば、まずは、自分達のやり方が、もしかすると現状維持になっているのではないかと疑ってみることがスタートなのかもしれません。
「今まではこうだったけど、この選択は本当に最適なのか?」。過去の成功体験にばかり依存していないかと自分を疑ってみたり、自問自答する時間をあえて持つ。現状維持の打破には、変えること、変わることのメリットを体験したり、リスクの小さな挑戦からやってみるなど他にもいろいろあると思いますが、「変わっていない自分を知ること」がいちばん大事な気がします。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 02 月 05 日 11:35
結果を出し続ける人
結果が大事か、プロセスが大事かという問いがあります。どちらが大事かと優劣はつけられないかと思いますが、プロの世界は結果がすべて。結果を出せないと生き残っていくことはできません。しかし、だからといって結果ばかりを気にしすぎると、手っ取り早い成果を求めてしまい、プロセスを疎かにするということもある。かといって、結果なんて関係ない、努力が大事だといって結果に目を向けないのもプロではありません。また、結果は嘘をつくこともあります。例え準備不足でも良い結果が出てしまう時もある。結果ばかりをみていると慢心が生まれ、努力しなくなることもある。結果ばかりに一喜一憂しているだけでは、結果を出し続けることはできなくなるのかもしれません。
先日、田舎の営業所に在籍しながら、毎年のように全国上位の成績をあげる、ある優績営業スタッフのお話を伺う機会がありました。訪問を嫌う顧客が多くなるうえ、顧客数が激しい過疎地での活動はかなり難しいはず。昔の営業のように、ただ訪問件数を重ねたり、「お願い」で買ってくれる時代ではありません。そんな時代で、この営業スタッフは、とにかくお客様の側にたって、その人にふさわしい商品を考えることを一番に考え続けることを大事にした活動を続けられます。無理に売りつければ嫌われるだけ。お客様が必要だと思ってもらえるなら買ってくださるはず。だからこそ、お客様の側に立つ営業であろう。その信念を貫き、ベテランになった今でも、仲間の成功事例や時には新人の成功事例にも耳を傾け、自身のヒアリングの質、お客様に最適な提案の幅を磨き続けておらます。そして、結果が出た月は何が良かったのか、結果が悪かった月は何が悪かったのか。常に自分のプロセスを分析し、修正する。「再現性がある技術」をこそがプロだと言われます。
一流のアスリートほど練習やプロセスを大事にされます。「結果は嘘をつくこともあるが、プロセスは嘘をつかない」というのは、どの業界にも当てはまるのかもしれません。
もしも、今、結果がでないのであれば、プロセスのどこかに問題があるからと考える。逆に、結果が出ている時も、プロセスの何が良かったかを考え次に活かす。結果を出し続けられる人、結果に一喜一憂せず自分を磨き続けられる人が真のプロなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 01 月 07 日 10:29
脱皮と挑戦
新年あけましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬ御高配にあずかり厚く御礼申し上げます。
本年も皆さまのお役に立てるよう、精一杯努力して参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
昨年はお正月の能登大震災から始まり、政治でも経済でも社会でも様々な出来事が起こった一年でした。まさに誰も予測できないVUCAの時代の中にいることを実感します。
そもそもVUCAとは「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を取った言葉ですが、まさに「正解を誰も知らない」あるいは「正解はいくつもある」ということ。とにかくこれまでのやり方が通用しない、従来の延長線上の考え方だけではやっていけない時代であることは間違いありません。
過去のやり方が通用しないのならば、新しいやり方に挑戦していくしかありません。そう考えると、VUCAの時代における大事なマインドはまず「試してみる」、まず「やってみる」こと。小さな実験や仮説検証を繰り返して進んでいく。大きくやろうとせずに小さな実験をしてみて早くに失敗をする。そこから次のやり方を考えて、次に進む。失敗をしないように慎重になる姿勢より、あえて失敗を求めにいくくらいが丁度良いのかもしれません。
また、正解がわからない時は、一人でやるよりもいろんな人と相談しながらチームでやることの方がうまくいくものです。まったく違う分野の人、異なるバックグラウンドを持つ人と話し合うと、今までにない気づきが生まれることがありますが、例えば、営業だけの会議に製造の人が入って話し合うなど、職種を超えて智恵を出し合って仕事をしていくことも大事なことなのだと思います。
ただ、考えてみれば戦後の焼け野原の時代だって誰も先がわからない。誰もやらなかった新しい事業を立ち上げてきた先人もいます。わからないなら、やってみる。シンプルな言葉ですが、挑戦をあえて楽しんでいくのがいちばん大事なマインドかもしれません。
そういえば、今年は「巳年」ですが、蛇は脱皮をすることから巳年は「復活と再生」の年でもあるそうです。過去のやり方を脱皮していく一年なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2024 年 11 月 19 日 16:39
競い合うチーム、助け合うチーム
先日、全国でもトップクラスの成績を挙げる営業スタッフを、何年も続けて輩出する、ある組織の地方の営業チームを取材させていただきました。都心部でもなく、なぜ、そんなに優秀な人が生まれるのかと伺っていくと、その理由はこのチームが昔から大切にしてきた文化が影響しているようでした。
そのチーム(支店)には、昔から「お互いを助け合う精神」があって、40名以上いる営業メンバーは常にお互いの状況を開示し合い、もし、メンバーの中に困っている仲間がいれば、エリアを超えて助け合っていきます。成績が芳しくない仲間がいると聞けば、リーダーやトレーナーが声をかけ、すぐに助けにいく。入ったばかりの新人には優秀スタッフがべったりと張り付き、惜しみなくノウハウを教える。そんな日常の中で、常に成績の良い人が育ち続け、何年にもわたってチーム全体で好業績を出し続けているということでした。昔は、営業は個人で頑張るもの。社内であってもお互いがライバル。仲間にもノウハウを隠す人もいました。自分の成績だけが一番の関心事で他人のことなど関係ないという空気もありました。しかし、世の中がこれだけ変化していく時代の中では、個人主義だけでは全体の成績も出せず、お互いが良い情報を共有する「助け合うチーム」でなければ良い成果が出なくなっているのかもしれません。
「助け合うチーム」は社員のやる気にも影響します。日本能率協会が実施した「働く人の満足度やモチベーション調査」でも、所属しているチームの雰囲気が働く人のやる気に影響することが報告されています。その調査で「現在所属しているチームの雰囲気に満足していますか」という質問で「満足」と回答されたビジネスマンは約半数強。満足の理由として一番多く上がったのが、「困ったときに助け合いができているから」という回答(40%)でした。日本人が求める理想のチームは「困った時に助け合うチーム」そして「良好な人間関係ができているチーム」であると結論づけていました。
しかし、そうした助け合うチームはどうすれば出来るのか。先ほど紹介したチームの方に伺うと、その会社には、昔から「仲間は絶対に見捨てない」という精神が脈々と流れていると感じておられました。昔、自分が苦しかった時に先輩が助けてくれた。その喜びを知っているからこそ後輩に伝えていく。そんなDNAが「助け合い」の風土を作っているようです。
「大家族主義」「チーム営業」など言葉は違えど、いい組織、いい会社はやはり仲間を大切にされています。農耕民族は競い合うことより、助け合ってきましたが、「助け合い」は、日本人にいちばん合っているのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 素晴らしい組織風土づくり
2024 年 10 月 16 日 15:42
追いかける仕事、追いかけられる仕事
仕事というのは、本当に不思議なもので、同じ仕事をしていても、その時々で感じ方が違ってきます。山のように仕事が舞い込んで、しんどいと思う時もあれば、山のような仕事を前にやりがいを感じる時もあります。つまらないと思っていた仕事が、意味や意義を感じるようになり、突然、面白くなることもあります。
「こなさなければ」「やらなければ」と、やることに「追いかけられている」と辛い時間になる仕事も、「こうやっていこう」「もっとよくしていこう」と、創意工夫し、「やることを追いかけて」仕事をしていると、楽しくなる。一流職人や、プロと言われる人の仕事をみていても、一流と言われる人ほど、「もっとよくできないか」「もっといい方法はないか」と探求心を持って仕事をされています。正解もなく、ゴールもないから、どこまでも考え続けてしまう。そこが楽しいから、やり続ける。
追いかけられれば、義務感・負担感に、追いかけていけば、夢や使命感。本当に自分の心次第です。
仕事を追いかけるか、追いかけられるか。面白くするか、つまらないままにするか。
どちらも自分で選べます。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2024 年 10 月 08 日 17:53
優秀営業スタッフに学ぶ「お客様からの信頼」
以前、ある方から、お客様から信頼され、業績を上げ続ける営業スタッフを業界を超えて調査した時に、いくつかの共通点があったと聞きました。その共通点は、常にお客様の立場にたち、お客様のことを良く理解しようとする人、それと、お客様の小さなお困りごとや不満を聞き、解決しようとする人、そして、そのお客様の立場にたって、お客様に合わせた提案をする人だということです。
成績の良い営業、売れる営業と聞くと、お客様に買いたいという気持ちにさせるような巧みな話術だとか、目標達成に貪欲な姿勢などを想像します。確かに「売れる営業」はそんな姿勢が求められるのかもしれませんが、「売れ続ける営業」は少し違うようです。もちろん、そうした話術も数字へのこだわりもある。しかし、それ以上にお客様の立場になって、お客様と一緒になってお客様の幸せを考え続ける。一見すると不効率にみえるような活動を一生懸命に行っている人が、売れ続けている営業のようです。
顧客満足度の高い、ある自動車販売会社の中で、長年トップの成績を誇る営業スタッフのお話を聞いたことがあります。その人は、例えば、新規のお客様と商談中で、今、買おうとされている瞬間であっても、もし、既存のお客様から、トラブルがあって助けてほしいと連絡があれば、その商談を中断して、すぐに助けにいくそうです。商談を中止にされたお客様は、さぞ怒られるのではないか思ってしまいますが、逆に、その人のどんな時もお客様を大事にする姿勢に感銘し、その人から買いたいと思われるそうです。自分が販売したお客様が心配になる。その人のためにできることをしたい。どうせ買うのなら、そんな姿勢の営業スタッフから買いたいと思うのは、むしろ当然のことかもしれません。
自分の成績や自社の利益のことよりも、相手の立場になって考える。お客様にとっては、これほど信頼できる人はいません。
「目の前のお客様が大事だ、しばらく買わないお客様なんかほっておけ。」と、業績を上げろ、業績を上げろと言われる時代もありましたが、今そんなことをしていては、大事なお客様から嫌われて、次の売上を失ってしまいます。売れ続けるには「売った後」が大事な時代です。だから売れる。
実際、先ほど紹介した営業スタッフは、「あなたから買いたい」というお客様が増え続けるので、ヒット商品が出ようが出まいが、不況であろうがなかろうが関係なく、どんな時でも営業成績が落ちず、ずっと売れ続けているそうです。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2024 年 10 月 01 日 10:27
職場の人間関係と生産性
徳島県に西精工という会社があります。この会社は自動車部品のナットを作る製造業ですが、働く人の9割近くが、社内のES調査に対して「この会社で働いていて幸せを感じている」と答えるほど、社員エンゲージメントが高い会社です。
こうした職場になった背景には、理念の共有などいろいろな取り組みがあるようですが、特に大事にしてこられたのが職場の風土づくりでした。働く仲間同士が良い人間関係を築けていないと良い仕事はできない。言われてみれば当たり前のようなことですが、良い人間関係をつくっていくことはなかなか難しいことです。
論理的に考えれば、10の力を持っている人同士が仕事をすると、5の力の人同士のチームより大きな仕事ができるという理屈になります。でも、いくら10の力を持っていた2人でも、その間の人間関係が悪く、いがみあっていては仕事はマイナス10になることもあります。逆に、例え5の力のチームでも人間関係が良ければ協力し合って仕事をすればプラス10が生まれることもある。10の力のチームより、5のチームの方がいい仕事をすることがあるというのが人間です。
また、もし10の力を持っていた人だとしても、家族の中に不安があったり、悩みを抱えていれば、仕事の中で力を存分に発揮できません。10の力が半減する時もある。そんな時にチームメンバーが声をかけ、不安を理解してくれるか。人間関係は仕事の生産性にも大きく影響します。昔は飲み会やプライベートの交流という、いわれる仕事を超えた付き合いで、お互いがわかり合うことができましたが、最近はなかなかそんな時間もありません。人間関係が希薄になってきています。
西精工では、少しでも職場の仲間同士がわかり合おうと、毎朝1時間近くもかけて朝礼を行っています。この朝礼は、単なる報告や情報伝達の場ではなく、理念や価値観を題材に、お互いが仕事に対して、どのような気持ちで取り組んでいるか、職場のメンバー同士でじっくりと対話をする時間です。この1時間は、一見すると「無駄な時間」のようにも思えますが、この朝礼が職場の中の人間関係が良くする大切な時間になっているようです。お互いの理解・信頼が高まる。結果として助け合いや協力の質が高まる。結果的に仕事の生産性も上がっていく。この朝礼は15年も続けておられます。
何十年も働く時間は、いつも順風満帆な人生ではなく、家族のことで悩んだり、人生で悩むこともある。そんな時、人間関係が良好で、プライベートなことでもフランクに相談できるような人が傍にいてくれる。働く人にとってこれほど安心なことはないかもしれません。
よい人間関係と生産性。働く人にとっても、会社にとっても、これからの時代において大事なことではないでしょうか。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 いきいき働くための仕事の姿勢
2024 年 09 月 25 日 10:48
やらされている仕事からの脱却
「やらされている」「させられている」という感覚のまま何かをやることは、大きなストレスです。させられている訳ですから、やっていることに納得していない。しかし、やらなければ怒られる。我慢しながらも愚痴を言いながらも仕事をする。こんな状態では、「さっさとかたずけよう」という気持ちが先に来てしまい、この業務をより良くしようというような前向きな気持ちはなかなか起こりません。
企業の中での「研修」でも、こんな「やらさせている」という気持ちを感じることがあります。本当は参加したくない、面倒くさい。何で今さらこんなことを学ばなくてはいけないのか。会場の雰囲気から参加者の気持ちが伝わってくることがあります。学校の授業もそうですが、そんな気持ちで参加していては、「こなす」だけになって、身につく訳がありません。だから、講師は、何のためにやるのか、なぜ、この研修が大切なのかを伝えようとしますが、そもそも本人が「学びたい」「参加したい」と思っていなければ、どんな研修も無駄な時間になってしまいます。
日々の業務でも、「やらされている」「させられている」という気持ちになることがあります。上司の言うことを聞くことが当たり前、ルールに従うことが当たり前。自分が納得していなくてもやる。それが会社員。昭和の時代は、こうした姿勢が仕事のスタンダードだったのかもしれません。ただ、そんな気持ちでは、「こなす」仕事になり、お客様のためにもっと良い対応をしようとか、より良いものを生み出す仕事にはなりません。
では、どうすれば、「やらされている」「させられている」という気持ちを消すことができるのでしょうか。個々の気持ちの問題ですから外からどうすることもできない。個々が「自分が本当にやりたいこと」を考えるしかありません。先ほどの研修でいえば、本当に参加したくないと思えば、参加しない。意味がないと思えば、自分にとって意味ある研修に参加する。もし、義務感で参加したとしても、そこに参加する以上、自分で意味を見つけようとする。「やりたくない」ことを「やりたい」ことに変えるのはその人にしかできません。
最近、組織のビジョンやパーパスを明確にしようとする企業が増えてきていますが、いくら企業が「ありたい姿」を示したとしても、それが、社員自身の「ありたい姿」が重なっていなければ、すべては他人事。その人が自分もそうありたい、そこを目指したいと思えなければ、仕事はいつまでも「やらされている」ことになってしまいそうです。企業の中でも、こうしたことを考える時間や場所をつくる企業が増えてきているようですが、自分の人生で本当にやりたいこと、自分が行きたい場所、自分がありたい自分は何か。個人の「やりたいこと」が明確になってこそ、本当のモチベーションが生まれるような気がします。
余談ですが、研修の前に、やらされ感をなくす方法を話すことがあります。その方法は、早めに諦める。嫌だ嫌だと思いながら終了時間まで我慢するか、「ここまで来た以上、しょうがない」と受け入れて、少しでもいい時間にしようと自分自身を学ぶモードに切り替えるか。天候や環境など、自分で変えられないものは変えられないと受け入れることを「肯定的な諦め」と呼ぶそうですが、嫌な状況でも、気持ちだけは自分でつくることができます。せっかくの研修の時間とどう過ごすか。会社も仕事も同じかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2024 年 09 月 11 日 15:58
仕事の面白さ
先日、ある会社の若い年次の営業スタッフに、仕事のやりがいや面白さについてインタビューする機会がありました。今年から急に成績が上がってきたある若手は、やはり自分が上位にいることやそれに伴って報酬が増えていくことが、今いちばん楽しいと感じていると話をしてくれました。確かに自分の頑張りが数字に出てくると、達成感が生まれますし、仕事は面白くなってきます。
しかし、だんだんと数字の面白さだけではなく、仕事の中身に喜びが移っていく人もいます。ある年次の若手は、自分の営業の中で、思いがけずお客様から感謝の言葉をかけてもらったことが転機になり、もっと役立っていきたいと、面白さを語っていました。
数字が達成した時などは確かに嬉しい。周りも褒めてくれます。しかし、何度も繰り返していくとそれが当たり前になって喜びが少なくなったり、続けていくうちに数字が苦しくなることもある。そんな時に、違う喜びに転換していけるかどうか。後者の若手のように、「この仕事で自分が人に役に立てている」というような喜びに出会うと、また違った意味で仕事は、どんどん面白くなっていきます。
確かに「仕事の面白さ」はひとつではない。「出来ないことが、出来るようになる」というという面白さ、「頑張りに対して報酬がもらえる」という面白さ、自分の頑張りを、「みんなが称賛してくれる」という面白さ。成長と共に面白さも変わっていきます。その中でも本当に仕事が面白いと感じている人の面白さは、「自分の仕事を通して人の役に立つ、感謝される面白さ」ではないでしょうか。頑張ったとしても、なかなか感謝されることもない。しかも、人によって喜ばれる内容は違う。難しいからこそ、やりがいになります。
そもそも仕事に色はついていない。「面白い仕事」や「面白くない仕事」というものはありません。
ようは、自分が面白いと感じているかどうか。もし、仕事が面白くなくなっているとしたら、仕事のせいでも、まわりのせいでもなく、ただ、自分が飽きたり、興味がなくなっているだけ。次のステージにいくタイミングなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2024 年 08 月 20 日 10:31
売ってから始まるおつきあい
先日、自宅のトイレが故障し、その会社に連絡をすると、休みの中でもすぐに駆け付けてくださって助かったことがありました。住宅でも車でも家電でも、使っていると故障したり、不具合が生じてきますが、その時に買ったお店がしっかり対応してくれると本当に助かります。「売った後」に責任をもってくれるお店や企業はやはり、信頼できます。時々様子を見に来てくれたり、手紙をくれたりすれば、なおさら。「次もその店で買おう」という気持ちになります。
一流ブランドのバッグなども、高くても、何かあってもしっかり修理してくれるという安心感があるからこそ、買おうという気持ちになる。自分達の売ったものに誇りと責任を持っている企業ほど、アフターフォローに手を抜かないのかもしれません。
東京都の町田市に、「でんかのヤマグチ」という小さな家電専門店があります。お店の周囲に大型量販店がひしめく環境にあって、この店は「多少高くても家電はヤマグチで買う」というファンをがっちりつかんで成長し続けているお店ですが、やはり、創業時から大切にしてこられたのが「アフターフォロー」です。どんなにお客様が買いたいといっても、無理に商圏は広げず、自分がしっかりとアフターフォローできる範囲に絞り、その中で、家電を販売した後に、様子を伺いに訪問したり、困ったことがあれば、電池一個でも届けにいく徹底ぶり。そんなこまめなアフターフォローが安心感になり、大型量販店がどれだけ安売りをしても、このお店のファンは離れていかないそうです。
昔は、このお店のやり方を見て、「電池一個を届けるなんて不効率だ」「安さの方が大事だ」という声も多かったそうですが、その長い時間の無駄のおかげで強い「顧客エンゲージメント(絆、つながり)」が育まれています。今では安売りの量販店もアフターフォローに目を向ける時代。周囲の声に流されず、お客様の立場にたった商売を続けていくことの大切さを感じます。
売ることが商売ではなく、売ってからが、お客様との本当のおつきあいのスタート。お客様の心の中に「次もこの店で」という気持ちが生まれるには、どんな商売においても、自分が販売した商品に責任を持という姿勢と行動がますます重要になっている気がします。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2024 年 08 月 07 日 17:11
持続可能な顧客サービス
一人の生活者として、いろいろなお店で「お客様サービス」を体験していますが、日本のサービスレベルは向上していることを実感します。SNS等で、お客様の評価が見えるようになったからなのでしょうが、以前なら、接客態度が悪い、商品の質が悪いと文句を言いたくなるようなお店もありましたが、どこを利用しても、不満を感じることが少なくなっているような気がします。
しかし、お客様にサービスを提供する従業員のマインド面で見た時に疑問を感じる部分があります。本当の意味でサービスは向上しているのでしょうか。人の顧客としてお店のサービスを体験してみると、「この店はいい、いいサービスだ」と感じるお店は、やはり、従業員がいきいきと働いています。サービスはしっかりしているのに、従業員がいきいきと働いていないお店と違って、そうしたお店では、従業員が声をかけてくれたり、ちょっとした気遣いをしてくれたり、顧客に楽しんでもらうことを、自分も楽しんでいる気がします。
お店で行うサービスにその人が心の底から楽しんでいるか、義務感でやらなければいけない仕事だと思ってやっているのか。
良いサービスを実現するのは人。日本のサービスはお客様に対しては向上しているのかもしれませんが、従業員のマインドは向上したのででしょうか。
お客様満足を高めるために従業員にサービスを義務付ける。マニュアルにして強制する。確かにそれでサービスは向上したとしても、働く人は楽しくはない。これでは、どんなにお客様が評価をつけようが、従業員が定着はしないし、長く続かないのではないでしょうか。義務的なCSとやらされていると感じる従業員。自由裁量の中での主体的なCSと、それを自分の喜びとする従業員。どちらが持続可能かは言うまでもなく、後者。やはりESの向上なくして持続可能な本当のサービスは生まれないように感じます。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2024 年 07 月 31 日 12:10
手間をおしまない
先日、顧客満足度の高いある住宅会社が行う、お客様に新築物件をお渡しする前の点検活動の様子を映像で拝見しました。お客様にとって人生でいちばん高い買い物。それを建てた責任として、不具合箇所がないか、床についた小さな傷も見逃さまいと、社員が這いつくばって点検をする。お客様に喜んでほしいと、丁寧に点検される姿にこの会社の姿勢が伝わってくるようでした。
こうした手間ひまかける対応を見ていると、顧客満足度日本一のレクサス星が丘のお店のスタッフが、お客様に出すお茶を入れる際に、お茶を蒸らす時間を秒単位で決めたり、車の誘導の際に、運転席から案内が見やすい角度を研究し、マニュアル化されていることを思い出します。
効率化、省力化と向かう世の中で、こうした手間はコストもかかり、逆行することなのかもしれませんが、やはり「手間」をかけることは、必ずお客様の満足につながっていく。飲食店における料理の仕込みもそうかもしれません。開店前の掃除やお店の飾り付けも同じかもしれません。手抜きの仕事に満足は生まれません。お客様のための「手間」は、きっと相手の心に伝わっていく。高い買い物ならなおさらです。
ただ、私たちは仕事に慣れてくると、つい、手間を省こうとしたり、こなすように仕事をしてしまう時があります。慣れるということは良いことである一方、毎日同じことを繰り返していくと、つい、これまで一生懸命やっていたことが面倒になる。自分自身が飽きてしまう。「慣れ」や「飽き」から手抜きが始まります。しかし、お客様はそうした姿勢を見逃さない。せっかく買いものをしても、そこで流れ作業のような対応をされれば、きっと心の中で「もう、この店は来ない」と思われてしまうのではないでしょうか。
あのディズニーランドでは、こんな「慣れ」や「飽き」の気持ちを戒めるために、「毎日が初演」という言葉があるそうです。初めてステージに立つ時に感じた緊張感、全力でやりきろうとする姿勢、お客様に喜ばれた時の感動。確かに、初めての仕事は誰も手抜きをしませんし、手間をかけたことに喜びや手ごたえを感じるもの。ディズニーランドが40年にもわたって顧客を魅了するのは、こうした姿勢の積み重ねかもしれません。
手間を大切にする。手間をおしまない。顧客にとっても働く人にとっても大切な姿勢のような気がします。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上 素晴らしい組織風土づくり
2024 年 07 月 23 日 12:59
「ちょっとした心配り」と顧客満足
買い物をしたり、サービスを利用する時、時々、そのお店の店員さんの思いがけない気配りや心配りに感動することがあります。自分のことを覚えていてくれた。手間のかかることなのに笑顔でやってくれた。困っている時に親切にしてくれた・・・。マニュアルを超えて店員さんの想いから行われる「ちょっとした心配り」。お店のスタッフとお客様の間で交わされる「ちょっとした顧客体験」について考えてみました。
こんな体験は誰でも一度はあると思いますが、ある調査では、こうした「ちょっとした心配り」の体験を1人が1年間で体験する割合は14%だそうです。その調査では、この体験をすると「この店をもう一度利用したい」という再利用意向が、体験しなかった時と比べ47ポイントも上がるという結果が出ているそうです。また、こうした体験をすると「この店を人に薦めたい」という推奨度も28ポイントも向上するそうです。こうした調査は一部ですが、自分の実感としても、「ちょっとした心配り」が顧客満足向上やファンづくりの上で、大きな影響を与えていることがわかります。
その調査にはありませんが、「ちょっとした心配り」は社員の側にも良い影響を与える気がします。「心配り」というのは、相手ことを考え、行動することですが、自分の行為がお客様の笑顔につながったとすれば、「された方」だけでなく「した方」も嬉しくなるはず。「店で決められたサービスを、決められた通りに行う」ことは確かに大事なことであっても、そればかりをやっていると働きがいを感じにくい。しかし、自分が考えて行うこと、そしてそれが誰かの喜びを生み出せることだとすれば、「やりがい」にもなります。「ちょっとした心配り」が増えていけば、顧客も、働く人も、企業にも良い影響が生まれてくるのではないでしょうか。
しかし、考えてみれば、困っている人がいたら助ける。手を貸す・・・そんな「ちょっとした心配り」は日常生活の中で、社会人があたりまえに行うべきこと。仕事の場で気配りが出来ている人は、日常の場でも同じようにしているはずで、「ちょっとした心配り」は、ビジネスだからやる、顧客満足に有益だからやるというように考えて行うことではなく、人として「あたりまえなこと」を、仕事の場でも当たり前にやろうということなのかもしれません。相手も自分も嬉しくなること、決して損はありません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2024 年 07 月 18 日 09:49
仕事の誇り
いきいきと働いている人をみると、やはり自分の仕事に誇りを持っています。自分の仕事が社会の役に立っている、誰かのお役に立てていると感じながら働けることほど、充実した時間はありません。自分の仕事や会社に誇りをもてるかどうか。大事な自分の家族に誇れるかどうか。誇りは働きがいです。
しかし、どうすれば自分の仕事に誇りがもてるのでしょうか。同じ給料で同じ仕事をしている人でも、「こんなつまらない仕事、やってられるか」と思う人もいれば、この仕事は「本当にいい仕事だ」と心をこめ、誇りをもってやる人もいます。しかし、どれだけ上司が、誇りをもってほしいと「仕事の素晴らしさ」を語ったとしても、それに共感するかどうかその人の心の問題。外側から何とかできる問題ではありませんが、自分の仕事に誇りを感じられれば、毎日が変わっていきそうです。
仕事への誇りは、どのような時に生まれてくるのか。単純ですが、私は、「自分がやると決め、心をこめて行ったことで、誰かが喜んでくれたり、思わぬ感謝の言葉をいただいた体験」が仕事の誇りにつながっていくのではないかと思います。苦しかったけど「やってよかった」「がんばってよかった」という感動体験。仕事を通した感動体験を通して、「自分はいい仕事をしている」という実感が生まれてくる気がします。
やらされていると感じ、仕事に心がこもっていない仕事でいい仕事はできませんし、そのような仕事で喜ぶ人はいません。例え業務が終わっても、目標を達成しても、やらされている気持ちでいれば、ホッとする気持ちになっても、感動はないはず。一生懸命のプロセスがあってこそ、感動体験が生まれます。
仕事は、頑張ったから必ず感謝されるかというと、そう単純なものではありません。しかし、そうした仕事を続けている人は、必ず誰かが見ていてくれる。少なくとも、自分自身がいちばん見ています。
自分の仕事を、心からいい仕事だと大切な家族に誇れる。給料も大事ですが、働く幸せは、こんなこともあるかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2024 年 07 月 10 日 13:26
やりたいことしか続かない
誰でもそうだと思いますが、人間にとって、やりたくないことを続けていくことは本当に苦しいこと。継続するには、それが本当に心からやりたいことでなければ、継続しないのではないかと思います。
個人もそうですが、企業においても、働く人がやりたいと思ってやっていなければ、いつか破綻していく。人間の本質に沿っていないことを持続させていくことは難しい気がします。
本来、自分のやりたいようにしたいというのが人間だとすれば、行動を型にはめる「マニュアル」も長続きしないのかもしれません。企業とすれば、「一律なサービス」を提供しようと接客もマニュアルにしますが、顧客としていろいろと見てきても、マニュアル通りの対応をしている人で、楽しそうな人はあまり見たことはありません。もちろん「悪くない対応」なので不満はありませんが、気持ちよいという感情にはなりません。不満を出さないサービスは提供できていても、働く人にとってはどうなのか。短期間のバイトなら我慢ができても、本当にやりがいを求める人にとって魅力はないかもしれませんが、義務感ややらされ感の顧客満足が長続きする訳がない。そんな気がします。
型にはめない対応を実現するのは、本当に難しいことなのでしょうか。「自分がやりたいと思ったことを、やりたいようにやりなさい」と社員に任せると悪いことが起こるのでしょうか。もちろん、企業である限り、何でもできる訳はなく、できる範囲は制限されると思いますが、働く人の「やりたいこと」を信じてやってもらうことは、そんなに難しいことなのでしょうか。
昭和の時代は、その仕事が嫌でも、義務感でもやらされ感でも、我慢してやることが当たり前と言われてきましたが、我慢しても、やはりやりたくないことは続かない。
あなたは、今、やりたいことをやれているか。働く人にも問われていることなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2024 年 06 月 25 日 10:02
お店の姿勢
私たち消費者は、お店を選ぶ時、便利だから、品揃えがいいから、接客がいいからというような理由で選んでいると思いますが、その理由の奥に、やはり、そのお店や企業の商売に対する姿勢も判断の軸になっているような気がします。旅行で利用するお店や、1回だけしか利用しないお店なら、それほど問題にしないかもしれませんが、通い続けているようなお店は、結局、その店の姿勢が好きという理由でファンになっているのではないでしょうか。
お店の姿勢というのは普段は見えないものですが、小さなところ、ちょっとした行動に滲み出てくるような気がします。先日、あるスーパーの方に、お客様と店員さんの小さなエピソードを伺いました。その日、閉店の準備が進み、まな板や包丁などを消毒して片付けをしていた時に、一人のお客様がキャベツをほしいと言ってこられたそうです。それも4分の1だけ。その時に店員さんは、喜んで!と笑顔で片づけたまな板や包丁を出して売ってあげたそうです。面倒な時間に申し訳ないとお客様も思っておられたはず。その時に嫌な顔ひとつせず対応してくれるお店の姿勢は嬉しかったに違いありません。
こうした対応はその人だけの特別なものではでないはず。普段から、こうしたことを大事にしようという店長がいて、快く手助けしてくれる仲間がいる。会社そのものが業績よりもお客様を大事にしようという姿勢があったからこそできた対応のような気がします。
お店の姿勢とは、企業の「あり方」、企業の理念。お客様を大事にするという姿勢、喜んでほしいという企業のあり方が「店の姿勢」として消費者に伝わっていく。4分の1のキャベツのように、お店の「あり方」が、売り場に、接客に、商品の細部ににじみ出て、そこに共感したお客様がファンになり、通い続けるようになる。
閉店間際に来店して、ムスッとした顔をされる店員さんもいますが、そうした対応も含めて、消費者は、いつもお店の「あり方」も敏感に感じているような気がします。
消費者がお店の「あり方」もお店選びの判断にしているとすれば、企業がもっと理念を大事にし、理念の浸透に多くの時間を割いていくことが、持続的に成長していくためにも大事な気がします。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の経営のあり方
2024 年 06 月 17 日 17:35
仕事の意義
仕事がつまらない、身が入らないという人がいます。頑張っているのになかなか成果があがらない、業務量が多い、単調になってしまう、身体が疲れている・・・そんな気持ちになる時の要因は様々だと思います。何が要因か、実際はその人によって異なるのかもしれませんが、その可能性のひとつとして、自分の仕事の意義・意味を感じられなくなっているということがあるかもしれません。
自分の仕事をただの仕事だと感じるか、それとも社会に役立つ価値ある仕事だと感じて働いているか。もし膨大な仕事をしていたとして、身体は疲れていたとしても、後者なら心は疲れないはず。目的も知らされず、「ただこの作業を行え」と言われてやるほど、苦しいことはありません。今、若い人の転職が増えていますが、やりがいを求めるのは、やはり自分にとって意義あること、意味のあることをしたいと誰もが思っているのではないでしょうか。
何のために働いているのだろうか。この仕事の意義は何だろうか。その人がわからなくても、どの会社にも、その答えがあります。多くの会社の事業の意義、意味は経営理念として明確になっているはずです。ただ、それが、社員にとっての「自分の働く意義、意味」として感じているかどうかは別の話で、経営理念がただ飾られているだけの会社では、社員もそれを感じる機会が少なくなるのではないでしょうか。理念が形骸化している会社ほど、仕事が作業になり、「つまらない」となってしまうのかもしれません。
自分の仕事に意義を感じているかどうかは、簡単な質問でわかります。例えば、車という商品を売っている会社の社員に「あなたの仕事は何ですか?」と尋ねてみる。そこで、何と応えるか。「私の仕事は、車を売る仕事だ」と応える人もいます。しかし、笑顔で「私の仕事は、車を通して人の幸せを提供する仕事だ」と応える人もいます。前者は仕事を単なる業務としてとらえている人。後者は、自分を、社会に役立つ仕事だと意義を感じている人。どちらの人がいきいきと働けているかどうか、言うまでもありません。
今、多くの企業で、希望をもって入社した若い人が3年たたずに辞めていくという状況が多くなっています。離職する理由はいろいろとあるかもしれませんが、もし「つまらない」と感じさせてしまうのは、やはり、自分のやっている仕事の意義や意味を感じさせてあげられていないということもあるのではないでしょうか。与えられた仕事をただの作業ととらえる3年か、その作業の先にはお客様がいて、喜んでもらっている尊い仕事をしていると感じて働く3年か。先輩や会社が理念を忘れていると、仕事は労働にしかならないですし、そんな会社に魅力を感じることはない。働く人が少なくなる時代、意義を求める時代だからこそ、改めて企業の理念というものが大事になる時代だと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2024 年 03 月 21 日 11:00
笑顔の力
顧客満足、ファンづくりの話をしている時、ある経営者が「単純なことかもしれないが、お客様にいかに安心してもらうことがファンづくりの基本。安心感をつくるのが笑顔だと思う」というお話をされていました。
笑顔にはどのような力があるのでしょうか。
初めての場所に行く。慣れない場所に行く時に、誰もが不安になります。病気になって病院に行く時などは、そもそも身体に不安があるので余計に不安が増します。そんな不安な時に誰かが笑顔で迎えてくれると少しホッとする。そんな体験は誰もが持っていると思います。
確かに「笑顔」には人を安心させる効果があります。ムスッとした表情で働いている人より、笑顔で働いている人を選んで話しかけようと思うのも笑顔の力。赤ちゃんの笑顔をみると誰もが笑顔になるように、笑顔は伝染し、ポジティブにさせる力もある。ある高齢者の方が、不安を抱えながら病院に通っている時に、受付の人がいつも笑顔で迎えてくれたから、通い続けることができたというお話を聞いたことがありますが、笑顔が人の勇気にもなる。そう考えると、笑顔は単なる表情以上の力があります。
どんなに商品が良くても、その店のスタッフに笑顔がないお店には何となく行きたくなくなるのは、どこか不安な気持ちになるからでしょう。店員さんが笑顔で迎えてくれるとホッとする。ホッとすると話しかけやすくなる。話しかけていると、相談をしたくなる。相談に乗ってくれると信頼する。信頼するとその人から買いたくなる。昔から、お店では笑顔が大事だと言われていますが、品揃えや店構え以上に、そんな小さなことがいちばん大事なことなのかもしれません。
だた、問題は、いつも笑顔でいること。それがなかなか難しい。
接客のプロは、朝起きたときに鏡の前で自分自身に笑顔を向けるということを習慣にされているそうですが、笑顔で始まると一日がポジティブな気持ちになるということは、心理学でも言われているそうです。
そう考えると、お客様の前だけでなく、出社する時も、仲間と挨拶する時も、意識して笑顔で挨拶をするのは大事な習慣です。人の笑顔につられて笑顔になるのなら、自分がまず笑顔でいる。すると相手が笑顔になって、また自分も楽しくなる。多少つくり笑顔と言われても、笑顔スタートが大事なのかもしれません。
自分自身に笑顔を向けると、自己価値を高める効果があり、自己肯定感が高まっていくそうです。当然、他人が笑顔でいてくれると、自分を受け入れられていると感じて、また自己肯定感が高まる。笑顔は心や健康にも影響が大きいもの。笑顔は顧客だけでなく、働く人の幸せや健康も高めていくのかもしれません。
たかが笑顔、されど笑顔ですね。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2024 年 03 月 12 日 15:03
社員が幸せな会社は成長する
今、世界各国で「幸せ」について研究されるようになり、何が幸せなのか、幸せに何が関係するのかということが少しずつわかってきているそうです。例えば、「金持ちになれば幸せになる」ということが昔から言われていましたが、幸せの研究では必ずしもお金と幸せは相関しないということもわかっているそうです。もちろんある程度のお金がなければ幸せではありませんが、いくらお金があっても憎しみ合って、幸せを感じていない人もいます。それよりも、家族や友人の関係が良いなど、良好な人間関係を築いている人が幸せを感じることが多い。「良い人間関係」が幸せと結びつくという結果もあるそうです。経営においても、幸せな社員が多い会社は、そうでない会社と比べて生産性が高く、業績も良いということも証拠が出てきているようです。先日も、ある会社に訪問させていただいたのですが、社内に入るととても良い雰囲気を感じました。お互いが笑顔で話され、一瞬で社内の人間関係の良さが伝わってきます。こうした雰囲気は社外にも伝わっているのでしょう。実際に、その会社は、お客様に喜ばれ成長を続けておられます。
何が幸せか。研究結果などでみると、何か新しい情報のように聞こえますが、我々は既にわかっていることなのかもしれません。私のまわりにも幸せそうな人がいますが、幸せを感じている人は、やはり前向きで、何事にも感謝して、ポジティブな気持ちをもっている。家族関係や友人関係が良い時は、仕事も前向きにできる。会社も、みんなが笑顔で働いている時は業績もあがるけど、ギスギスしている時は結果も悪い。幸せがよい結果につながっていく感覚は経験としてもわかります。
では、どうすれば、幸せになれるのか。何かを手に入れたり、ご馳走を食べると確かに「幸せ」を感じます。つい、こうしたことが毎日続けば幸せが手に入るような気がします。しかし、安い居酒屋でいい仲間と過ごす、いい時間という幸せも知っています。お金では買えない幸せがあるのも私たちは知っています。
健康でいること、家族と良い関係であること、いい仲間といい関係で働けていると感じること。自分の仕事に誇りを感じられること。その瞬間の幸せをハピネスと呼び、後者のようにしみじみと感じる幸せをウェルビーイングと呼ぶそうですが、この幸せは、長続きします。
いい会社にあふれているのは、後者のような幸せなのでしょう。「幸せになろう」ではなく、「今が幸せだ」を感じている人だからこそ、成長していくのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2024 年 02 月 27 日 17:36
外発と内発の動機付け
人のやる気を高めるためにインセンティブを与えるという方法があります。10件やれば1万円など、「達成すれば報酬がもらえる」となれば、きっと誰もが頑張って働くようになる。昔も今もお金は人を動かす動機になります。逆に、達成しないと上司から叱られたり、罰を受けるという状況をつくれば、人はそうならないために頑張るということもあります。
ただ、こうやって外側から人を動かそうとすることは確かに強力で効果的ですが、半面マイナス面もあります。例えば、報酬が出る時はやるけれど、出なくなればやらなくなる。罰が怖いと、それを避けるために、嘘をついたり、ごまかそうと、不正をはたらく人も出てきます。報酬を得る為に無理な販売をしたり、上司の怒りや罰を避けたいが故に、倫理に反する行動をしてしまう。昨今の不祥事の多くは、こうしたことが原因のひとつになっているようにも思えます。
しかし、だから、これからは内発的動機付けだと言われても、そもそも内発の動機ですから、好きでやっていることなら勝手に行動しますが、好きでないことや興味のないことはなかなかやらないのが人の常。さぼりたくなることもあります。そうするとまた報酬や罰で動かしたくなる。長い間、人間の世界はこの間で行き来しているのかもしれません。
ただ、本当は、結果に対する報酬をもらう為でもなく、罰を避けるためでもなく、純粋にその仕事が面白く、やりがいを感じながら働くことがいいということは誰もが理想だと思っているはず。やりたいこと、好きなことに取り組めることたら、何よりも幸せだとわかっているけれどなかなかそう理想通りにはいかないのが現実です。時には外発的な動機付けが必要なこともある。嫌だった仕事が、上司に激励され頑張る中で、好きになることなども、ざらにあります。外発も内発も、どちらがいいということではなさそうです。
ただ、社員の人たちがいきいきと内発的動機で働いている会社はどんどん増え、そんな会社で働きたいと思う人も増えているのは確かです。「仕事は好きとか嫌いじゃない」と外発的動機付けで、厳しく怒られならがやってきた世代にとっては、なかなか馴染めないのかもしれませんが、後何年か経てば、こんな動機付けはどんどん古くなっていくような気もします。嫌なことを無理にやる、やらせる世界ではなく、やりたいこと、好きなことをやって成果を出す。こうした働き方がスタンダードになるのはいつでしょうか。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 11 月 30 日 11:36
いきいきと働くことの価値
人に「仕事は楽しいですか?」と尋ねると、あたりまえですが様々な反応がかえってきます。即座に「楽しい」と言われる人。「楽しいなんて感じたことがない」という人。そもそも、給料をもらって働いているのだから、仕事はつべこべ言わずやるもので、楽しいとか、楽しくないということは言うものではないという意見を聞くこともあります。「楽しくなくてもやるのが仕事」というのが、世間一般的の認識かもしれません。「楽しくいきいきと働く」ということに価値や意義を感じていない人や会社は、まだ多いのかもしれません。
しかし、社員がいきいきと働いている会社は、そうでない会社より、業績が高いという研究結果もあるように、経営においても重要なテーマであり、同時に働く人のやりがいや生きがいからみても、いきいきと働けることは大切なことだと思います。
ただ、いきいきと働くというのは本当に曖昧です。いきいきに明確な定義もなく、こうすればいきいきと働ける、こうすればやりがいが高まるというような決まりもありません。いきいきと働くきっかけも人によって様々です。
例えば、面白くないと思って働いていたとしても、誰かに「ありがとう」と言われたりすると、自分の役割を感じて自分の仕事が違ってみえることもあります。人間関係の中で「やりがい」がみつかることがあります。
自分が一生懸命に取り組んだ仕事で、お客様が涙を流して喜んでくれた。そんな体験を通して仕事に誇りを感じることもあります。喜ばれることはやりがいになります。役立てた体験は心が躍ります。
また、マニュアル通りにやっていた時は楽しくなかったけど、初めての仕事に挑戦していく中で創意工夫をしている時にいきいきしてくることもあります。言われたまま仕事をしていると辛いけど、「自分が仕事をコントロールしている」と感じられる時は楽しいもの。だんだんと仕事ができるようになると、この楽しさが得られます。
それ以外にも、誰からも褒められない単調な裏方仕事。流れ作業のようにこなしていた仕事が、その先にお客様がいてそれが幸せにつながっていると実感できた時、自分の仕事が輝いてみえることがあります。自分の仕事は地味だけど、社会に役立っている。そんな体験をした時に、自分に誇りを感じるでしょう。
やりがいを感じる瞬間、いきいきとする瞬間は様々です。このような瞬間はいつ訪れるかわかりませんが、この中のひとつでも体験できれば、自分の仕事の見方は変わる。そんな人もたくさん見てきました。
だだ、やりがいを感じるかどうかは個人差もありますので、会社がこのためにやれることは少ないのかもしれませんが、例えば、仲間同士で「ありがとう」を言う。仲間を信じて仕事を任せる、裏方の人に感謝を伝える、仲間の頑張りを認める、褒める。お客様の感謝の声を共有する。小さなことならできることはあるのかもしれません。
こうやって仕事の中にはいろんな体験ができる。しかし、「そもそも仕事は楽しくないもの」と思っていると、こんな瞬間に出会っても素通りしてしまうのかもしれません。「いきいきと働く」ということに価値を感じるのか、そんな風に働きたいと願っているのか。最後はその人がどう働きたいかなのではないでしょうか。
8時間の労働時間をつまらない時間するのも、楽しい時間にするのも自分。楽しさは見つけたいと思う人だけが見つけられるのかもしれません。皆さんは、いきいきと働きたいですか?
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2023 年 11 月 14 日 15:06
心が突き動かされるもの
先日、ある塾の講師の方のお話を聞く機会がありました。勉強嫌いの生徒のやる気をいかに高めるかということを一生懸命取り組まれてきた方で、その塾から何人も難関校への合格者が出ています。
どうすれば生徒のやる気を高められるのか。その方が取り組まれたのは、受験する「目的」をとことん聞くことでした。〇〇に合格するというのは目標ですが、目的があいまいな生徒はやはり最後まで頑張ることができない。なぜ合格したいのか?何のために勉強したいのか?勉強を始める前に、その人に向き合い、その理由をしっかり聴くそうです。自分が勉強する目的、その学校を受験する目的。そこがはっきりすると、生徒の目の色が変わり進んで勉強するようになる。こんな話を伺いました。
ビジネスの世界でも同じかもしれません。いくら数値目標や行動目標を明確にして取り組んでみても、その目標の奥にある「何のためにやるのか」という自分が進む理由、目的がなければ、最後は力がでない。あの山に登ろうと言われても、そこに「どうしても登りたい」という強い思いがなければ途中で諦めてしまいます。
そこに行きたいと思うかどうか。自分の心を動かされる目的があるかどうかは、社会人にとっても大切なことだと思います。
ただ、社会人の場合、どの組織でも組織の目的は明確になっています。我々は何のために働くのかは「企業使命」として理念に謳われています。それなのに、その目的が社員にとっての「登りたい山」になっていない場合もある。最近、行動指針を示し社員に徹底させようしているのに、なかなか現場で実行されないという悩みを伺ったことがありますが、これも目標の奥にある目的が語られていないからかもしれません。「どこをめざすか」「何をやるか」は明確になっていても「なぜやるか」がわからない。働く人が目的に心が突き動かされていないと、いくら行動を強制しても形だけになってしまいます。
組織の目的が自分も登りたい山であれれば自分から登ろうとする。そう考えると、企業の理念はやはり、働く人の心を突き動かすものであり、人がそこに行きたいと思う崇高なものでなければならないでしょうし、その理想と経営者の行動が一致していなければ、誰の心も動くはずがありません。
自分の心を突き動かす目的があれば努力は継続する。やる気の源泉はやはり「目的」だと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 07 月 19 日 10:29
誇れる仕事
先日、何百年も前に建てられたお寺などの建築物などを修繕したり、建て直しをする、宮大工の方のお話を読みました。古い建物は一度すべて解体し、傷んだ部分を直し、できるだけその古材を利用して建て直すのですが、解体してみると、外から見えない部分が見えてきて、当時、この建物を建てた大工さんの技術が見えてくるそうです。
外側から、見えないところにこそ丁寧な仕事が施されているそのきめ細やかな技術を見ると、「自分に恥じない仕事をしよう」という当時の大工さんの心が伝わってくる、解体に携わった宮大工さんは、その当時の職人さんの誇りや仕事への姿勢に、とても感動されていました。
裏側の部分だから、もし手を抜いても誰も見ていない。怒られることはない。しかし、それでよしとするかどうか、決めるのは自分です。しかし、いちばん見ているのは自分。
もし、手を抜いてしまったら、その人はその建物を通る度に胸が痛くなるかもしれません。その前に立てなくなるかもしれません。
出来上がったお寺の前に立って、誇れる自分でいたい。きっと、それがその職人たちの想いだったのではないでしょうか。仕事の判断基準は、自分の「良心」です。
翻って、今の自分の仕事はどうか。
本当はもう一度やり直した方がよいものができるのに、安易に妥協していないか。
早く納めることばかりに意識がいって、品質を下げていないか。
仕事の質は、追求すればするほど、さらに上が見えてきて、なかなか100点が見えてきません。
納期、予算、スピード、全体の生産性・・・。いい仕事の前にはいろんな壁があり、どこかで妥協しなければならない。しかし、数百年前の大工さんの時代でも、もしかするといろんな制約があったのではないか。しかし、彼らは、その厳しい制約の中でも、自分に恥じない仕事をしようと闘っておられたに違いありません。
どこまでいい仕事をやり抜くか。自分の良心に誇れる仕事をしていきたいです。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 03 月 22 日 14:33
Fail fast(早く失敗せよ)
目標を掲げて取り組んでいたのに達成しなかったり、仕事を抱え込みすぎてパンクしてしまったり、仕事をしていると上手くいかないことが時々発生してしまいます。失敗すると精神的にも辛いし、落ち込みます。だから、次は失敗したくないと思い、なぜ上手くいかなかったのか、どうすれば上手くいくようにできるかを考えて、次に挑戦をする。取り組みを変え、自分の向き合い方を変え、やり続けていく中でようやく成功する。
スポーツにしても、ビジネスにしても、この繰り返しの中で、人は成長していくのだろうと思います。
そう考えてみると、失敗ということは、人が成長していくためには最も大事なこと。よく言われるように、失敗こそが、成長の原動力なのだと思います。だからよく「失敗を恐れずに挑戦しろ」と言われるのだと思いますが、失敗すると怒られたり、厳しく叱責されるという環境の中だと、失敗を避けるようになってしまいます。
目標を低く設定したり、新しい挑戦を避ける。不安な道に進むより、正解がある道、安全な道を選ぼうとする。その道は、確かに失敗は少ないけど、考える機会も少ない。成長のためには、失敗のある道の方が良いように思います。
ただ、いくら失敗が大事だと言っても、それを自分の「糧」にしなければ成長はない。「失敗を気にしない」と反省をしないで次に挑んでも同じ失敗をしてしまいます。失敗が大事というよりは、「失敗から何を学んだか」、教訓を得ることが大事であって、失敗後の「振り返り」がなければ、成長にはつながらない。一番大事なのは、ここだと思います。
アメリカのシリコンバレーでは、「Fail fast」(早く失敗せよ)という言葉が良くスローガンとして使われているそうです。どのような天才でも100%成功する時代ではない。だからこそ、アイディアを実際に試して失敗し、そこから得た教訓をもとにまた新しい仮説を試す。その繰り返しを早く実行することが成功につながる。
それがFail fastという標語の意味。変化が激しく、誰も正解がわからない時代だからこそ、失敗から学んでいくことが大事だと、この業界では失敗を推奨しているそうですが、どの業界でも大事なことではないでしょうか。
失敗の連続は確かに苦しいことかもれませんが、そこで七転八倒してきた数年を振り返った時に、人生の充実感や自分の成長を感じることがあります。そうやって考えてみると、人生にとっても失敗は大事な経験であるように思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 02 月 20 日 18:07
お客様の立場に立つ
お客様の立場に立って考える。お客様のニーズをつかむ。
昔から接客においても、商品開発においても、お客様の側に立って考えて行動することが大事であると言われています。ただ、実際は「お客様のためになる」と思ってやったことが、すべて上手くいく訳ではなく、思ったよりもヒットしなかったり、「お客様のために」と考えたことが、逆に余計なお世話だと感じられてしまったというようなことが起こったりします。
以前こんな話を聞きました。あるお客様のお店の「おもてなし」についての感想です。
「お店に入った時、駐車場でスタッフがドアの前で迎えてくれるのは嬉しいんだけど、何となく早く降りろと言われているようで嫌な気になった」。
お店側としたら、店舗で挨拶をするより、お客様の車の方まで行ってお迎えする方がお客様に気持ちが伝わると思われてやっている「おもてなし」だと思います。しかし、お客様の立場になってみた時、確かに目の前で待たれていると逆に気を使ってしまう。そんな気持ちもわかります。もちろん、これが「嬉しい」「気にならない」というお客様もおられますので、この接客がすべて悪い訳ではないはず。ただ、店側が「お客様のために」と思ってしたことと、お客様の感じ方がずれることは、よく起こっていることかもしれません。
セブンイレブンの創業者、鈴木敏夫さんは、「お客様のために」と「お客様の立場に立つ」という考え方は違うと言われている経営者です。
「お客様のために」という時は、どこか「過去の経験」をもとにしたお客様に対する思い、決めつけがあり、お客様がそれを良いと思われているどうかはわからない。「お客様のために」と言いながら、自分達のできる範囲でしか考えていないのではないか。どこかで自分達の都合を優先しているのではないかと言われています。
「お客様の立場に立つ」ということは、あくまでもお客様の立場で見ることで、お客様のニーズから発想していくこと。もしかすると自分達にとって不都合なことでも実践していかなければならないこともある。だからこそ「お客様のために」ではなく、「お客様の立場に立つ」というお客様を起点にして考えていく。その重要性を従業員に伝えておられています。
「お客様のために」という思いは悪いことではなく、人の役に立とう、喜んでほしいという姿勢は商売の上で大事なことだと思います。ただ何が良いかどうかはお客様が判断すること。その立場に考えてみないと間違ったことをしてしまいます。「お客様の立場で」と強く言われるのはそうした戒めだと思います。
ただ、お客様からの目線で見るということは、意識しないとなかなかできません。鈴木敏夫さんも、実際に毎日、商品を試食し、土日でも消費者としてセブンイレブンを利用して、「お客様の立場に立つ」を実践されていたそうです。
「お客様のために」と「お客様の立場に立つ」。つい、同じような意味で使ってしまいますが、良い商品をつくるためにも、お客様に喜んでいただく店にするためにも、やはり「お客様を起点に考える」ことが重要なポイントになるのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2023 年 02 月 07 日 14:07
やってみなはれ精神
ここにきてだいぶコロナ禍も収まりつつありますが、この数年間、飲食や旅行などのサービス業の皆様は本当にたいへんな時期を迎えられたと思います。来店客がゼロになる、しかし大切な従業員を簡単に解雇する訳にはいかないという厳しい選択が迫られる中で、何とか業績を上げようと新しい取り組みに挑戦された方も多かったと思います。先日あるホテルの経営者にコロナ禍での取り組みをお伺いしましたが、料理の通販やお弁当の販売、団体にホテルを1棟丸ごとお貸しするプランなど従業員の皆さんとアイディアを出し合い、この数年間、必死に取り組まれたそうです。行ったものの中には全く売れないものなど、たくさんの失敗があったそうですが、その挑戦の中にはヒットし、今後の新しい柱に成長したものもあったそうです。コロナだからと尻込みをしなくてよかった、やってみることの大切さを痛感したと、その経営者が語っておられました。
「やってみなはれ。やらなわからしまへんで」。これは、国産初のウイスキーを開発したサントリーの創業者、鳥居信治郎さんが大切にされていた言葉だそうです。
入念な市場調査を重ねて開発した新車が売れなかったり、逆に思いもかけない売れ方をすることがあるということがあるそうですが、未来を確実に予測できることは少なく、何事も「やってみなければとわからない」ものかもしれません。
サントリーさんが創業した戦後の混乱期や現代のコロナ禍など、誰も経験をしたことがないことが起こった時や、未開拓の分野に出る時は、誰も正解がわからない。だからこそ、「やってみなはれ」という歩き方が必要だったのでしょう。以前、新しい仕事をする時はPDCAではなく、まず行動から始める「D‐CAP」が大事だという考え方を教えていただいただことがあります。安全に関わることや大きな予算や多く人が動くような仕事は入念な計画をしなくてはいけませんが、初めてのプロジェクトや未知の分野の仕事をする時は、とにかく小さく始めてみること、そこから学び、改善していくという「D‐CAP」の方が良いのかもしれません。
ただ、そうはいっても「まずやってみる」ということは、勇気がいります。責任の重圧や失敗した時の恐怖、未知の世界に飛び込む時は誰でも怖いもの。
「やってみなはれ、やらなわからしまへんで」と言えるリーダーでありたいなと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2022 年 12 月 27 日 17:48
お客様満足が社員の満足
昔から、ESなくしてCSなしと言われていますが、時々CSが先ではないかと思うことがあります。
先日、ある社員がいい表情をして会社に帰ってきました。苦労した仕事が一段落し、それがお客様にとても喜んでいただけたと言います。彼は何か月もの間、どうすればもっと役に立てるのかと考え続け、準備や打ち合わせを重ねてきたので、仕事が終わった時に、お客様から「ありがとう」と言葉をかけてもらえたことが本当にうれしかったのでしょう。
やりがいを感じてやっているから、お客様に喜ばれる仕事ができたとも言えますが、お客様に喜ばれたからやりがいにつながったとも言えます。鶏と卵のような関係です。ただ、よく考えてみればこうした感動を味わうことができるのはお客様がいるからこそ。感謝されたことが喜びにつながったのは間違いないですが、何とかして「お客様に喜んでいただきたい」と仕事をしている間もやりがいを感じていたと思います。
「もっとお役に立ちたい」とCSを考えていること自体がESを高めるとすれば、やはりCSが先。誰かに喜んでもらおうと思いながら仕事をしていくことは、幸せに働くことの出発点かもしれません。
最近、社員満足や働きがいということが盛んに言われるようになっていますが、それを高めるのはお客様満足だとすれば、全社でお客様満足に向かって仕事をしていくことがいちばん最初のスタートかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2022 年 10 月 18 日 11:47
「楽しさ」の歯車が回り出す瞬間
「やらされ感」ではいい仕事ができない。仕事は楽しくない。
これは心の中では誰でもわかっていることですが、上司の命令だからやるしかない、仕事だからしょうがないと、やらされ感を覚えながらも、与えられた仕事をなんとかこなしていけば、なんとか仕事は進んでいきます。
昭和の時代は、そんな感情を持ちながらも「歯を食いしばってやるのが仕事だ」「好き嫌いを仕事に持ち込むな」と気持ちを奮い立たせてみんなが頑張ってきた時代でした。やらされ感であろうがなかろうが、なにくそと働いていくのが常識の時代だったと思いますが、今やそんな常識は通用しません。
どうすれば、人はやらされ感ではなく、自ら進んでやりたいと思えるようになるのでしょうか。
先日、ある若い社員から、「最近、仕事を追求していくことが楽しくなってきました。面白くなってきました」という嬉しいメールをもらったのですが、きっかけは、ある仕事の責任者として矢面に立ったことだったようです。その仕事は、先輩に頼らなければできない大変な仕事だったのですが、何とかやりきり、お客様から感謝されたことで、仕事の楽しさや喜びを感じたようです。
自らやっていくことの面白さ、仕事の目的を追求していくことの面白さを一度知ると、それからは仕事の仕方が変わります。私もそうでしたが、一生懸命に取り組んだことが人に役立った感動体験は、働く楽しさに気づく大きな転機になります。
ただ、大変な仕事ほど、途中でくじけることもあります。先ほどの若い社員を支えていた先輩社員の存在が大きかったようです。横にいてくれた先輩が、仕事に妥協せずに取り組んでいる姿やお客様に喜んでもらいたいと一生懸命に頑張る姿勢が支えになったようです。上司や先輩の関わり方が大切になってきます。
その若い社員は最近、自分から本を読むようになったり、仕事の効率を考えてどんどん工夫や改善をしています。人を思いやるゆとりや感謝の気持ちも高まってきて、毎日が楽しそうです。
一度「楽しい」という歯車が回り出すと、言われなくても動き出すのが人。楽しさこそ、成長の原動力だと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2022 年 10 月 12 日 13:23
仕事の厳しさ
令和の時代に、昭和の話をするのは本当に時代遅れですが、昔は厳しい人がたくさんおられました。厳しいというのは、偉そうにしたり、人を罵倒したり、こき使うということではなく、「いい仕事をすること」に本気で取り組み、自分にも、周りにも厳しいという人です。
私が育った映像制作の業界では、監督、カメラマン、照明、音声など、様々な独立事業主が現場に集まり、ひとつの作品を作るために、喧々諤々議論をしたり、いいものが撮れるまで何度もやり直しをして、みんなでいい作品を作ってやろうと必死に頑張っていました。
現場では何度も叱られたり、怒鳴られることもありましたが、飲み会の席でも、いい作品を作るために議論をしている先輩の姿を見ていると、やっぱり、この仕事が好きだからこそ本気になるのだなあと、カッコよさを感じ、いつの間にかこの空気が好きになり、本気になっていきました。
撮影というのは様々な条件の中でやりきらないといけない厳しい世界。チームが一丸とならないと良いものはできません。だからこそ、現場には、今ならパワハラと思われるような罵声も飛び交っていましたが、そこには「いい作品を作るんだ」という夢に向かって進むチームの一体感がありました。
厳しい現場を一日頑張って、みんなで酒を飲み、次の日を迎える。先輩と語り合う中で、先輩の仕事への想いや、私を育てようとしてくれる優しさを感じることもあり、決して心がすさむことはありませんでした。知らない人から見ると厳しい世界に見えると思いますが、本当に人がいきいき働いている現場でした。
今は時代が変わり、若い人を怒ることも叱ることもなかなかできません。遅くまで働くこともできませんし、飲み会の機会も減ってきました。なかなか若い人に面白さを伝えることが難しくなっています。
もちろん、こんな昭和のやり方がすべて良いとは思いませんが、「良いものを作るんだ」「もっと良くしていこう」という気概がなく、ただ決められた仕事をこなすだけでは、いいものは生まれませんし、企業は成長していきません。働く人も仕事の面白さもやりがいも感じることはできないのも事実です。
厳しくてもいきいきと働ける組織と、厳しくて人が荒んでしまう組織と何が違うのでしょうか。
私が若い時、厳しい中でもやりがいを感じることができたのは、仲間が「みんなでいいものをつくろう」という夢があったから。この夢がない組織では、ただ仕事をするだけになってしまうでしょう。
会社でいうなら、理念やビジョン。もっと良いものを提供していこう、もっとお客様に喜んでもらおうという「共通の夢」への共感が、チームにとっていちばん大事なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2022 年 06 月 07 日 10:18
仕事の奥にある楽しさ
「仕事は、毎日同じことの繰り返しで、つまらない。」そう感じている人も多いかもしれません。
あるホテルの経営者に聞いたことがあるのですが、右も左もわからない新人の時は一生懸命フロントで接客をやっていた人も、ある程度仕事ができるようになると以前の輝きが消え、いつの間にか辞めてしまうということがあるということでした。
確かに、ただ同じことを毎日繰り替えしていると面白くない。だから、仕事を楽しくするには「同じことを繰り返さない」ということになります。しかし、「業務は決められているのだから、毎日同じことを繰り返すだけだ」とも言われます。どうすれば楽しくなるのでしょうか。
先日、ある美容院のベテランスタッフの方に、シャンプーをしていただく機会がありました。普段シャンプーは新人や若いスタッフがすることが多いのですが、この日は若い人が研修で不在だったので、20年以上この仕事をされてこられたベテランの美容師の先生が私を担当してくださったのです。その手さばきは実に丁寧。シャンプーの間の言葉も、雰囲気も心地よく、夢見心地になってしまいました。
どのようにこういう技術を覚えられたのかと伺ってみたのですが、やはり若い時に毎日シャンプーに取り組みながら技術を向上させてきたということでした。「どうすればもっと気持ちのよいシャンプーができるか」と、手の強さや洗い方を工夫したり、人のまねをしたり。また、お客様によって頭皮の柔軟性が違うことに気づかれて、お客様の皮膚に合わせて力加減を変えるなど、「お客様にとって気持ちよいシャンプーとは何か」という課題にずっと取り組んでこられたそうです。
若い人からすると、この人は、一見、シャンプーという「同じ仕事」をしているように映るかもしれません。しかし、この方にとっては、毎日が違う仕事に挑戦している感覚なのだと思います。だから面白くなり、何十年も続けてこられたのでしょう。
どんな仕事にも「奥」があると思います。トイレ掃除でも、窓ふきでも、一見単調に見える仕事でも、もっと良くできる、もっとうまくできるはずだと追求すればするほど、だんだん奥が見えてくる。まだまだ未熟な自分に出会う。だから技術を高めたくなる。これが「仕事の楽しさ」ではないでしょうか。
「そこそこできる」で「自分は仕事ができるようになった」と思っていると、後は繰り返し。あとは、その人が、そこから先に行こうとするかどうか。若い人に、この「奥」の楽しさ、「仕事を深める」ことの面白さをどう伝えていけるかが先輩の仕事なのだと思いますが、数秒のタイミング、数グラムの力加減で出来栄えが変わるこの世界を、言葉で伝えていくのは本当に難しい。その人が「自分もそこに行きたい」と思わないとつかめません。
仕事は、毎日同じことをくり返すこともできるし、毎日進化させていくこともできる。どちらを選ぶかですね。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2022 年 05 月 18 日 16:48
仕事と生きがい
先日、ある方のお招きで、改装した古民家で一日一グループのお客様だけに、フランス料理を出すお店に行きました。この店のシェフは71歳。若い時からホテルで修行し、最後は一流ホテルの料理長として経験を重ねた素晴らしい職人さん。ひとつひとつの料理が繊細で本当に美味しく、最初から最後まで楽しませていただきました。
食事をしている時、料理長自らが料理を運び、その都度、料理の説明やフランス料理のことを説明してくださいます。材料の仕入れへの時間のかけ方、お客様に合わせた調理の時間の工夫、美味しくなるか不味くなるかのギリギリの調理時間のお話など、なかなか聞けないプロの仕事の裏側を聞かせていただきました。
ひとつの料理の奥に、こんなにも工夫や努力があるのかと驚いたのですが、それ以上に、自分の仕事に誇りを持ち、楽しそうに語られる料理長の仕事への姿勢にも感動してしまいました。自分の得意分野を長年時間をかけて極め続け、今、この料理に全力を傾け提供する、そのことで人が喜んでくれる。その幸せそうな笑顔がまた自分の励みになり、収入になる。そのことが嬉しくて、また自分の技術を磨き、努力する。人生の中で、自分が心から打ち込める仕事を見つけることは、本当に素晴らしいことだなあと、料理長の話に耳を傾けていました。
今、日本人独特の幸福感である「生きがい」という概念が欧米で注目されているそうです。なぜ、日本人は長生なのか?長寿と生きがいについて研究が進んでいます。その学者がまとめた「生きがい」の構成要素が、「好きなこと」「社会が必要とすること」「得意なこと」「収入を得られること」の4つ。自分の好きなこと、自分の得意なことが出来ていて、それが社会の役に立っていると感じられ、尚且つそれが生業になっているという時に、人は生きがいという幸福感を味わっているのだそうです。料理長の話を聞きながら、このことを思い出していました。
私たちも、仕事をしていて、やりがいや幸せを感じることがあります。やりがいを感じると努力も楽しくなる。失敗したり、うまくいかないことがあると苦しいけれど、そこに格闘することで、どこか生きていることを感じる。こんな日々が生きがいを作っていくのではないでしょうか。
仕事はただお金を稼ぐ作業だと思うと、手を抜きたくなってしまいますが、自分の生きがいであれば、努力も楽しくなっていく。仕事をどうとらえるか。長い人生を豊かに生きる上でいちばん大切なことかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢