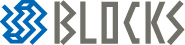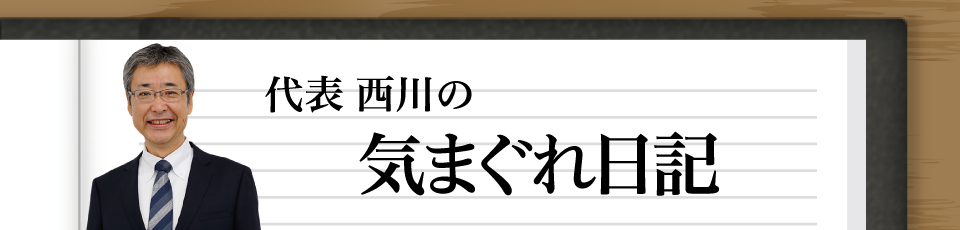2025 年 12 月 24 日 16:54
職場の雰囲気、会社の社風
先日ある会社を訪問しました。社員同士の信頼関係が良好で、会議の中でも職場の中でも、ああしよう、こうしようと意見が飛び交い、みなぎるような活気を感じました。しかし、その会社も、数十年前はお互いが悪口を言い合い、毎月のように人が辞めていく暗い職場だったそうです。このままではいけないと思った経営者が、いい社風にしようと取り組みはじめて数年。少しずつ職場の中に良い空気が生まれてくるようになりました。今まで仲が悪かった人たちも、次第にコミュニケーションをとるようになり、部門を超えた協力や助け合いも生まれる。それに比例するように業績もあがっていったそうです。社内の雰囲気がいいと上司にも話しかけすくなり、連携が良くなりミスも少なくなる。意見が増えれば新しいアイディアも生まれる。「空気」には力があると言われていますが、生産性の土台にはいい雰囲気の職場が欠かせないと思います。
組織の雰囲気といってもいろいろあります。だだ、仲がいいだけの仲良しクラブのような雰囲気の職場もあれば、間違っていたら指摘する、喧々諤々意見を戦わせながらも力を合わせるという雰囲気の職場もある。自分の業務だけをして帰るような雰囲気の会社もあれば、社員同士がいつも「ありがとう」と言い合い、いつも助け合いながら働く雰囲気の職場もある。会社によって雰囲気は違います。組織の雰囲気や社風というのは、人間でいう人柄のようなものかもしれません。
最初に紹介した会社では、いつも社員同士の会話でも、人に何か伝える時に「ありがとう」という言葉を添えて声をかけあっておられました。それを聞くこちらも心地よくなり、頑張ろうという気持ちがみなぎってきます。気づくことができ、感謝ができるという社風は本当にいい社風だと感じました。
人柄というものが、その人の人生のこれまでの体験の中で生まれてきたものだとすれば、社風や職場の雰囲気も長年の積み重ねで生まれているので、そう簡単に変わるものではないのかもしれませんが、それが人の頃や活動に影響が与えるとしたら、よい社風、よい雰囲気の職場をつくりたいものです。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2025 年 12 月 12 日 10:44
仕事の奥にある楽しさ
「仕事は、毎日同じことの繰り返しで、つまらない。」そう感じている人も多いかもしれません。あるホテルの経営者に聞いたことがあるのですが、右も左もわからない新人の時は一生懸命フロントで接客をやっていた人も、ある程度仕事ができるようになると以前の輝きが消え、いつの間にか辞めてしまうということがあるということでした。
確かに、ただ同じことを毎日繰り替えしていると仕事は面白くありません。だから、仕事を楽しくするには「同じことを繰り返さない」ということになります。しかし、「業務は決められているのだから、毎日同じことを繰り返すだけだ」とも言われます。どうすれば楽しくなるのでしょうか。
先日、ある美容院のベテランスタッフの方に、シャンプーをしていただく機会がありました。普段シャンプーは新人や若いスタッフがする仕事なのですが、この日は若い人が研修で不在だったので、20年以上この仕事をされてこられたベテランの美容師の先生が私を担当してくださったのです。その手さばきは実に丁寧。シャンプーの間の言葉も、雰囲気も心地よく、夢見心地になってしまいました。
どのようにこういう技術を覚えられたのかと伺ってみたのですが、やはり若い時に毎日シャンプーに取り組みながら技術を向上させてきたということでした。「どうすればもっと気持ちのよいシャンプーができるか」と、手の強さや洗い方を工夫したり、人のまねをしたり。また、お客様によって頭皮の柔軟性が違うことに気づかれて、お客様の皮膚に合わせて力加減を変えるなど、「お客様にとって気持ちよいシャンプーとは何か」という課題にずっと取り組んでこられたそうです。
奥を知らない人からみると、この人は一見シャンプーという「同じ仕事」をしているように映るかもしれません。しかし、この方にとっては、毎日が違う仕事に挑戦している感覚。だから面白くなり、何十年も続けてこられたのでしょう。
どんな仕事にも「奥」があると思います。掃除でも、検査作業でも、一見単調に見える仕事でも、もっと良くできる、もっとうまくできるはずだと追求すればするほど、だんだん奥が見えてくる。まだまだ未熟な自分に出会う。だから技術を高めたくなる。これが「仕事の楽しさ」ではないでしょうか。
「そこそこできる」で「自分は仕事ができるようになった」と思っていると、後はその繰り返し。面白さには出会えない。若い人に、この「奥」の楽しさ、「仕事を深める」ことの面白さを、どう伝えていけるかが先輩の仕事なのだと思いますが、数秒のタイミング、数グラムの力加減で出来栄えが変わるこの世界を言葉で伝えていくのは本当に難しい。その人が「自分もそこに行きたい」と思わないとつかめません。
ただ、仕事は、毎日同じことをくり返すこともできるし、毎日進化させていくこともできる。どちらを選びますか。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2025 年 11 月 27 日 15:22
やらされる仕事とやりたい仕事
世の中にはいろいろな仕事がありますが、同じ仕事をしていても、そこにやりがいを感じてやっている人もいれば、しかたなくやっているという人もいます。やらされていると感じながらやる仕事は、辛いのだろうと思っていたのですが、最近はそれに慣れてしまう人もいると聞きます。自分の意見も言わず、工夫もせず、ただ言われたことだけをやり、時間になったら帰る。お金のため、生活のために自分の時間を売るというのも生き方のひとつなのかもしれませんが、同じ仕事でも、そこに面白さや楽しさを感じられれば自分自身の人生も変わると思います。だだ、仕事を面白くしたいかどうかも決めるのはその人次第。無理に変える訳にはいきません。
しかし、どうすれば、仕事が「面白い」と感じられるのでしょうか。
先日の休みに、地域のボランティア活動があり頼まれてその手伝いをしていました。朝早くから荷物を運びテントを立て、企画していた催し物を協力して実行する。傍から見てもかなりハードな仕事ですが、そこに集まったスタッフの人たちは実に楽しそうにその活動に取り組んでいました。食事は自分持ち、報酬はゼロ。しかし、みんなで来場者をもてなし、イベント運営に一生懸命に取り組んでおられます。
傍から見れば、会社と同じような「業務・作業」をしているように見えます。しかし、全員が笑顔。なぜ会社の業務は「やらされ」になり、無償のイベントが「やりたい」になるのでしょうか。
単純にいえば、この人たちはこの仕事に意義を感じている。スタッフの人たちは、このイベントの趣旨に心から共感しています。これが会社との違い。
ただ、いくら意義に共感して参加していたとしても、会社のように、上からの指示命令ばかりでは「やらされ」になるはず。主催者の動きを見ていると、とにかく、みんなを巻き込んで、スタッフの人たちの意見も聞き、みんなで作り上げるような運営をされています。その人に任したブースは、その人が考え、その人が行動してやっていく。もちろんメンバー同士の人間関係がいい。この空気も楽しさのひとつのようです。
意義の実感と自由裁量、良好な人間関係。その仕事に意義を感じるかどうか、自由裁量があるかどうか。報酬のあるなし、会社かどうかではなく、これが「業務・作業」を“楽しい”に変える要素なのではないでしょうか。自分の仕事の本当の価値や意義を見つけ、自分のやれる領域を自分で伸ばしていけば、仕事は「やりたいからやる行為」に変わっていくと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2025 年 11 月 18 日 13:42
困った時に一番に思い出される会社
私たちの周りには、他にも沢山の選択肢があるにも関わらず、何か困ったことがあれば、一番に思い出し、必ずそこに相談してみようというような「頼れる存在」がいますが、ある会社は、お客様にとってのそういう存在を目指そうと「お客様のファーストコールカンパニーになる」という理念を掲げられていました。何かあった時に一番に思い出し、声をかけてくれる。信頼していただけるお客様がたくさんいる会社は、景気に左右されることなく繁栄し続ける気がします。
しかし、よく考えてみると、最初に思い出してもらえる存在というのは、そう簡単になれるものではないはずです。1回だけなら満足してもらうことは出来そうですが、何度も、それも様々なお客様の要望に応えるためには、技術力も知識が不可欠です。しかも、困っているお客様に対して、親身になって寄り添っていく思いやりの心もなければ、次も相談しようという気持ちにはなりません。しかし、かといって何でも安請け合いをすることがお客様の為ではなく、自分に出来ないことは出来ないと、断ることができることも大事なのかもしれません。企業であればお客様から発注された仕様通りに仕事をすることは当然ですが、ある会社の社員の人は、お客様から渡された仕様の中に、そのやり方では効率が悪くなるという問題が見つかり、変更した方がきっとお客様のためになると思った時は、例え、その提案をすることで受注額が減額になり、自社の利益が下がることになったとしても、良いと思ったことは必ず提案し解決すると話されていました。
お客様の指示通りに進めれば、手間もかからず利益も確保できるけど、それでは自分の気持ちが許さない。だからこそ、手間がかかっても提案すると言われていました。お客様も、そうした対応をしてくれる会社だと絶大な信頼を置かれていて、何かあった時には、必ず相談する先になっているそうです。自分自身がファーストコールがかかる存在であるだろうか?と考えた時、自分の一つひとつの仕事が問われている気がします。
お客様が一番に思い出す、一番に声をかけてくれるファーストコールカンパニー。企業や人の誠実さこそが、そこに行く唯一の道なのかもしれません。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上 素晴らしい会社
2025 年 11 月 13 日 14:42
「見えない資産」の重み
店や会社で行うサービスは商売なので、基本的には料金に含まれるものですが、お客様がお困りになられていることにちょっと対応したり、気を利かせて少し何かをしてあげるということは、料金に含まれることではないかもしれません。生産性の観点からすれば無駄なことかもしれませんが、困っている人がいたら助けることは、人として当たり前のこと。しかし、こうしたちょっとした行為をしてくれると人は喜び、心に残ります。無駄なことかもしれませんが、積み重ねていくことで、地域の中できっと「信頼」という財産になっていくのはないかと思います。顧客数や売上は「見える資産」。顧客からの信用や信頼は「見えない資産」。成果が出ないと商売はできない、しかし、後者もなくなればあっという間に倒産します。
そんな見えない資産を高め、見える資産を増やし、生き残ったお店が東京町田にあります。「でんかのヤマグチ」。昔ながらの家電専門店として地域で50年以上商売を続けているお店ですが、一時、もはや倒産か、という大きな危機がありました。店の近くに大型家電量販店が立て続けに出店してきたときです。売上は毎年3割も減少、億単位の借金が増え、このままでは商売を諦めるしかないという状況でした。その時考えたのは、安さで対抗しても勝てる訳はない。利益は商売で不可欠なこと。ならば、利益を確保して生き残る「高売り」という道を行こう。本来地域密着、人間関係が地域店の強み。お客様に寄り添った商売をしてきたので、地域の事情をよく知っていました。高齢者が買い物に行けない、新機能についていけない、孤独で困っている・・・そこで、顧客にもっと寄り添っていこうと、商圏をあえて3分の1に絞り、訪問回数を増やし、お客様にもっと徹底したサービスをする。親切な店ということで評判になれば、きっと安売りに対抗できる。そこから、電球が交換できないという声を聞くとすぐに駆け付ける、旅行に行く間、新聞を預かってほしい、大雨で買い物に行けないので買い物をしてくれないかなど、高齢者の小さなお困りごとに、できるだけ応えていこうとみんなで努力を続けてこられました。ただ、こうした小さな親切はすぐに売上につながるものではありません。しかし、何年も何年も、お店のみんなで続けていきました。確かにそんなことをしたところですぐに売上が増えません。しかし、コツコツとやり続けていくうちに、次第に地域の中で「確かに値段は高いけど、どうせ家電を買うならヤマグチがいい」という評判が広がっていったそうです。量販店がいくら安く売っても、ヤマグチは一切値引きはしない。結果として粗利益は25%から35%に上昇。見える資産も確実に増えています。店に対する信用・信頼という見えない資産は積み重ねでしか生まれませんが、地域で商売をしていくために、高め続けるべき大事な資産だと思います。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上 働きがい・やりがいの向上
2025 年 10 月 23 日 13:00
挑戦の場と安全の場
先日、務めていた会社を辞めて自分で起業し一年たった30代の若い経営者の話を聞く機会がありました。起業当初から相談に乗っていたのですが、目標を持って挑んだものの、この一年、何度も壁にぶつかってうまくいかないことが山のようにあったそうです。しかし、壁を乗り越え続け、この一年を振り返ると、出来ることが増えたことはもちろん、何より仲間への感謝や仕事への考え方など、自分の成長も実感したと話をしていました。一皮むけたその様子を見ると、自分で選んだ道とはいえ、自分で目標を立て挑戦していくことは、プレッシャーが大きくても人としての成長につながる大事な機会だと感じました。
一方、最近、人手不足の中で、若手の育成に変化が起きていると聞きます。無理をさせると人が辞めてしまう。ノルマの廃止に踏み切ったり、できるだけ負荷を与えないなど育て方を変えている企業が増えているそうです。確かにプレッシャーが少ない職場は気持ち的も楽なのかもしれません。辞める人も少なくなるのかもしれません。しかし、そうした職場を若い人は望んでいるのでしょうか。ノルマやプレッシャーが嫌で会社を辞めていく人もいる一方で、最近、プレッシャーが少ない会社でも、「このままこの職場で働き続けても成長できない」と転職する若者も増えているということも聞きますが、挑戦もない、ゆるい会社は楽ではあっても楽しくはない。挑戦して成功や失敗を経験しなければ、成長もありません。
人が成長する職場とはどのような職場なのでしょうか。先日、全国的に優秀な営業成績を出し続ける優績スタッフが次々と育つ、ある地方の会社を取材させていただきました。全員が高い目標に挑戦する厳しい環境にも関わらず、ここ数年離職者はゼロ。1年目は先輩の指導を受けながら営業を学んでいきますが、2年を過ぎるころには、ほとんどの人が自律的に働き、優秀な営業スタッフに育っていくといいます。さぞ厳しい上司がいるのかと思うと、そういう人はいません。その職場で昔から受け継がれてきたのは、高い目標に挑戦することはプレッシャーも大きく大変だけど、その中で必ず人として成長できるという成功体験。成長を実感した先輩が、今後は背中を押す役になり後輩の成長を支えます。「辛い時に先輩に声をかけてもらったことが励みになった」「悩んでいる時、先輩が相談に乗ってくれたことが成長につながった」。そんな成功体験が受け継がれています。高い目標に挑戦するシビアな環境でありながらも、職場ではみんなが支え合っていくので誰も孤独にならない。それがやる気の源泉になっていると言います。優しいだけ、甘いだけの職場では人は育たない。厳しいだけの職場でも続かない。厳しいけれど、困った時に何でも聞ける職場だからこそ頑張れるんだと若いスタッフが話されていたのが印象的でした。成長には、高い目標に挑戦することが不可欠ですが、同時に支え合う仲間も必要。成長するための挑戦の場と、信頼しあう仲間がいる安全な場。そんな両輪が混在している職場が、成長できる職場なのではないでしょうか。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 素晴らしい組織風土づくり
2025 年 10 月 14 日 17:08
人として当たり前のことをする
創業してもすぐに倒産してしまう企業が多い中、日本には創業何十年という老舗企業があります。地域に根差した建設業、地域から愛され続ける小売業や飲食店。地域に住む人から「あそこなら、あの人たちなら間違いない」と言われる絶大な「信用・信頼」があるからこそ、永く商売が続けられているのだと思います。しかし、信用・信頼は一度失えば、一瞬で壊れるもの。一朝一夕にできるものはなく、小さな積み重ねによってしか得られないものだと思います。どうすれば信用・信頼を作り出していけるのでしょうか。
例えば、お客様や協力会社と交わした小さな約束。たとえどんなに小さな約束であってもしっかりと守る。そして仕事を任せるとみんなが真面目に一生懸命に取り組む。また、お客様も見ていなくても、心をこめ、期待以上の仕事をする。地域に信頼される企業の活動を見ていると、行動の判断軸は、人としてどうあるべきかという、人間の軸を基本にしているような気がします。
取引先だから、お客様だから一生懸命にする。マニュアルで決められているからそれを遵守するというような外部の基準ではなく、人としてどうするのがベストなのか。人と人の関係でも同じなのかもしれませんが、人としての当たり前を基準に行動している企業が地域から信頼され続けているように思います。いい職人さんほど、見えないところまで手を抜かずに仕事をされますが、そうした姿勢も同じことかもしれません。
先日、家族と一緒にあるお店で買い物をした後、車を停めていた、少し離れた場所の店の提携駐車場に戻った時、駐車料金の精算がうまくいかず困りはて、お店に戻って店員さんに事情を説明したところ、接客中に関わらず、わざわざ駐車場まで来て問題を解決してくれました。家族も感動していましたが、これは些細なことかもしれませんが、こんな小さな行動が、この店がいい、この店にしようという信用・信頼につながっていくような気がしました。
昔から日本には、「誰も見ていなくても、おてんとうさまがみている」という考え方がありますが、自分の心に正直であることが、信頼を築いていくうえで、いちばん大事なことかもしれません。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2025 年 10 月 02 日 10:29
壁は扉になる
通勤中に通るお寺の門に掲示板があり、毎月「いい言葉」が掲載されています。以前、その掲示板に「壁は扉になる」という言葉が張り出されていました。
仕事でも経営をする上でも、何かを成そうとするときには、必ず壁が表れます。簡単に乗り越えられる低い壁もあれば、超えられない大きな壁も出てくることがあります。大きな壁が立ちはだかった時にどんな行動をするかはその人の判断ですが、大きな壁の前に立つと、つい諦めたり、弱音を吐いたり、別の道を探そうとしがちです。
しかし、「乗り越えられない」というのは自分の決めつけであって、もしかするとその壁は開くことができる扉かもしれない。何とか乗り越えようと努力していると、知恵や実力が付き、そこから新しい展開が生まれることがありますが、それが「壁は扉になる」。言葉の解説はありませんでしたが、壁のとらえ方を考える言葉だと思います。
先日、昭和の時代から、社員の幸せを第一に経営されてきた経営者のお話を伺う機会がありました。当時、社員は使い捨てのような風潮もあり、その上その業界は特に不人気業種。なかなか人が集まらない状況の中で、企業の成長には「人」が全てだと、自分自身が採用の最前線に立って取り組まれたそうです。なぜ、不人気なのかを徹底的に考え、自分自身で応募者の前に立ち、一人ひとりに手紙を書き、理念に共感してくれる人を採用だけを採用する。その創意工夫の総量はすさまじく、まさに壁をどうとらえるかを教えてくれているようなお話でした。今、その当時採用した人財は経営者や幹部になって会社を支えられているそうです。
超えられそうにない壁を前にすると「解決策がわからない」と愚痴が出そうになります。無理だ、出来ない。しかし、先ほどの経営者は冷静です。解決策がわからないのは、問題がわからないのではないからだ。そう考え、どこに問題があるかを考えます。考え抜いた上で、引いたり、押したり、創意工夫をし続ける。時間がかかるかもしれないけれど、そうする中で必ず解決策が見つかる。そのプロセスで知恵も能力も高まる。その後はスムーズに扉を自由に出入りできるようになる。それが「壁は扉になる」ことなのかもしれせん。
そもそも壁というのは、とらえ方であるとすれば、壁は扉だととらえていけばいいのかもしれません。これは扉なのだと決める。どこかに開く鍵がある。経験したことがないのだからすぐに解けるはずがないと考える。そういう視点で向かえばやる気もわいてきます。理想が高いほど壁ができますが、壁は扉です。
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方
2025 年 09 月 22 日 16:44
先義後利
お客様が求めるからといって、何でも無料ですることは無駄ではないか。これは誰もが思うことだと思います。提供したサービスに対してお客様が対価を払ってこそビジネスは成立する。これはきっとビジネスの常識です。しかし、この常識にそったやり方で本当に商売が成立しているのかというと、そうではない気がします。
例えば、雨の日に荷物を持ったお客様が駐車場に向かわれた。それに気づいた一人のスタッフがお客様に駆け寄り、傘を差しだして車までお送りしてあげた。こんなサービスは普段の商売の中でもよくあります。こうしたスタッフのサービスは、決して利益を生み出していないかもしれません。ビジネスとすれば無駄ともいえます。しかし、こうしたスタッフの気遣いは、きっとお客様の心に残り、「また利用したい」と思ってくださるかもしれません。利益を忘れて、思わず行った行為が、結果として自分の利益としてかえってきたということは、人生の中でもあることだと思います。
こうした姿勢を表す言葉として、「先義後利」という言葉があります。これは中国の儒学・荀子に登場する言葉で、「利益より、人としての道義、義理を最優先にしていれば、利益は後から勝手についてくる」という意味です。日本では300年前に呉服店として創業した百貨店・大丸の創業時の経営理念としても有名です。
ただ、最近は何でも結果が求められる時代です。人としての道義や義理などの理想のようなものを優先して、コストはどうなるのか、商売は本当に成り立つのかと思う人も多いかもしれません。ただ、この先義後利を商売の姿勢として実践している企業は全国各地にあり、そして、そうした企業は着実に発展しています。
名古屋にある「レクサス星が丘」。お客様満足の高い店として有名ですが、創業時から、「お客様への価値づくり」を理念とし、お客様本位の商いを続けてこられました。先日、お店を訪問させていただき、創業時の話を伺ったのですが、このレクサス店でさえ最初の5年間は赤字続きだったそうです。しかし、それでもお客様に価値を提供しようと、困っておられるお客様がいれば、それに応え、不便な思いをされているお客様がいたら、みんなで考え改善する。判断軸は「人としてどうしてあげるとよいか」。利益以上にお客様本位に商いを続けてこられました。当初は赤字が続いていましたが、こうした商いを続けているうちに、少しずつファンが増え、販売も伸び、開業20年目の今年になって管理顧客は全国平均の3倍にもなっているそうです。「我々にとって台数は標ではない」と言っておられましたが、お店の姿勢が少しずつ地域のお客様に伝わり、「あの店はいい店だ」という信頼につながっているのだと思いました。
世の中には自分のこと以上に相手のことを考え行動する人がいます。そうした人に感謝や信頼が集まって、結果的にその人も利益が渡る。先に人に与える。喜びを優先する。先義後利は、不変の原則なのかもしれません。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 09 月 11 日 11:02
成功の理由
世の中には、「こうすれば上手くいく」というようなメッセージで「成功事例」や「成功ノウハウ」があふれています。「これをやれば売上が上がる」「これをやればお客様が増える」と言われると、つい気になって見てしまいますが、実際に飛びついてやってみたら、うまくいかなかったという声もよく聴きます。
他人が成功した事例は、一瞬「近道」のように感じます。しかし、それがどれだけ良いノウハウに見えたとしても、自社に落としていくまでにはいくつもの壁もあるでしょうし、やり始めたとしてもすぐに成果は出るようなものでもない。成功ノウハウは、継続してやり続けることで、初めて成果が出るものだと思うのですが、「これは近道だ」「儲かるぞ」と思ってスタートした人は、少し上手くいかないと、「成果が出ない」と途中で諦めてしまいます。「手っ取り早く成功したい」という楽な道を選ぶ考え方自体が成功を妨げる要因になっている場合もあります。
先日、デジタル集客で成功している、あるタイヤショップの経営者のお話を伺う機会がありました。このお店はSNSを通して様々な発信をして集客につなげているということで、そのノウハウを教えていただいたのですが、そもそも、こうした取り組みを始めたのは、ある時、経営に行き詰りお店をやめようと思っていた時に、先輩の経営者から「やり続けてもいないのに諦めるのか」と言われ、自分の甘さに気づいてから、お店の発信を毎日続けることにしたそうです。お客様とのやり取りを発信したり、お店の思いを伝えたり、試行錯誤をしながらその発信は10年も毎日欠かさず続けられたそうです。それがようやく花開き、全国から注目を集めるお店となっています。
確かに成功のノウハウ(やり方)は、原理原則、黄金の法則なのかもしれません。お客様の声を毎日発信する。お客様のコメントに丁寧に答えていく・・・言葉にすれば簡単なことですが、実際のお店では、忙しい時もあれば、人手不足でやれない時もある。内容が枯渇することもある。そのような状況でもいかに毎日続けていけるか。それを実行する人に「強い思い」がなければ、絶対に続いていかなかったと思います。
「やり方」を知っていることと、それを「やり続ける」ことは同じではない。成功事例やノウハウが世の中にあふれているのに、なかなか成功事例が広がっていかないのは、そんな理由もあるのではないでしょうか。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上
2025 年 09 月 04 日 10:57
お客様が本当に欲しいもの
「人々が本当に欲しいのは、4分の1インチのドリルではなく、4分の1インチの穴である」
これは、マーケティングの有名な言葉ですが、なかなか奥が深い言葉だと思います。
ドリルを買いに来られているのだから、お客様が求めているのはドリルだと思ってしまいますが、本当にお客様が求めているのは「穴」。ドリルを買うのは「穴をあけるため」であって、ドリルを所有することが目的ではない。お客様が本当に叶えたいニーズは「穴」だという意味です。この考え方は、営業や接客をしていくうえで大切なヒントを与えてくれます。
普通、もし「ドリル」を求めて来店したお客様がいるとすれば、求められているのはドリルなのだから、電動工具売り場を案内しよう、商品の違いを説明しようというのが普通の流れ。しかし、本当にお客様の立場に立った接客をしようとするならば、案内する時に、どこに穴をあけたいのか、なぜ穴をあけるのかを聞くことからはじめるべきなのかもしれません。穴をあけたい本当の目的をしっかり聞くことができたとしたら、もしかするとドリルを買って、わざわざ穴をあけなくても良いという提案ができるはず。ドリルの販売機会は逃すことになるかもしれませんが、それ以上にお客様は喜んで帰られるはずです。
紳士服店の場合でも、「スーツが欲しい」と来店されたとしても、本当に求めているのは「スーツ」というモノではなく、「大事な面接で自信を持って臨みたい」「取引先に信頼感を与えたい」といった成果だとすれば、本当に買いたいものは、新しいスーツで得られる満足や幸せなのだと思います。お客様の本当の目的やその背景を理解して、ふさわしい提案をすることで、商品以上の満足を提供できるのではないしょうか。
営業や販売はつい売ることに目が向き「商品の説明」をしようとしてしまいますが、商品の詳しい説明よりも、お客様の目的に応える提案の方がお客様は求めていると思います。「ドリル」ではなく、「穴」(本当に求めておられるもの)に目を向ける。接客や販売だけでなく、職場の中での依頼ごとなど、どんな場面においても大事なことかもしれません。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上
2025 年 08 月 26 日 10:04
リーダーシップは影響力
ビジネスで「リーダーシップ」というと、しばしば「権限」や「地位」と結びつけて考えられがちです。しかし、いくら肩書きが立派でも、人の心を動かせなければリーダーシップは発揮されません。逆に、肩書きがなくても、周囲に良い影響を与える人は、立派なリーダーと言えるのかもしれません。
リーダーシップとはどんなことなのでしょうか。
以前、リーダーシップについて、このような話を聞いたことがあります。ソニーの創業者である井深さんが社長の逸話です。
ソニーの厚木工業は、当時最新鋭の設備が設置され、世界中から見学者が来られていたのですが、井深氏が問題だと思っていたのは「トイレの落書き」だったそうです。井深氏は「会社の恥だから」と工場長にやめさせるよう指示を出し、工場長も徹底して通知をしたのですが一向になくならなかい。「落書きをするな」という落書きまで出てくる中で、井深氏も諦めていました。
しかし、しばらくしてから、工場長から「落書きがなくなりました」という連絡がきました。「どうしたんだ?」と尋ねると「実は、パートできてもらっている掃除の女性スタッフが『落書きをしないでください。ここは私の神聖な職場です』と書いてトイレに張ったのです。それでピタッとなくなりました」ということでした。井深氏は、「この件については私も工場長もリーダーシップをとれなかった。パートさんに負けた。」と言われたそうです。そこから「リーダーシップとは上から下への指導力、統率力だと考えていたがそれは誤りだ」と悟り、それ以来、リーダーシップを「影響力」と考えるようにしたそうです。
社長や工場長という権威のある人がいくら言っても動かなかったことが、ある人の一言で動き出したという例ですが、影響を与えるものは、肩書だけでないということがわかります。何が影響力になったのか。
このスタッフは、きっと日ごろから真剣にトイレ掃除し、皆さんから信頼されていたと思います。「ここは私の神聖な職場」というくらいに、毎日一生懸命仕事をされていたからこそ、その人の言葉にみんなが影響を受けたのだと思います。
権威や力で人を動かすことでなく、「この人と一緒にやりたい」「この人の考え方についていきたい」というものが「影響力=リーダーシップ」だとすれば、この力の源泉にあるのは、その人の人間性と行動の一貫性なのかもしれません。
確かに、いつも率先して明るい挨拶をする人、誰かが困っていると、いつも声をかけ助けようとする人がいると、その人はみんなから信頼され、何かやろうとした時に、「この人なら」とついていこうという気持ちになります。逆に言葉で良いことを言っても、日ごろ何もしていない人には、ついていきたいとは思えない。「リーダーシップの発揮」と言われると、メンバーにスピーチをしたり、派手な行動と思いがちですが、本当の「影響力」とは、誠実な心で行う日常の小さな積み重ねなのかもしれません。何れにしても、リーダーシップは、リーダーだけのものではない。「みんながリーダー」の時代だと思います。
カテゴリー :
これからの時代の人財育成
2025 年 08 月 19 日 14:11
お客様第一とお客様中心主義
昔から、「お客様第一」という言葉がありますが、実際にそれを実現するのは、なかなか難しいことです。お客様第一は“目の前のお客様”の希望や要求を中心に据え、ときに個々の要望をすべて受け止めよう”という意味になると思いますが、実際にこれをやろうと思うと、顧客対応にバラつきが生まれたり、やればやるほど現場に負担がかかっていきます。何でもかんでもお客様の希望に沿おうとすることが、本当によいことなのでしょうか。
大阪に患者様本位の医療を貫き、多くの患者様から支持されている歯科医院があります。名前はヨリタ歯科クリニック。都市部から離れた東大阪という町にありながら、一般の10倍、1日200人もの患者が来院する歯科医院です。医療界は国の制度があるために、差別化が難しい業界です。宣伝も禁止されています。しかし、この医院を体験した患者の口コミが広がり続け、年々売上が伸びています。
なぜ、こんなに人が集まるのか。それは、この医院が創業以来、徹底して患者様中心に医療を考え、それを形にしてきたからです。
一度歯を削ると、何年かたって、またそこから虫歯になったり、詰めものが外れてしまうことがあります。「歯を削れば削るほど、虫歯を増やすことになる」。院長寄田さんは、創業の頃、「年々歯科の技術は進んでいるのに虫歯が減らないのは、歯科のあり方が抜本的に間違っているからだ」ということに気づきました。
患者様に本当に喜ばれる歯科をつくるには、「歯を削らない医院」をつくるしかない。そこから予防歯科をクリニックの中心におき、患者様本位の医院を作り出されていきました。いきなり治療するのではなく、治療前にしっかりとカウンセリングをする。患者様とのコミュニケーションに時間をとり、歯に関する不安や悩みをしっかりと聞く。患者様に代わって、患者様が求める歯科医院を実現しようとされたのです。
しかし、歯を削る行為には国から報酬が支払われますが、どれだけカウンセリングをしても、それで儲けはでません。それでも、それが「患者様が求める歯科」だと、患者中心を追求し、それが次第に評価されて今の実績になっていきました。
この医院が貫いてきたのは、「患者様本位、お客様を中心に考える姿勢」です。「患者様第一」は、患者の無理な要求にも答えるようなイメージもありますが、この医院は、それをしません。例えば「カウンセリングなんていらないから、急いで治療してほしい」という患者がきたら、その人には違う歯科を紹介する。あくまでも、この「削らない治療」の方針に共感してくれる人をイメージして医院を作っておられます。何でも患者様の言うことを聞くわけではないようです。定義がある訳ではありませんが、お客様が欲しいというものを、その通りに提供する「顧客第一主義」と、「お客様にとって何が大事なのか」と顧客に変わってあるべき姿を考えていく「お客様中心主義」は、根本的に違う気がします。
例え儲からなくても、初診でしっかりとカウンセリングをする。むし歯にならないように健康相談にのる。最近も歯科医院に通えない高齢者のために何かしてあげたいと訪問治療をはじめられましたが、「お客様にとって何が良いのか」とお客様を中心に考える姿勢は、歯科業界の常識を覆すサービスもたくさん生み出しています。プロとして「お客様中心」で考えていくことは、お客様さえも気づいていないニーズにも答えることにもつながっていくのかもしれません。
顧客の目の前の要求に答えることではなく、お客様にとって何がいちばん大事なのかをいつもセンター(中心)に置き、それをプロとして実現する。お客様中心の経営が、今こそ、大事なことなのかもしれません。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2025 年 07 月 29 日 10:11
可能性の蓋
先日、30代前半ですが海外で仕事をしている若い方たちと話をする機会がありました。その人はこれまで一度も日本の企業に就職したことはなく、すべて自分で道を切り開いていく生き方をしておられます。事業に必要な技術や知識はすべて独学で学び、海外に行きたいと思えば語学を学び、決して安定の道を進むのではなく、失敗をしながらも自分のやりたいことに挑戦を続けています。
よく「自分の能力はこんなものだ」と現状に縛られ、自分成長をあきらめてしまう人も多い中で、その人は「やってみてから考えればいい」「できないことはない」と自分の可能性に限界を設けていません。なぜ、そういう考え方や生き方になったのかと聞いてみると、両親の姿を見てきたからだと言います。子どもがやろうとすることを決して否定しない。自分のやりたいことをやってみたらいいという育て方をしておられます。それ以上に両親自身が、そのような生き方をしている人達なので、自然とそう考えるようになったということでした。心配のあまり、子どもに対して「お前には無理なんじゃないか」「リスクがあるからやめた方がいいのではないか」と育てる人も親もいると思いますが、その両親は、子どもが小さな時から、人に迷惑をかけないこと、人に感謝することなどの「人の道」の基本は厳しく教えるものの、それさえ外さなければ、何でもやらせてくれたそうです。
企業の中での人材育成においても、同じかもしれません。この人の能力はこうだと決めつけている上司もいます。失敗をさせないように事細かに指示をして人を動かす人もいます。親がつい子供に失敗させたくないからと、親の過去の経験や価値観を押し付けてしまうことがあると思いますが、それが子どもの自信や自分の可能性を信じる気持ちを奪っていることもあります。企業においても、良かれと思って指示をする、アドバイスをする。しかし、それが逆に可能性の蓋を閉ざせてしまっているのかもしれません。
最近、若い人が挑戦しない、指示通りにしか動かないという悩みを聞きますが、本当にそうなのでしょうか。可能性を信じて軽々と未来に挑戦する若い世代の話を聞くと、そうなってしまうのは若い人の問題ではなく、若い人の可能性を信じない、任せようとしない、挑戦しようとする気持ちを抑えつけてしまう親や上司側の問題かもしれないと考えてしまいます。もし、職場で若い人が辞めていくとすれば、上司の姿から可能性を感じられなくなってしまっているのかもしれません。
先ほどの人は、今の時代はやろうと思えば何でも情報が手に入るから、人に教わらなくても独学で何でもできるんだと話していました。教えてくれる上司が一人もいない状況でもどんどんと成長しているようです。教えないと人は育たないと、過去の常識に縛られているのは、もしかすると私たちの方かもしれませせん。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2025 年 07 月 23 日 11:25
成果がやる気を高める
よく、人のやる気をいかに高めるかという話をする機会がありますが、人のやる気がいちばん高まるのはどんな時でしょうか。人に褒められる。給料が上がる。それは確かに嬉しいし、やる気も出ます。しかし、いちばんやる気が高まるのは、自分の努力が実った時ではないでしょうか。努力を重ね、それが成果となって表れてくる。努力が実った時の喜びは何事にも代えがたい嬉しさがあります。
しかも、努力の過程が厳しい時ほど、成果につながった時の喜びは大きい。難しい仕事を一人でやりきった、高い目標をなんとかクリアした。自分を振り返ってみても、そんな成功体験が自信になり、やる気を高め、その後の仕事へのやる気に大きく影響してきたように思います。
しかし、問題は簡単に成果が出るまでの期間。努力の過程には、もうまくいかない時もあり、くじけそうになります。そこで諦めるか、続けるか。誰か助けてもらうのは簡単ですが、それでは達成感は半減する。苦しさを乗り越えてこそ喜びが跳ね返ってくるとすれば、自分自身で苦労するしかありません。頭でわかっていても、これがいちばんしんどい。特に最近の若い人はすぐに成果に結びつかないことはやろうとしない傾向にあります。しかし、苦労を乗り切らなければ成長はないのは事実。こういう時こそ、その人を取り巻く環境が大事なのかもしれません。
以前、ノルマが厳しく、それについていけずに辞めていく人が多い「営業」の現場で、なぜかある営業所だけ人が辞めず、若い営業スタッフがどんどん成長するという、ある地方の営業所を取材したことがあります。目標が低いかというちそうではない。他の営業所と同じく高い目標が与えられています。しかも、その営業所は全国レベルの営業成績を残す優績者を多く輩出するレベルの高い営業所。数字への意識が高い職場なのに離職者はゼロ。何が違うのでしょうか。
1年目の新人の指導に違いがあるようです。優績者ほど、成果を出すまでに行う苦労の大事さを知っています。「この仕事の本当の喜びは、努力を重ねた向こうにある」と知っているこうした先輩が新人を教えていくのです。新人はすぐに成果が欲しいと思う。しかし、成果が出るまでには時間がかかるし、苦しさが必要。そこをあきらめずにやっていけば、成果につながるということを様々な先輩が代わる代わるに教えていくのがこの営業所の特徴です。そして1年後、ほとんどの新人が目標を達成します。「成績を出せ」と迫るでのはなく、努力し成果を出すことの喜びを体験させていく。それがやる気や自信につながり、努力をして成果が出る喜びを知った2年目以降は、今度、自分が後輩にその文化を伝えていくそうです。
最近、やる気を高めるには褒めることが大事だということが言われていますが、人が本当にやる気が高まるのが「自分の努力が実った時」だとしたら、いかに努力をさせるか、成果が出るように支えていけるか。この視点も同時に大切なことかもしれません。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2025 年 07 月 15 日 13:28
厳しさは愛情の裏返し
最近、「パワハラと言われそうで怖い」と、部下への指導をためらう上司が増えているそうです。
確かに、ハラスメントに対する社会の意識が高まり、注意や叱責がトラブルにつながるケースも多くなっています。しかし、人が成長していくためには、外側からのフィードバックは必ずいります。上司がそうした恐れから、本当に必要なフィードバックまで避けてしまっては、社員の成長も、職場の成長も失われてしまうのではないでしょうか。
以前、ある会社の社員の方が、新人の時に、自分が行った仕事の準備や完成度が低く、その時の上司から「お前はこの仕事に本気で向き合っているのか」と厳しく叱られたと話をされていました。その人にとっては、涙が出るほど悔しかったといいますが、それがきっかけで徹底的に準備をする姿勢が身についたと言っておられました。今、その人が若手を指導する立場になり、あの時の上司の姿勢を思い出すそうです。「あの時の厳しさが自分を変えてくれた」と振り返っておられました。考えてみれば誰にでも、このような「厳しさが自分の糧になった」という経験があるのではないでしょうか。
しかし、部下に「否定と受け取られたらどうしよう」と不安になり、ミスがあっても笑って済ませたり、あいまいな助言しかしない上司もいます。そうした職場では、部下がいつまでも成長せず、「自分はここで成長できるのだろうか」と悩む若手が増えているということも聞きます。しっかりと指摘してほしいという人もいるはずです。
「厳しさ」とはどんなことでしょうか。いい会社を取材していると、人に優しい文化だけでなく、こうした厳しい文化が必ず共存しています。本当の「厳しさ」とは、怒鳴ることでも、感情をぶつけることでもないはず。相手の将来を本気で考えるがゆえに、伝えにくいこともあえて言う。愛情があるからこそ、言いにくいこともいう。それが「本物の優しさ」であり、信頼される上司の姿なのかもしれません。
しかし、実際は厳しくすることは難しい。でもどれだけ難しくても、パワハラと指導の違いを見極め、逃げずに向き合う。その厳しさこそが、職場を強くし、人を育てる力になるような気がします。
カテゴリー :
これからの時代の人財育成
2025 年 07 月 02 日 11:55
お客様本位と効率性
先日、地元の友人が、ある飲食店について「あの店はすぐにお皿を下げに来て、ゆっくりできない」と対応について不満をもらしていました。お店としてもさすがに「早く帰ってほしい」という気持ちはないと思いますが、お客様からするとすぐに皿を片付けに来られると、何かせかされているような気持ちになります。
お店の側は、早く皿を下げて片づけたい。回転を速くして効率を上げたいという気持ちがあるのかもしれませんが、その効率優先のたったひとつの行為でお客様を失ってしまっているのだとしたら本当に勿体ない。さらに、こうして悪い口コミが広がってしまうのは、本当に残念です。
効率を優先する、しないということで思い出すのは、以前DOIT!でご紹介した川越胃腸病院です。取材中、看護師さんが患者様の検温のために各部屋を回るシーンがありました。しかし、その看護師さんはある部屋で患者様が寝ておられるので「このまま寝かせてあげようと」、やるべき検温をせず次の部屋に行かれます。検温しないともう一度来なければなりません。効率で考えると患者を起こして検温をした方が良いはずです。その看護師さんは「この病院の方針は、あくまでの患者様本位。そっとしておくことが本当の看護であって、寝ている患者を起こしてまで検温をするのは、看護ではないと教えられているんです。」「これまで勤めていた病院では、決めら仕事をしてこないで帰ると怒られたけど、この病院は誰も怒らない」と話してくださいました。
検温を後回しにするのは、二度手間で不効率な行為。しかし、この病院はあくまでも患者様が優先。もちろん経営なので効率も大事にされていますが「お客様の幸せが病院の理念」であると、たとえ手間が増えたとしてもお客様の満足を優先する。どこまでいっても基準はお客様の満足です。
そもそも「生産性」という言葉は工場などで使われる言葉。しかし、サービス業で生産しているものは「お客様の満足」であるとすれば、患者様を起こさないであげる方が生産性は向上していると言えます。最初の飲食店のように、小さな手間を惜しんで生産性を上げることは、本当の意味では生産性を上げていないのかもしれません。自分の会社が生産しているものは何か?私たちの会社でも、生産性の名のもとで、少しの手間を惜しんでお客様を不快にさせてしまっているようなことをしていないか、もう一度見直してみようと思います。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 働きがい・やりがいの向上
2025 年 06 月 11 日 12:13
心がこもる仕事
売り手の都合ではなく、お客様のニーズを把握し、それに応じて対応していくことが、顧客志向のマーケティングの基本と言われていますが、お客様のニーズを理解するということは、言葉でいう以上に難しいことだと思います。
例えば「食事」というニーズでも、さっと済ませたいと思うニーズもあれば、家族でゆっくり過ごしたいというニーズの時もある。友人との食事か、ビジネスでの食事か、一緒に行く人によってもニーズは違います。
また、例えば、空港を利用する時なども、仕事で利用する時と、休みの日に遊びで利用する時では、空港に対して求めるサービスが違います。年齢、性別、老若男女といろんなお客様がいますが、その一人のお客様の中にもいろいろなニーズがある。お客様のニーズを理解するというのは、理論で言われるほど簡単なことではないのかもしれません。
お客様として企業のサービスを利用する時は、「もっと、気を利かせてほしい」とイライラすることはたくさんあります。しかし、サービスを提供する側にたってみれば、会社から言われたことをするのが仕事だと考えるスタッフもいるでしょう。「自分の業務、自分がやること」に目が向くとお客様のニーズには気が及ばない。
お客様が「急いでほしい」と焦っている時に、マニュアル通りにゆっくりと対応をされたり、「今日は家族でゆっくり話をしながら食事をしたい」と思って食事をしにきたのに、話をさえぎるように、勝手に料理の説明をしてしまう。お客様の不満はこんなところから生まれていきます。こうしたことは「小さな不満」ですから、お客様もあえて声に出しませんが、つもり重なれば「この店はもう利用しない」と思う人もいるはず。スタッフがお客様に目を向けているかどうかは、お店の業績にもつながっていくことなのかもしれません。
逆に、同じ状況であっても、お客様に気遣いができる人もいます。時計を気にしているお客様を見つけて、「お急ぎですか?」と声をかけてくれるホテルのフロント。グラスに入っている水の「なくなり加減」を常に観察し、お客様から声をかけられる前に、グラスに水を注ぎにいこうとするレストランのスタッフ。サービス業だけでなく、お客様のことに目を向け、相手の気持ちを察した行動する人は、いろんな業界にいます。
こうした人たちの仕事には、その人の「心」を感じます。ただ、決められた仕事を決められた通りにしている人か、お客様に喜んでほしい、いい仕事をして役立とうと思いながらやっているか。心の姿勢は、小さなところに現れていくものなのかもしれません。
「心」がない仕事と「心」をこめる仕事は、作業の内容や見た目はそんなに変わらないのかもしれませんが、相手の心に与える影響は大きいはず。どちらの心で仕事をしていくか。もし、自分がお客様だったら、どちらで買い物をしたいか。答えは明白です。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 06 月 03 日 17:21
体験に勝る気づきはない
過去を見て考えるのではなく、未来のありたい姿から今を考えていくことが大事だと言われていますが、確かに自分たちの目標やありたい姿を明確になると、現状の課題も見え、やるべきことが見えてきます。組織のありたい姿、サービスのありたい姿。抽象的でぼんやりしていたものが明確になれば、全員で目指していけます。
自分たちより優れた組織や相手を見つけ、そこを基準にして近づけるために見学に行くことがベンチマークですが、実際に体験すると気づきが生まれます。例えば、リッツカールトン・ホテルのように、お客様を感動させるおもてなしに近づきたいと思ったら、実際にホテルに宿泊し体験をしてみる。社員が自律的に働く組織が目標ならば、そうした組織を訪問し体験する。本でも会社の業績や規模、事業内容などはわかりますが、社風やおもてなしのレベルなどは、実際に行って、自分自身で感じてみないとわかりません。
以前、自社の経営に悩んでおられた経営者が、社員がいきいきと働く組織の見学会に参加し、自分の目の前で、いきいきと自律的に働く社員のレベルに感動し、そこから、その会社が目標になり、そして経営の方向を変え、業績を回復させた方がおられましたが、比較するものや目標が定まってくると、行動がはっきりしていきます。
顧客に対する「接客」に関しても同じかもしません。一流に触れてみると自分たちとの差がわかります。私は、以前、おもてなしレベルが高いある有名な高級ホテルを知り、その接客を体験したいと、家族で食事にいったことがあります。しかし、妻も子供も高級店の雰囲気になじめず、礼儀正しいスタッフに少し緊張していました。すると、そんな私たちの雰囲気を感じたスタッフが、何かを察したのか、それ以降のサービスから、その人はもちろん、他のすべてのスタッフが一緒になって、私たちを楽しませようと、方言を交えたフレンドリーな言葉で接客をしてくれるようになりました。お客様本位で、かつ臨機応変な対応。これが一流の接客なのかと感動したことがあります。自分自身で顧客のニーズを察し、自分自身で解決策を考える。上司に伺いを立てずに。顧客にとっても社員にとっても気持ちがいい。これが接客の理想だと感動し、それ以来、これが自分の目標、基準になりました。
自分たちの日常の中だけにいると、それが普通になっていきます。しかし、一歩出て一流のサービス、一流の組織など、目指したいものに触れると、自分自身の視座や目標が高くなっていきます。体験しないとわからないことは意外と多いと思います。「ありたい姿」を明確にするためにも、またそれを全員で共有するためにも、やはり、自社の外側を体験していくことは重要なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2025 年 05 月 28 日 11:11
仕事を楽しむ人
これまで、いろいろな会社を見てきましたが、成長し続ける会社は、やはり、社員の人たちが仕事を楽しいと思って働いておられます。楽しいというのは前向きな感情。楽しいから、自分で仕事をよりよくしようとするし、楽しいから勝手に挑戦する。チャレンジすると能力も向上するし、心も向上する。しかし、いい会社で働いている人は楽しそうだということはわかっても、なぜ、仕事がそんなに楽しいのかがわからない。そんな声も聞きます。
楽しく働く方法はわかりませんが、つまらなそうに働いている人にも共通点を感じます。例えば、言われたことだけをやる。自分から仕事はしない。やったらやりっぱなし、振り返りも改善もしない。心を無にしてただ会議に参加する。発言しない。誰かが楽しくしていると待っている。大学の授業もアルバイトもそうかもしれませんが、心も込めず、ロボットのように働くと、絶対に楽しくならないということは、誰もがわかっていることではないでしょうか。
仕事を面白くする方法は、その反対の方向にあるような気がします。言われたことだけでなく、言われたこと以上をやる。仕事の目的を考え、工夫改善し、心をこめる。目標を自分でつくり、自分で挑戦し、やった後に自分自身で反省する。
仕事に「楽しい」「楽しくない」という色分けがあるのではなく、どんな仕事でも楽しくしようとすれば楽しくなるし、つまらなくすることもできる。自分次第でどうにでもできるのが仕事。どんな単調作業でも、ぐっと心を込めれば別のような仕事になります。
「〇〇が楽しい。〇〇を楽しむ。」似たような言葉ですが、少し意味が違います。「楽しい」というのは受動的。この「楽しい」は、周りや人の状況に振り回されることがあります。それに比べて、「楽しむ」は能動的。自分でコントロールしようとしている言葉。自分が「楽しむ」から、自分で「楽しい」ということが作り出せるのでしょう。仕事を楽しむか、楽しい状況を待っているか。選ぶのはそれぞれです。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 05 月 08 日 14:06
GW とウェルビーイング
経済的、物質的な豊かさを追うのではなく、精神的、心の豊かさを追う。ここ数年で「ウェルビーイング」という概念が注目されるようになりました。どれだけ経済的に豊かな都市に暮らしていても、何か満たされない、不幸だとかいう人はいますし、たとえ経済的に貧しい村に暮らしていたとしても、自然を楽しみ、仲間と楽しく過ごしている人もいる。物質的な豊かさが幸せにつながらないのはひとつの事実かもしれません。
企業においても、働く人のウェルビーイング向上が注目されるようになってきましたが、心が満たされているかどうかはどれだけいっても主観的なものであって、周囲がどれだけ「良い会社に勤めている」と言ったとしても、あなたの会社は高い給料が出ているとデータで示されたとしても、その人がそう思わなければ幸せではない。心が満たされているかは本人のとらえ方。ウェルビーイングというのはなかなか難しい問題です。
そんな時、ゴールデンウイークが終わって会社に行きたくない、休み明けに退職者が増えるというようなニュースが目に入ってきました。長期の休暇があって、好きなところに行けるお金もあり、十分にリフレッシュし、戻れる会社も、活躍できる場所もある。客観的に見ると幸せと思える状況にあるはずなのに、休みが明けて働くことになると仕事が憂鬱だ、行きたくないと思ってしまう。どれだけ経済的に豊かであったとしても、それに感謝する気持ちがなければ、決して心は満たされないのかもしれません。
会社が社員のために働く環境を整えたり、良い制度をつくることは大事なことなのでしょう。ただ、それをどうとらえるかはその人次第。幸せかどうかは、幸せを受け止める心の問題だと言われますが、感謝できる人がいちばん幸せなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 04 月 30 日 13:33
利益は影
ビジネスの現場では、つい「利益」を追いかけたくなります。売上、コスト削減、利益率の向上・・。どれも企業経営に欠かせない指標ですが、ただ、忘れてはいけないのは、利益はあくまで「影」にすぎないということ。影は、光と実体があってはじめて生まれます。本当に追いかけるべきは「実体」で、どれだけ追いかけても、影はつかめません。
では、実体とはどんなことでしょうか。それは、「お客様の喜び」「社会への貢献」「社員の成長」といった、目には見えにくいけれど、確実に価値を生むもの。
例えば、あるカフェチェーン。一時はファンも増えていたものの業績が悪化。目先の利益を上げるために原料の質を落とし、人員も削減。一時的には利益率が向上したものの、味やサービス提供が悪化して、ファンが激減。数年後には多くのお店を閉店させる結果になる。こんな話は様々なところで聞きます。
一方で、その逆もあります。ある小さな町の定食屋さん。お店を始めたものの、なかなか売上が上がっていかない。そこで経営者は、お客様の声を一冊のノートにまとめ、日々改善を重ねていったそうです。メニューを少しずつ変えたり、接客の言葉を見直したり、常連さんの好みを覚えたり、派手な広告も、割引キャンペーンもせず、地道にお客様に向き合い続けた結果、10年経っても行列が絶えない人気店になったそうです。
ある町工場の事例。職人がこだわって作っている丈夫な商品。しかしコストもかかり、なかなか売れ行きが芳しくない。しかし、これがお客様のためだと地道に続けていったことで、いつしか買った人から「この商品は壊れない!」という評判が広がり、海外からも注文が入るようになる。
何年も何年も、働く人の心の成長に時間を割いてきた建設会社。続けていくと、見えないところでもいい仕事をしようとするスタッフの「良心」が育ち、地域から信頼を集めるようになり、業績が上がり続ける企業に成長。「実体」を大事にされる企業はいろんな業界に存在します。
お客様に心から喜んでいただく商品やサービスを届けること。社会にとって意味のある存在であり続けること。社員一人ひとりがやりがいを持って成長できる環境をつくること。「実体」に磨きをかけていくことは、短期的に見ると非効率的に見えるのかもしれません。しかし、長い目で見れば確実に影も伸びていく。負うべきものは影でないのは確かなようです。
利益を出すために何をするかではなく、価値を生むために何をするか。この視点こそが、ビジネスを長く、強く育てるために欠かせない考え方だと思います。
カテゴリー :
これからの時代の経営のあり方 働きがい・やりがいの向上
2025 年 04 月 21 日 17:32
比べることの良い面、悪い面
それぞれの会社に新入社員が入ってきています。研修が終わって、これからいろいろな現場で仕事がスタートすると思いますが、仕事をやり始めると、どうしても、できることやできないことの差が生まれてきます。そういう事実がみえてくると、つい他人と比べてしまうことがあります。良くできる人と比べて、なぜ自分は出来ないのだろかと劣等感を感じたり、結果を比較されるとプレッシャーにもなる。なぜ、自分だけがこうなのかと自分の能力を疑ったり、不安も生まれます。それ以外にも、環境や条件を比較して、なぜ、あの人だけ特別扱いなのかと負の感情が生まれたりと、他人との比較はよくないことが起こりがちです。これは新人でなくても、誰でも人と比べることで幸せから遠のいていくことは多い。だからこそ、昔のから、幸せになるには人と比べてはいけないと言われます。
しかし、自分を人と比べることは良い面もあります。頑張る仲間を知ることで、自分の意識の低さに気づく。一生懸命に仕事をする同僚の姿を見て、自分ももっと頑張ろうとやる気がわくこともある。他人と比較することが成長の動機になることがあります。また、他人と接し比べる中で違う価値観があることに気づき、視野が広がる。うまくいっている人のやり方と自分のやり方を比較すれば、自分を成長させることもできます。最近は、過度なプレッシャーが負荷になるからと、個人の業績評価を廃止するという会社もあると聞きますが、ライバルを意識することや、他人と比較して仕事をすることは全てが悪いことではないはず。ただ、やはり、いつも他人のことばかりを気にしていては、自分が正しくみえなくなるのは事実かもしれません。確かに人と比較すれば、できていないことや能力の差が目につくかもしれませんが、過去の自分と比べると、成長していること、できるようなっていることも多いはず。一流のアスリートは常に自分を振り返り、自分を向上させていますが、他人でなく、過去の自分と今の自分という成長の視点で見ている人は、劣等感も優越感もなく平常心で仕事ができていそうです。
比較には、人と競い合う、切磋琢磨しながら人間的に成長できるという面もあれば、間違うと不満や自己肯定感を下げてしまう悪い面もある。比較には両面あるということを理解すること、その人自身が比較をどう受けとめているかが、大事なのかもしれません。新人や若手の育成が難しい時代と言われていますが、良い比較、いい成長をさせてあげたいですね。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2025 年 04 月 08 日 17:43
チームの中の人間関係
先日、毎年毎年、成果を上げ続けているある組織を取材させていただきました。業界が衰退し、全国的になかなか良い結果が出ない組織が多いのに、なぜ成果を出し続けているのか。特別に能力が高い人を集めたという訳でもなく、給料が高いという訳でもない。表面上は他の組織と何も変わりません。何が違うのか。何日も取材していちばん感じたことは、この組織のメンバー同士の人間関係の良好さでした。
「関係性」というのは、目に見えないので、表面からはわかりにくいのですが、メンバーの話を聞いていると、お互いを信頼しあえる、言いたいことが素直に言える、自分の弱い部分もさらけ出せる、みんなが助け合っている・・・というような言葉が次々と出てきます。目に見えないものが、見える結果に大きな影響を与えているのは間違いなさそうです。
確かに、どれだけ優秀な人が集まっても、良い結果に結びつかないことはよくあります。10の能力を持つ優秀な人同士がチームを組めば10以上の成果がでると考えがちですが、いくら優秀な2人でも、お互い嫌いだと、いがみ合っているような状況では、何も進まなかったりします。責任を擦り付け合うばかりで、協力しない。だから結果も出ない。せっかくある10の能力のうちの5しか出さなくなっていることもあります。
しかし、逆にもし能力が5しかない人がチームを組んだ場合でも、そこに良好な関係があり、信頼しあっていれば相乗効果が生まれ10以上の結果を出すこともあります。しかも、そうした良いチームでは、協力しあって働くことでお互いの学びが深まり、最初5しかなかった能力が6になり7になることがあります。頑張ってきた喜びをわかちあえれば、やりがいも高まります。良いチームで働いていると個人も成長する。改めていうまでもなく「関係の質」は、個々の成長にも、チームとしての結果にも大きな影響を与えるものだと思います。先ほどの組織は、そうした良好な関係を、組織の文化としてみんなが大事にされていました。
我々はよく、チームの結果が出ない時に、つい、そのチームメンバーの能力が足りないとか、やり方や行動が悪いと「個人」に目を向けがちですが、能力があっても関係性が悪ければ、それは発揮されません。チームとして良い結果を出したいと思うなら、個人の意識や能力を変えること以上に、チームの中の人と人の関係性をよくすることに取り組むことが大事なのかもしれません。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり
2025 年 04 月 02 日 15:01
やり方とあり方
最近、アスリートがよく「心のあり方」のことを言われます。心の質がプレイ(行動)の質につながり、結果の質にも影響する。個人スポーツの中でもチームスポーツの中でも、自分は何のためにこのスポーツに挑むのか、どうありたいのか等のあり方を深めたり、心が乱れないようにセルフマネジメントをしたり、競技の「やり方」(行動)の探求以上に、「あり方」(心)のマネジメントに取り組むアスリートが増えていると聞きます。確かに、緊張で本調子が出せない人もいれば、まるで遊びのように楽しみ、平常心で良い結果を出すアスリートもいます。スポーツの世界では心の状態がパフォーマンスに影響するというのは、最早当たり前になっているようです。
ただ、ビジネスの世界では、これまで、あまり「あり方」や「心」に目が向けられることは少なかったかもしれません。問われるのは、やるべきことをやったか、どのような結果を出したか。仕事に、どのような心で取り組んでいるかは、あまりクローズアップされなかったように思います。
しかし、「あり方」(心)が、仕事(行動)に影響を与えるのは実感としてもわかります。例えばモノをつくる仕事の場合でも、「いい仕事で社会に貢献したい」「ずっと残る良いものを作りたい」という思いをもって仕事をする人と、「言われたから、言われた通りにやっている」という人では、細部の出来栄えが違うはずです。営業でも、自分の成績を上げようと自分中心に営業する人と「お客様に喜んでほしい」と「人に役立つことこそが営業だ」というように思っている人では、気配りやご説明の細部が違ってきます。
また、私生活に不安を抱えている時には仕事に身が入らないし、組織の中で孤立を感じている時に、いい仕事をしようという気にはならない。仕事に意義を感じている時や、家庭でも会社でも人間関係に不安がない時は、確かにいい仕事ができます。当たり前のことですが、心と行動はつながっています。
ただ仕事でもスポーツでも、結果がでるとやる気になったり、失敗したことで落ち込んだり、周囲の影響で心は変化しがちです。若い人はより、そうなるかもしれません。どのような状況においても揺らがない心を保つために、アスリートたちは、自分自身でその競技をする目的を明確にしたり、自分の心が前向きになるような言葉を自分に向けて話しかけたり、あえて仲間を応援することで自分自身の心を高めようとしているようですが、ビジネスにおいても、そうしたしなやかで強い心を保つ努力が大切なのかもしれません。
その上で、チーム全体でメンバーの心に配慮する。確かにいい会社、いいチームは人間関係が良好だと思います。お互いに心の状態に気を配り、一人でも不安な顔をしているメンバーがいれば、上司や仲間が自然と声をかけるような優しい風土がある。仕事だから、やるべきこと(行動)をやることは当然ですが、あり方(心)が伴って「いい仕事」ができるとすれば、やはり、「あり方」にも目を向けていくことがますます大事になっているのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 03 月 25 日 15:15
育てる側の成長
この春、多くの会社に新人が入社してきます。就職活動で様々な会社に出会い、最後に「この会社なら」と期待をもって入社してくれた貴重な人材。この会社で成長し、活躍してほしい。誰もが願うことですが、3年もたたないうちに、モチベーションが低くなってしまったり、辞めていってしまうこともあり、若手の育成は企業にとって本当に重要なものになっています。
新人をどう育てるか。それに答えはないのかもしれませんが、人の育成を考えた時、育成を通して新人の能力や心が育つのは間違いありませんが、実は、育てる側が成長しなければ人は育たないということもあると思います。子育てでも、子育て未経験の親が、悪戦苦闘を続けながら親として成長していきますが、もしかすると、若手の育成は「育てる側」が成長していかなければ、育っていかないのかもしれません。
真っ白な新人をどのように育てるか。初期研修ももちろん大事ですが、それ以上に大事なのは研修後の職場環境。子育ての言葉で「子供は親のいうことは聴かないけど、親のやることはみている」という言葉がありますが、子供は親のいうこと以上に、親の「あり方」に影響を受けます。会社でも、約束の時間を守らない先輩が多い職場にいれば、新人も時間を守らない。愚痴や不満が多い職場にいれば、やはりそこに染まってしまうかもしれません。逆に、忙しい中でも笑顔で頑張る人がいれば、それに染まっていく。私たちが家庭の中で親のあり方に影響を受け育ってきたように、先輩や上司の「あり方」次第で、新人はいかようにも育ちます。
期待に胸を膨らませて入社する新人が、前向きな職場に触れて「会社は期待以上」だと思うか、期待した以下の状態で、こんなはずじゃなかったと、がっかりさせてしまうか。つい、新人が辞めてしまうと辞めていく人に指を向けがちですが、育てる側の「あり方」こそ、人材育成にとっていちばん重要なものかもしれません。どのような背中を見せていくか。それが組織の力だと思います。
カテゴリー :
これからの時代の人財育成
2025 年 03 月 18 日 15:33
「お客様のため」は正しいか
顧客本位、お客様起点という言葉は、昔からよく耳にします。しかし、本当に「お客様本位」とは、どのようなことを指すのでしょうか。
お客様の言うことを何でも聞く、お客様に迎合する。これが「顧客本位」かと言えば、決してそうではありません。たとえば、お客様から「こうしてほしい」と依頼されたとしても、それがお客様のためにならないと判断した場合は、たとえ売上につながるとしても、代替案を提案したり、場合によってはお断りすることも必要です。本当に「お客様本位」の仕事とは、後者のような対応ではないでしょうか。
確かに、お客様の要望をすべて聞き入れれば、その場では喜ばれ、売上も上がるかもしれません。しかし、それが本当に相手にとって良いことなのか、その人の将来にとってプラスになるのかを考えることが大切です。人間関係においても、一時的に嫌われることがあったとしても、相手のためを思い正直に意見を伝えてくれる人の方が信頼できるものです。同じように、売上のために何でも聞く会社よりも、信念を持って真に顧客のために行動する会社の方が、最終的には信頼されるはずです。
「お客様のために」という言葉も、よく使われます。しかし、その活動が本当にお客様の役に立っているのか、ズレてしまっていないかを見極めることが重要です。
たとえば、「接客は丁寧であるべき」「しっかり時間をかけてお迎えすることが大事だ」と考え、昔から丁寧な接客を徹底しているお店があるとします。かつてはそれが喜ばれたかもしれません。しかし、現在では、丁寧な接客を好む人もいれば、スピードやスムーズさを求める人もいます。結果として、「お客様のため」と思っていた接客が、実際には喜ばれていないということが起こり得るのです。
「お客様のため」という考えは、多くの場合、過去の経験から生まれた基準に基づいています。そして、一度「こうするべき」と決めてしまうと、いつの間にか「それをやること」自体が目的となり、本来の「お客様に喜ばれることをしよう」という思いが薄れてしまうことがあります。
気づかないうちに「過去のやり方」や「こちらの都合」を押し付けてしまっている――こうしたことは、どの企業にも起こり得るのではないでしょうか。
大切なのは、「お客様のために」ではなく、「お客様の立場に立つ」こと。過去のやり方にとらわれず、「今、目の前にいるお客様が本当に望んでいることは何か」「何を求めているのか」を理解する。そして、その人にとって本当に役立つことを提供する。今求められているのは、「お客様のために」という想いを大切にしつつも、お客様の視点に立ち、真に必要とされる価値を提供する姿勢なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 お客様満足・感動の向上
2025 年 03 月 11 日 10:34
理念の力
パーパス経営やミッション・ドリブンなど、いろいろなところで、企業経営において理念やビジョンがいかに大切であるかということが言われるようになりました。しかし、家族経営の小さな商店では必要がない、そんなきれいごとでは商売はできないという意見もありますし、経営者が必要だと経営理念を掲げていても、社内でそれが語られることはなく、社員に理念が浸透していないという会社もあるのかもしれません。抽象的な経営理念なんか意味がないという考え方はまだ多数派ではないでしょうか。
しかし、個々の人生においても、自分のビジョンや信念が明確であるほど、力がわき、粘り強く取り組むようになる。こうしたい、ここを目指したいという人は確かにいきいきしています。将来のイメージを鮮明にしていくことは組織にとっても、人生にとって重要なことだと思います。
以前、一般的な絵が書いてあるジグソーパズルとすべて真っ白なジグソーパズルを比喩に、ビジョンの重要性について伺ったことがありますが、絵のあるジグソーパズル。やはりパズルは、絵があるからこそ、完成したいという意欲がわいてきます。完成形を想像できるから効率も良いし、しかもやっていて楽しい。逆に真っ白なジグソーパズルは、効率も悪いし、そもそも面白くない。確かに働いていても、やる気や意欲がわかない時は、やる意義や進む方向が見えていない時。「ありたい姿や景色」が鮮明なほどやる気がわいてきます。人にとってビジョンは意欲の源泉です。
また、自分の役割や会社の役割、つまり自分自身が社会に果たす使命を自覚して仕事をすることも重要な鍵。例えジグソーパズルだとしても、それが誰かの役に立つことで、使命を感じられればさらに力がみなぎってきます。
そんな時、こんなお話を伺いました。経営理念について学ぶ勉強会の参加者で、二代目の経営者として小さな商店を経営している方です。今まで理念など考えたことがなく、ただ漫然と仕事をしていたそうです。しかし、勉強を機に、親の話を聞いてみたり、自分のお店の役割は何か、どのようなことで役立つ店なのかと考えられました。そして、結晶のようにひとつの言葉が浮かびあがった。そして忘れないように、それを名刺に入れてお店に立ち商売を続けてきたそうです。
1年後にお会いした時、その経営者は「自分の使命を言葉にしたときから、不思議にそこに意識が向くようになり、不思議なことに業績も上がっていくようになった」と話してくださいました。そのお店は数人のスタッフがいる小さな店ですが、経営者の意識が変わっていくと業績まで変わっていくのか私も驚きました。自分の頭にあるもの、めざすことを言語化し、明確になると日々の言葉や行動も変わっていくのかもしれません。
自分や会社の役割、使命。こうありたいというビジョン。追及したいものがあるとやはり力がわいてきます。理念はジグソーパズルに書かれた「絵」だとすれば、そこに何を描くか。自分がやりたいことをやり抜くことができれば、人生幸せですね。
カテゴリー :
素晴らしい組織風土づくり 経営理念の浸透・共感
2025 年 03 月 05 日 13:30
利益の少ない仕事
仕事をしていく時、生産性や効率は重要なものだと言われています。無駄をなくす。利益の高い仕事に集中する。時間を効率的に使う。確かに理屈はその通りで、これができないと儲かりません。ただ、本当に何が無駄なのか。そんなことを考ええる機会がありました。
「利益の少ない仕事にも心をこめる」。これはカレーチェーン店「COCO壱番屋」の創業者、宗次徳二さんが創業から商売の心構えとして大切にされてきた言葉です。
壱番屋の創業は夫婦で開業した小さな喫茶店。ただそこは裏通りで誰も気づかない場所、商売としては難しい立地でした。そのような中でもお客様がわざわざ来てくださる。それが本当にうれしく、お客様に強く感謝するようなり、そこからお客様第一の商いが生まれました。そんな商売の中で、掃除や挨拶の大切さに気づかれ実践されるようになったそうです。
店前の掃除はもちろん、近所も掃除する。無駄と言われても続けられました。その内に、宗次さんの真摯な姿勢が地域の人にだんだん伝わり、お店は繁盛していったそうです。「もちろん、掃除をしているから良いと来店する人は1%もいない。ただその1%のファンが1月1人でも来てくれたら1年で12人のファンができる。それがいつか売上の一部になる」利益の少ない仕事も心をこめてきたことが壱番屋の原点だと話してくださいました。
効率や生産性は大事。ただそこばかりだと、儲かる仕事ばかりに目が向いてしまいます。そのうえ、忙しくなればなるほど手間がかかる仕事は疎かにしがち。確かにそれの方が儲かるのかもしれません。しかし、自分がお客様の側にいるときは、そう思わない。面倒な相談にも親身になって応えてくれたり、近所の掃除など、儲けにもならないことを一生懸命にやっているお店の方が心に残ります。ファンが増えるのはどちらかと考えると、本当に何が効率なのかと考えてしまいます。利益の少ない仕事にも心をこめる。長い目でみれば商売では大事なことなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 素晴らしい組織風土づくり
2025 年 02 月 26 日 10:49
「負荷」が成長をうながす
筋肉を鍛える時は身体に負荷を与えていきますが、仕事で成長するためにも、やはり負荷が必要だと思います。「自分にできるだろうか?」「無理かもしれない」ということに挑戦していく中で、能力が磨かれたり、視野が広がったりすることは、誰もが経験しています。だからこそ、若いうちは無理をしてもいい、仕事を一生懸命した方がいい、苦労は買ってでもしなさいと歳を取った人は言いたくなってしまいます。
しかし最近は、あまり無理をさせるとすぐに辞めてしまうからと、新人になるべく負荷を与えないようにする会社も多いと聞きます。ゆっくりと育てる方針でも成長してくれると思いますが、負荷がない仕事ばかりでは、筋肉は鍛えられません。視野も広がりません。結果、同じ仕事の繰り返しになってしまい、仕事がつまらなくなります。成長の実感がないまま3年目を迎えるころに会社を辞めるということも多々あるようです。
嫌なら辞めて違う会社にすぐに変わることがあたりまえの時代ですから、ひとつの会社にずっといる必要はないのでしょうが、「石の上にも三年」というように、自分の経験からも、3年を過ぎるころから自信がつき、見える景色も変わっていきます。仕事が好きになっていくのは3年目あたりではないでしょうか。
新入をどのように育成していくか。新人たちではなく、私たちに問われていることのように思います。若手が自ら自分で厳しい道、努力の道を進もうと思い、挑戦していくことがいちばんですが、それには、それをいかに支えるか。「失敗してもいいからやってみたら」と支えてくれる上司や仲間の存在、いきいきと働きチャレンジする先輩の後ろ姿など、新人が成長していく会社をみていると、やはり若い人たちの勇気が掻き立てられ、自然に未知の領域に踏み込んでみたいと思えるような環境があります。
今の人は価値観が違うという声もあります。私も若い人の価値観の違いに驚くことがありますが、時代が違えば考え方も違うのは当然。お互いに違いを認めながらも、せっかく入社してくれた若い人たちが、自ら負荷に挑み成長し、幸せになってくれるように導いてあげたいものですね。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢 これからの時代の人財育成
2025 年 02 月 10 日 16:28
現状維持は衰退
昔から、組織は環境に合わせて変化していかなければならないと言われます。確かに成長している企業は常に変化しています。過去のやり方に囚われていてはいつの間にか時代に合わなくなる。だから新しいことに挑戦しよう。この話は、誰もが頭ではわかっていることだと思います。
しかし、これがなかなか難しい。例えば、過去のやり方に固守している古い業界に、時代に合わせた新しいやり方で参入した企業が成長する。そして、その成功に追随するように古い企業がやり方を変えていく。こうしたことは、どの業界でも起こっていますが、「現状維持ではいけない」と思いながらも、自分達のやり方を自分達自身で変えていくことは、頭で考える以上に難しいことなのかもしれません。
確かに、自分の生活を考えても、慣れ親しんだことを急にやめたり、変えていくことは意外とできません。変えたほうがいいと思っても、変えることによって何が起こるかわからない不安、それを実現するための新たな努力に対するリスクなどを考えてしまうと、このままでいいと思ってしまうのが人間の性なのでしょうか。例えば、飽和状態の携帯電話業界。「他社からの乗り換え」を訴求していますが、変える手続きが面倒、今のままでいいというユーザーが多くてなかなか思う通りにいかないそうです。確かに、現状維持には、余計なトラブルも、無駄なリスクが生じません。現状維持の魅力やメリットはそこにあります。
ただ、ビジネスの場合、自分たちは現状維持でよくても、顧客も競争相手も、周りはどんどん変化していきます。現状に甘んじているといずれ時代についていけなくなるのは明白。現状維持は衰退の道です。
では、こうした現状維持の心理をどうすれば打破していけるのでしょうか。どうすれば、自分のやり方を自分で変えていけるでしょうか。
そもそも、どんなやり方をしていようと、その中にどっぷりつかっている時は、自分達のやり方が古くなっていることに気づかないのかもしれません。「別に問題がない」と思っている時に変えようという気がおきません。とすれば、まずは、自分達のやり方が、もしかすると現状維持になっているのではないかと疑ってみることがスタートなのかもしれません。
「今まではこうだったけど、この選択は本当に最適なのか?」。過去の成功体験にばかり依存していないかと自分を疑ってみたり、自問自答する時間をあえて持つ。現状維持の打破には、変えること、変わることのメリットを体験したり、リスクの小さな挑戦からやってみるなど他にもいろいろあると思いますが、「変わっていない自分を知ること」がいちばん大事な気がします。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 02 月 05 日 11:35
結果を出し続ける人
結果が大事か、プロセスが大事かという問いがあります。どちらが大事かと優劣はつけられないかと思いますが、プロの世界は結果がすべて。結果を出せないと生き残っていくことはできません。しかし、だからといって結果ばかりを気にしすぎると、手っ取り早い成果を求めてしまい、プロセスを疎かにするということもある。かといって、結果なんて関係ない、努力が大事だといって結果に目を向けないのもプロではありません。また、結果は嘘をつくこともあります。例え準備不足でも良い結果が出てしまう時もある。結果ばかりをみていると慢心が生まれ、努力しなくなることもある。結果ばかりに一喜一憂しているだけでは、結果を出し続けることはできなくなるのかもしれません。
先日、田舎の営業所に在籍しながら、毎年のように全国上位の成績をあげる、ある優績営業スタッフのお話を伺う機会がありました。訪問を嫌う顧客が多くなるうえ、顧客数が激しい過疎地での活動はかなり難しいはず。昔の営業のように、ただ訪問件数を重ねたり、「お願い」で買ってくれる時代ではありません。そんな時代で、この営業スタッフは、とにかくお客様の側にたって、その人にふさわしい商品を考えることを一番に考え続けることを大事にした活動を続けられます。無理に売りつければ嫌われるだけ。お客様が必要だと思ってもらえるなら買ってくださるはず。だからこそ、お客様の側に立つ営業であろう。その信念を貫き、ベテランになった今でも、仲間の成功事例や時には新人の成功事例にも耳を傾け、自身のヒアリングの質、お客様に最適な提案の幅を磨き続けておらます。そして、結果が出た月は何が良かったのか、結果が悪かった月は何が悪かったのか。常に自分のプロセスを分析し、修正する。「再現性がある技術」をこそがプロだと言われます。
一流のアスリートほど練習やプロセスを大事にされます。「結果は嘘をつくこともあるが、プロセスは嘘をつかない」というのは、どの業界にも当てはまるのかもしれません。
もしも、今、結果がでないのであれば、プロセスのどこかに問題があるからと考える。逆に、結果が出ている時も、プロセスの何が良かったかを考え次に活かす。結果を出し続けられる人、結果に一喜一憂せず自分を磨き続けられる人が真のプロなのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢
2025 年 01 月 29 日 14:34
ぬるい職場と働きがいのある職場
どの業界でも人材が足りない、募集をしてもなかなか入ってくれないという問題が生じています。そうした背景の中で、若手を大切に育てようという企業が増えています。しかし、あまりにも大事にしすぎ、仕事の質を厳しく問わない、負荷をかけない。そうした会社の「ゆるさ」を感じる若者が、「ここでは自分は成長できない」と判断し辞めていくという皮肉な状況が増えているそうです。大切に育てようという会社と成長を求める若手の間にすれ違い。このギャップはどうすれば埋まるのでしょうか。
企業が成長し続けるには、結果を出していない人に対して指導をしたり、指摘をしたりする必要はあります。それでなければ頑張っている人が不満を感じます。指導や指摘に緊張感がありすぎるのは問題ですが、「ミスしてもしかたない」「業績が悪くてもしょうがない」というような「ゆるい職場」では業績は伸びていきません。人は、高い目標や壁に粘り強く取り組んでこそ成長していきます。会社にとっても若手にとっても本当にいい職場はこんな「ぬるい職場」ではないはずです。人が成長できる職場とはどのような職場なのでしょうか?答えはなかなか出ない課題だと思いますが、先日、そうしたことを解決し組織全体で高い目標を実現しているある組織のお話を伺う機会がありました。
全員が高い目標を実現する営業組織にも関わらず若手の離職はゼロ。上司や部下の方にその組織の風土をお尋ねすると、皆さんが部下や後輩に強い関心を持って接していると話されました。目標が未達で悩んでいる新人や若手には、できない理由を詰めるのではなく、悩みを聞き、どうすればできるか一緒に考えていく。一緒にロープレをしたり、お客様の立場にたった話法を考えてみたり、とことん寄り添っていくのがこの組織の伝統だそうです。先輩が自分にそうしてくれたからこそ、自分も後輩にそうする。甘やかすのではなく、絶対に出来ると信じて付き合っていく。新人の成長をみんなで喜ぶ。目標が高く厳しくても辞めない理由はそんな風土があるからと上司も部下も言われていました。
自分自身を振り返っても、確かに厳しい中でも成長できたという体験は、関心を持って接してくれる上司がいてくれたからこそ。本当に働きがいのある職場とは、仲間に関心をもちあう職場、成長を第一に考えてくれる職場。それが本当の優しさがある職場なのかもしれせん。
ぬるい職場、働きがいのある職場とは何か。改めて考え直す機会になりました。
カテゴリー :
働きがい・やりがいの向上
2025 年 01 月 20 日 15:41
本物を生み出す理念
美味しい食べ物や本物の商品を求めて遠くからでも人がくるということがあります。SNSの時代にあって人が良いと言ったものがクチコミで広がり、地方のお店でもあっという間に人が集まることがあります。しかし、一時的なブームではなく、ずっと評判になる「本物の商品」を提供し続けることは、そんなに簡単なことではありません。今は様々な商品の品質が向上していく時代。いくら良い商品を作っても、これで良いとあぐらをかいていてはそれ以上にはなりません。より良いものを提供したいという信念がなければ、本物を提供し続けるのは難しいのではないでしょうか。
埼玉県日高市に年間400万人もの人を集める農業のテーマパーク「サイボク」という施設があります。ここには加工豚肉の直売店やレストラン、子どもが遊べるアスレチック広場や温泉施設があり、老若男女が一日中楽しめる施設です。先日、その施設を訪問した時は平日でしたが、たくさんの人で賑わっていました。
なぜ、こんな場所に人が集まるのか。そこには歴史がありました。サイボクの始まりは豚の牧場。終戦後、日本人には栄養がいちばん大事だと、創業者の笹崎達雄氏が種豚の改良や養豚を興したのが始まり。良い豚肉を作ることから始まり、ソーセージなどの加工食品、そして小売りにも乗り出しながら、買い物に来る人に少しでも楽しんでもらえるようにと施設を増やしてきたことで、今のような場所になっていったそうです。自分で作り、自分で売ると消費者の声が聞こえてきます。その声に耳を傾けながら養豚や加工を改善する。もっと良いものを提供したいという情熱が世界が認める品質を作り、口コミが広がり日本全国からお客様が買いにくるようになったそうです。
健康に良いものを届けたい。戦時中、やせ細りながら戦う日本人をみて、日本に養豚を広げ、健康に貢献していきたいと思った創業者の創業の精神は今もスタッフに浸透しています。ひとつのソーセージでも毎月のように改善、改良がおこなわれているそうです。世の中に役立ちたい、サイボクの事業の中にそんな思いを感じます。競合他社を意識するのではなく、とことん顧客に向かっていくことで、どこにもない施設になった。サイボクの理念が独自価値を生み出しています。
どの企業も、他社より良くなりたい、差別化をしていきたいと思っているはずですが、差を生み出すために必要なのは、マーケティングなどではなく、最後は人のために役立ちたいという情熱や理念なのかもしれません。
カテゴリー :
「いい会社」が実践する理念経営 経営理念の浸透・共感
2025 年 01 月 15 日 10:46
チームで分かち合う喜び
よく顧客満足の教科書に「良い応対」の事例が出ています。マニュアルを超え、お客様の心に寄り添って対応することでお客様が感動され、ファンになる。そんな事例を題材に「良い応対」のあり方が示されています。確かにこうした事例は大事なものだと思いますが、現状、個人が「良い応対」ができる範囲には限界もあります。本当は持ち場を離れても困っているお客様のために時間を使いたい。しかし現状は人手不足で持ち場を離れる訳にいかない。ギリギリの人数で対応している限り、おもてなしをしたいと思ってもできない場面はたくさんあります。
こうした時に、チーム全体が同じ思いで働けていれば、みんなで助け合って「お客様」に向かっていくことができます。例えば、部門を超えて助け合う体制が出来ていれば、経理部門が助けてくれるかもしれません。また、情報共有がしっかり出来ていれば、顧客の安心感も高まります。車でいえば、担当した営業と修理のスタッフがしっかり情報共有をし、自分の好みや不安を共有していてくれるお店。「担当から聞いておりました」という一言から始まり、部門を超えても同じように対応してくれることほど嬉しいことはありません。一人の力でできないことも、チームの力があればできます。
今、どの企業も人手不足が続く時代の中で、高い顧客満足を生み出すお店や企業を見ていると、個人の頑張りによる「おもてなし」ではなく、「チーム全体でのおもてなし」ができている企業かもしれません。
みんなが同じ思いを持ち、みんなで助け合ってお客様に向かっていく。そんな職場は、働く側にとっても気持ちが楽でしょう。みんなで頑張ってみんなが喜びをわかちあうことができるので、個人で頑張る時よりもやりがいも高いはずです。仕事の終わり、スタッフみんなが顔を合わせ「今日もお客さんに喜んでもらえたね」とハイタッチをして喜び分かち合う。みんなでお客様の満足に向かって協力していく感覚は、一度味わうと忘れられません。これから先、職場の中でもっと人が少なくなります。個々が頑張ることに限界があるとすれば、ひとつの目的に向かって助け合うチームづくりがどの会社にももっと求められていくように思います。
カテゴリー :
お客様満足・感動の向上 働きがい・やりがいの向上
2025 年 01 月 07 日 10:29
脱皮と挑戦
新年あけましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬ御高配にあずかり厚く御礼申し上げます。
本年も皆さまのお役に立てるよう、精一杯努力して参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
昨年はお正月の能登大震災から始まり、政治でも経済でも社会でも様々な出来事が起こった一年でした。まさに誰も予測できないVUCAの時代の中にいることを実感します。
そもそもVUCAとは「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を取った言葉ですが、まさに「正解を誰も知らない」あるいは「正解はいくつもある」ということ。とにかくこれまでのやり方が通用しない、従来の延長線上の考え方だけではやっていけない時代であることは間違いありません。
過去のやり方が通用しないのならば、新しいやり方に挑戦していくしかありません。そう考えると、VUCAの時代における大事なマインドはまず「試してみる」、まず「やってみる」こと。小さな実験や仮説検証を繰り返して進んでいく。大きくやろうとせずに小さな実験をしてみて早くに失敗をする。そこから次のやり方を考えて、次に進む。失敗をしないように慎重になる姿勢より、あえて失敗を求めにいくくらいが丁度良いのかもしれません。
また、正解がわからない時は、一人でやるよりもいろんな人と相談しながらチームでやることの方がうまくいくものです。まったく違う分野の人、異なるバックグラウンドを持つ人と話し合うと、今までにない気づきが生まれることがありますが、例えば、営業だけの会議に製造の人が入って話し合うなど、職種を超えて智恵を出し合って仕事をしていくことも大事なことなのだと思います。
ただ、考えてみれば戦後の焼け野原の時代だって誰も先がわからない。誰もやらなかった新しい事業を立ち上げてきた先人もいます。わからないなら、やってみる。シンプルな言葉ですが、挑戦をあえて楽しんでいくのがいちばん大事なマインドかもしれません。
そういえば、今年は「巳年」ですが、蛇は脱皮をすることから巳年は「復活と再生」の年でもあるそうです。過去のやり方を脱皮していく一年なのかもしれません。
カテゴリー :
いきいき働くための仕事の姿勢